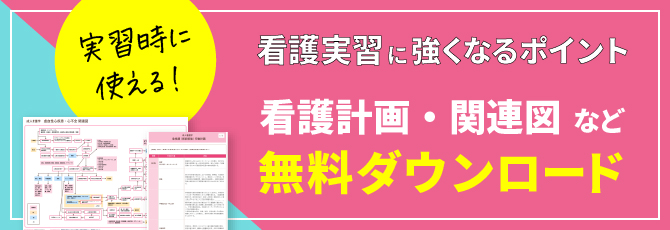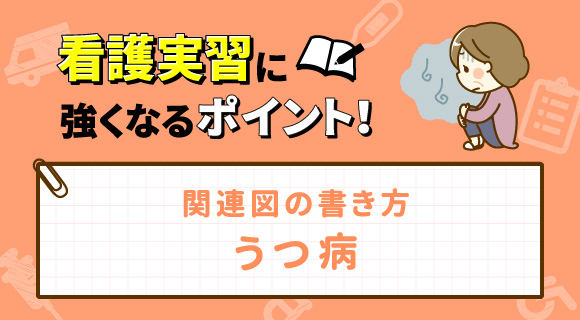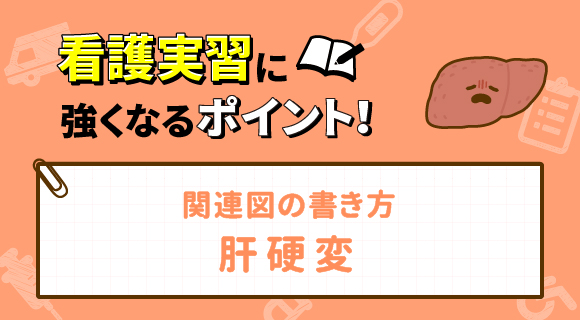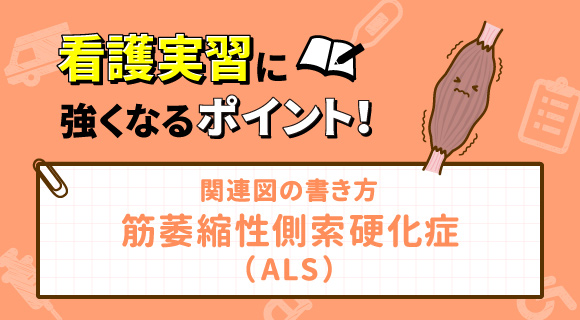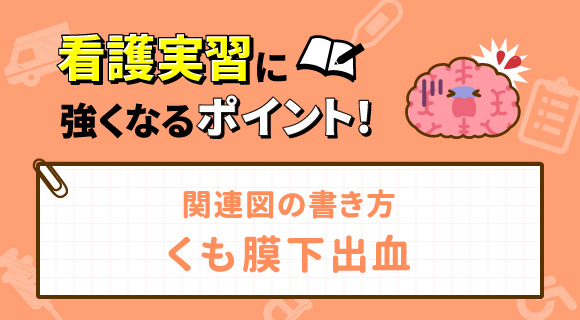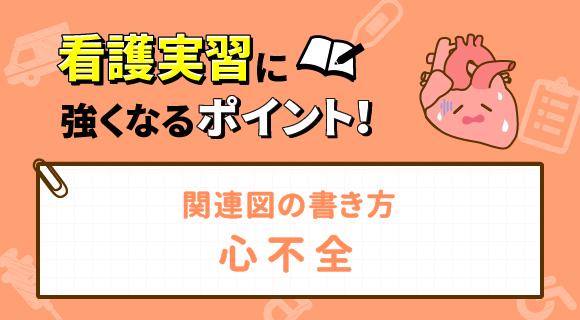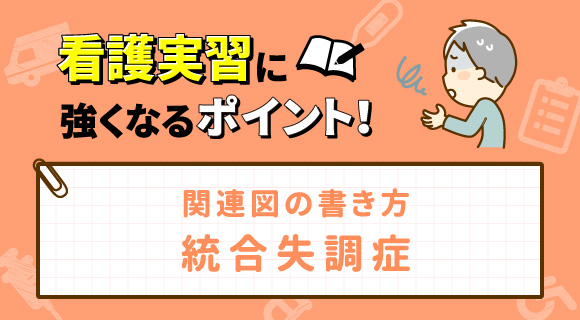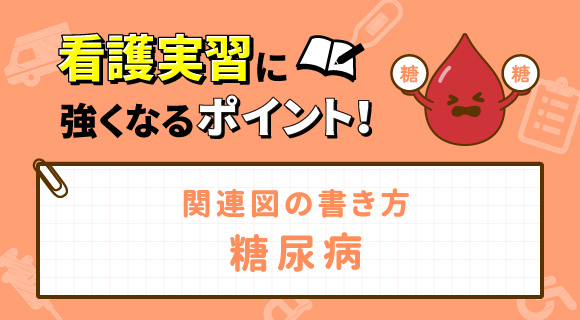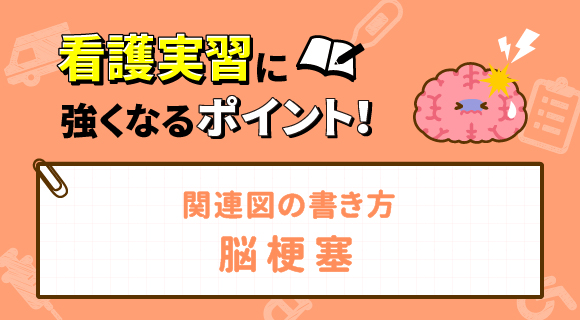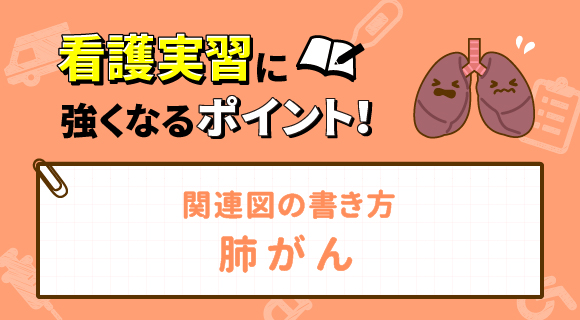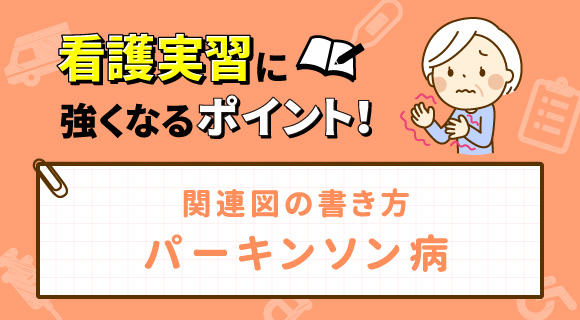ネフローゼ症候群とは、腎臓の糸球体という血液をろ過する部分に障害が生じることで、大量のタンパク質が尿中に漏れ出す病態です。これにより、血液中のアルブミン濃度が著しく低下(低アルブミン血症)し、血管内の浸透圧が下がることで、水分が血管外へ移行しやすくなり、顔や四肢、腹部、さらには全身に浮腫が現れます。また、血液中のアルブミンが減ると、体はその不足を補おうと肝臓でアルブミンや脂質を合成します。その結果、高脂血症(血中コレステロールや中性脂肪の上昇)も合併するのが特徴です。

ネフローゼ症候群の原因は、大きく分けて原発性(一次性)と続発性(二次性)に分けられます。
原発性(一次性)
小児に多い微小変化型ネフローゼ症候群(MCNS)、膜性腎症(MN)、巣状分節性糸球体硬化症(FSGS)などがあり、腎臓の病変が主体となります。微小変化型では、かぜなどのウイルス感染がきっかけで発症することが多く、MNやFSGSにおいても一部の症例でウイルス感染が誘因となる可能性が指摘されています。
続発性(二次性)
全身性エリテマトーデス(SLE)、糖尿病性腎症、B型肝炎や梅毒などの感染症、悪性腫瘍、薬剤性などが原因となります。
治療の第一選択はステロイド薬で、特に微小変化型では高い効果が期待できます。しかし、ステロイドに反応しにくい場合や再発を繰り返す場合には、免疫抑制剤の併用や支持療法(利尿薬、アルブミン製剤、高血圧治療薬など)が必要になります。また、ステロイド使用に伴う副作用(ムーンフェイス、骨粗鬆症、感染症など)への注意も欠かせません。
再発しやすい疾患であるため、長期的な治療と生活管理、感染予防、栄養管理などの包括的なケアが必要となります。