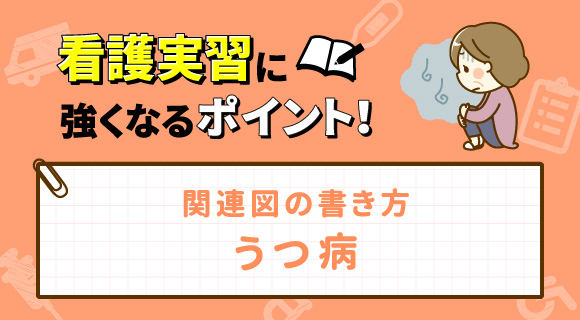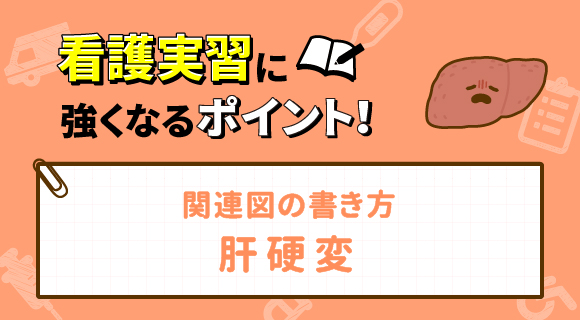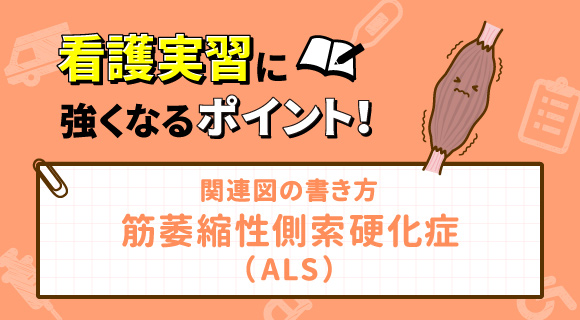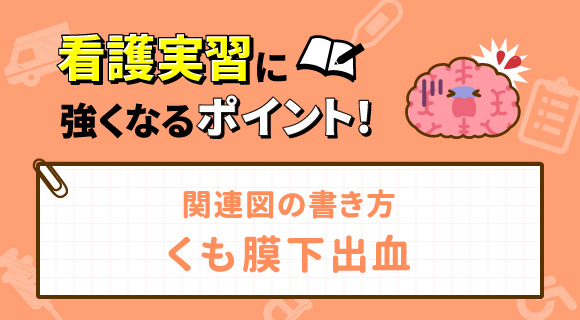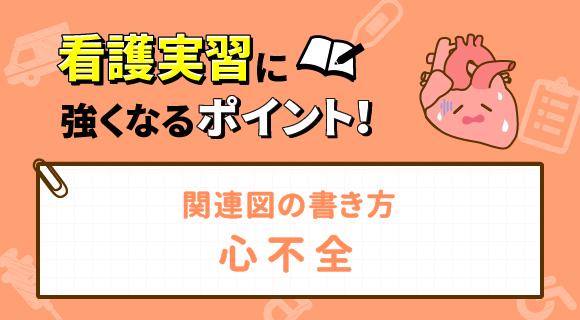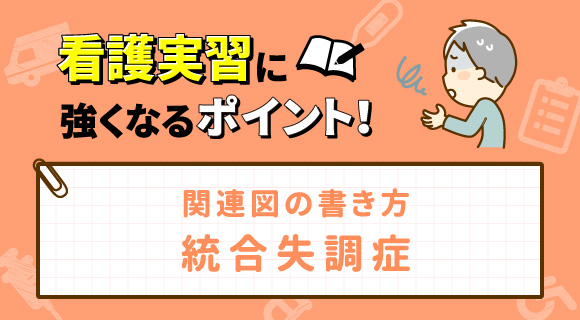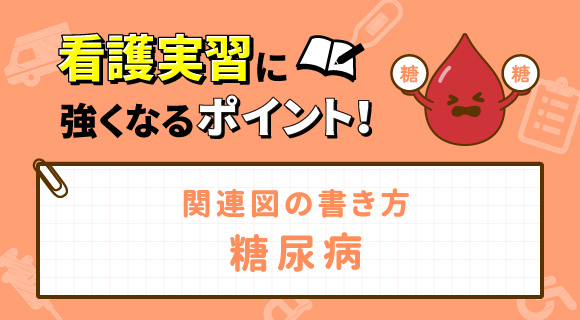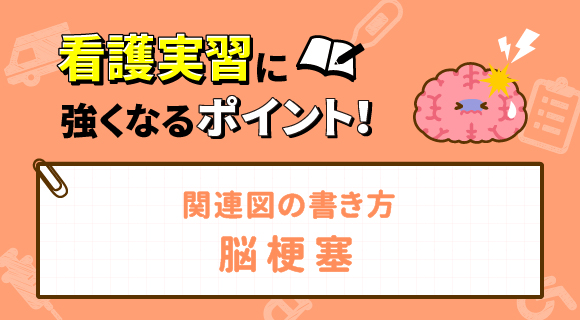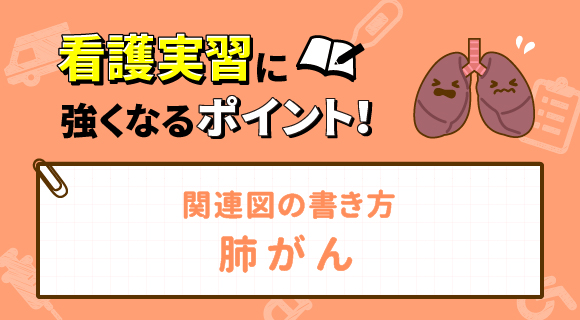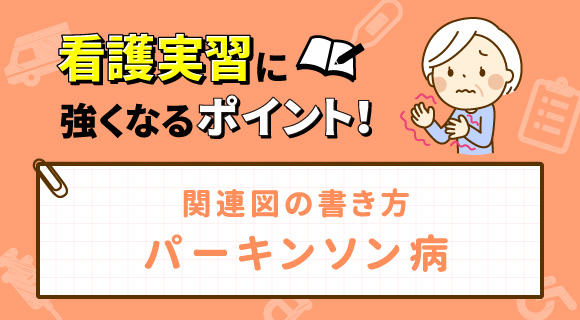脂質異常症とは、血液中の脂質(LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪)が正常範囲から外れた状態をいいます。
●高LDLコレステロール血症(悪玉コレステロール↑)
LDLコレステロールは肝臓から全身にコレステロールを運ぶ働きをしますが、増えすぎると血管壁に沈着してプラークを形成し、動脈硬化を進めます。
●低HDLコレステロール血症(善玉コレステロール↓)
HDLコレステロールは血管壁にたまった余分なコレステロールを肝臓に戻す働きがあります。これが少ないとコレステロール除去作用が低下し、動脈硬化が進行しやすくなります。
●高トリグリセリド血症(中性脂肪↑)
中性脂肪はエネルギー源として重要ですが、過剰になると小型で動脈硬化を起こしやすい「小型LDL(small dense LDL)」が増え、血管障害のリスクが高まります。
これらはいずれも動脈硬化を促進し、心筋梗塞や脳梗塞など重大な血管障害の発症リスクを高めます。

リスク因子には、以下が挙げられます。
- 加齢
- 食生活(高脂肪・高カロリー食、過食、飲酒)
- 運動不足
- 肥満・内臓脂肪型肥満
- 喫煙
- 糖尿病・高血圧などの生活習慣病
- 遺伝的要因
脂質異常症は自覚症状に乏しいため、健康診断で初めて指摘されることが多いです。進行すると動脈硬化性疾患として血管障害を引き起こすため、早期発見・治療が重要となります。
診断には血液検査が用いられ、以下の基準で異常とされます。
- LDLコレステロール:140mg/dL以上
- HDLコレステロール:40mg/dL未満
- 中性脂肪(TG):150mg/dL以上
治療は食事療法・運動療法が基本であり、必要に応じて薬物療法(スタチン系、フィブラート系、エゼチミブなど)が行われます。