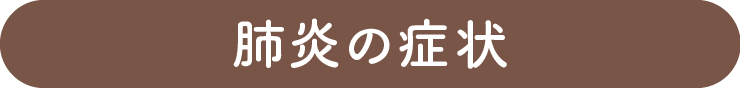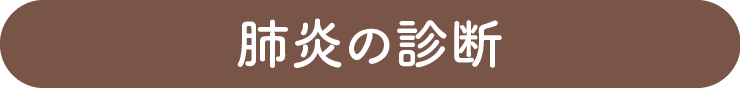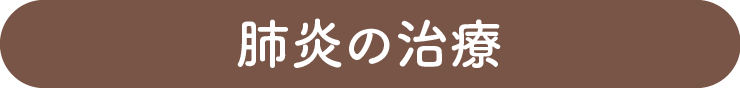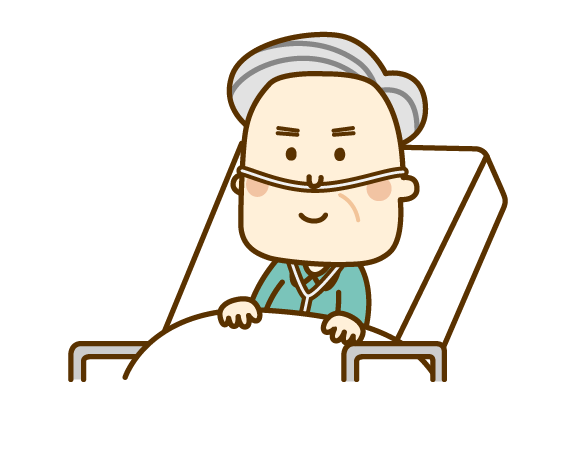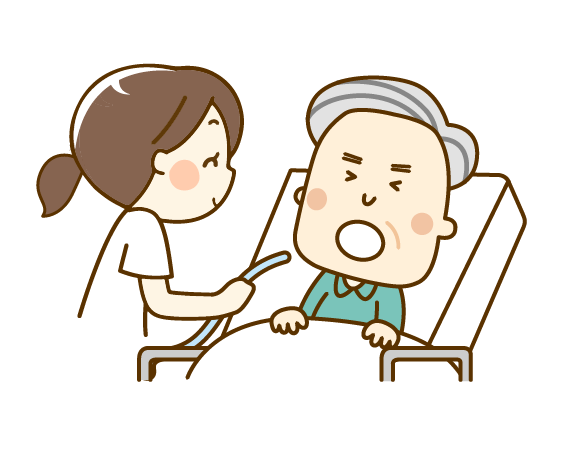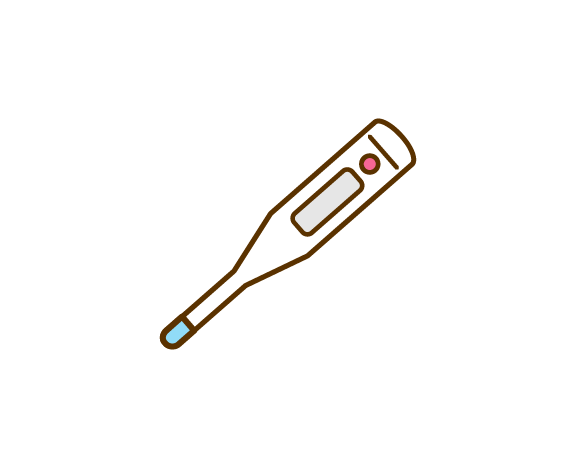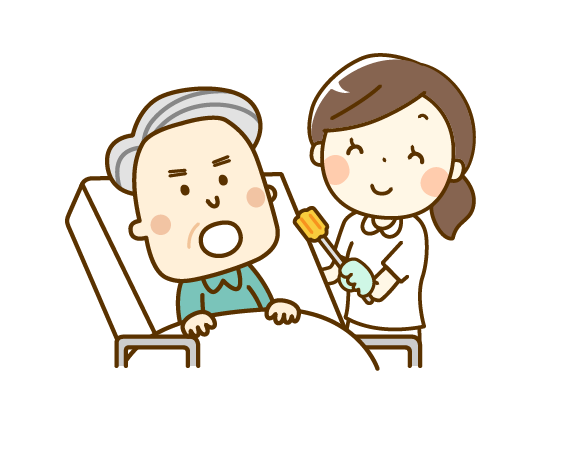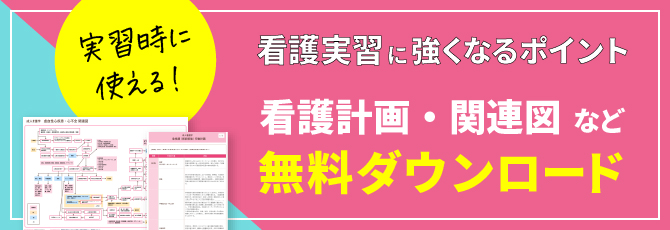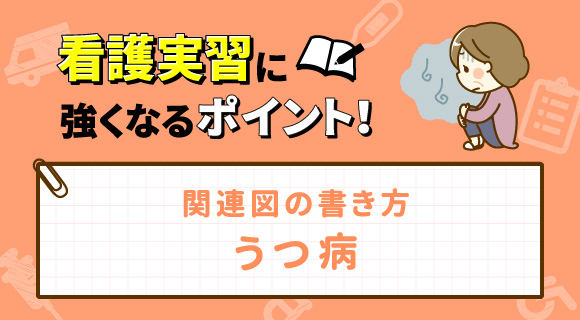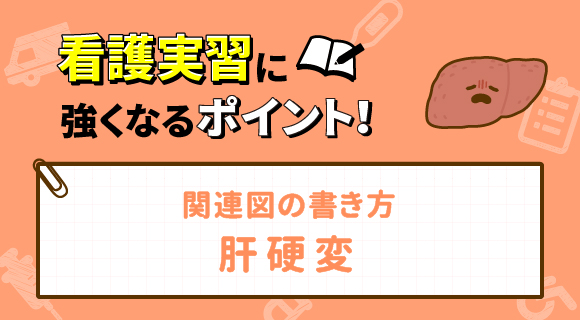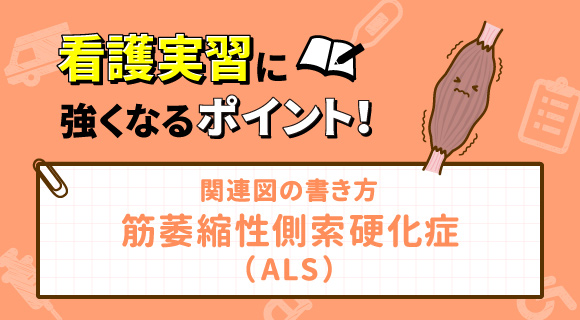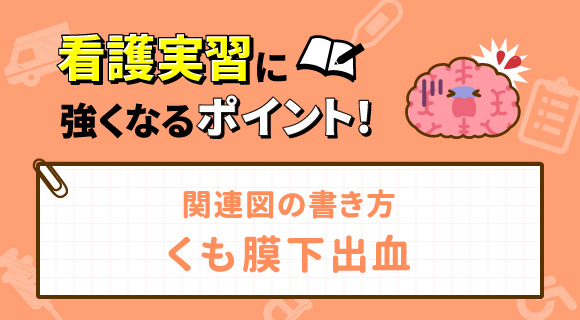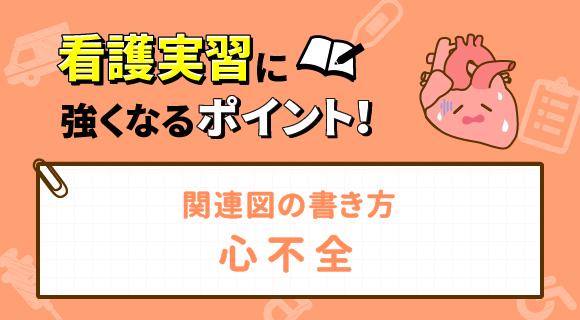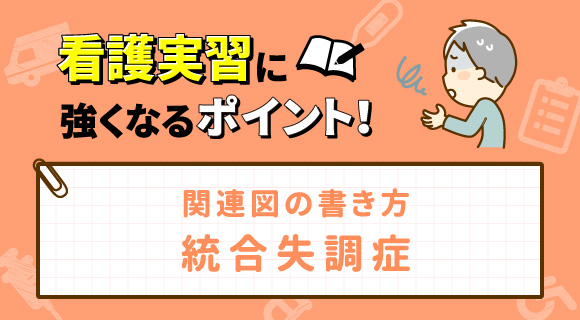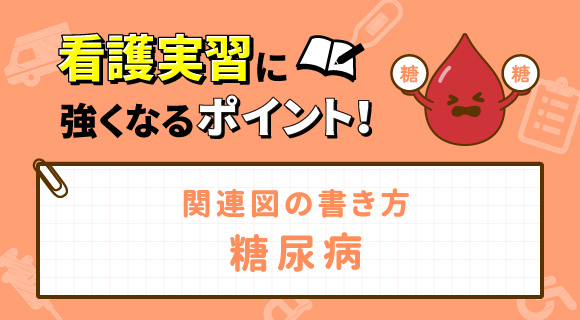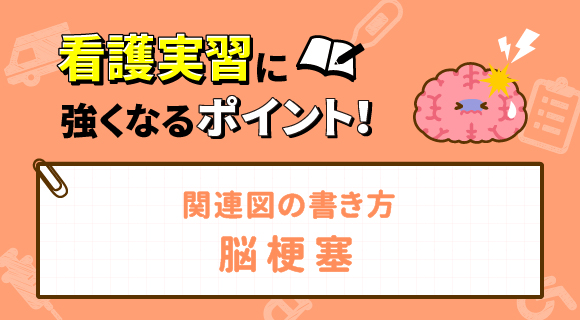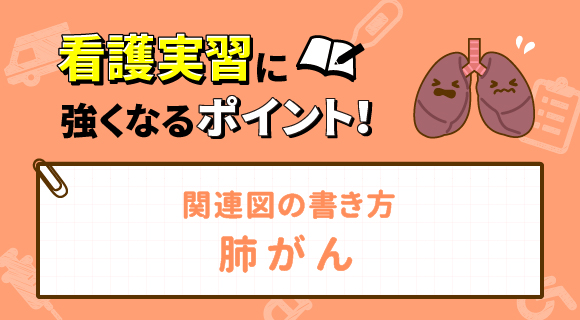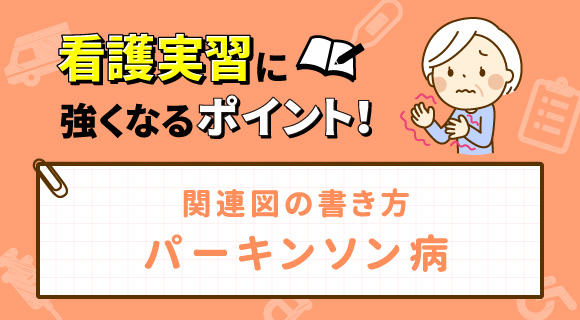肺炎とは、細菌やウイルスが原因で肺の中に炎症がおこる急性呼吸器感染症で、肺胞に炎症がおこります。
肺胞はガス交換を行っており、酸素を取り入れ二酸化炭素を排出する役割です。細菌やウイルスが原因で肺炎がおこると肺胞が障害されるため、呼吸困難感や息切れがあらわれます。発熱や咳辣、喀痰や胸の痛みなどもあらわれ、重症化すると「ヒューヒュー」「ゼーゼー」といった喘鳴症状もみられるようになります。
高齢者の場合、呼吸器症状ではなく食欲低下や意欲低下を主訴に来院されることも多く、早期に肺炎と診断しづらいケースもあるため注意が必要です。
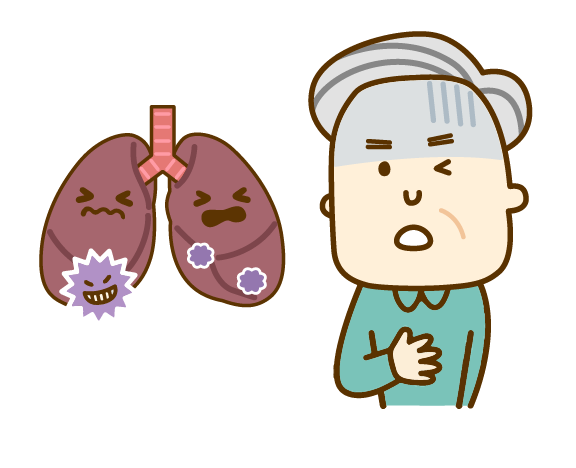
肺炎の診断には、レントゲン検査やCT検査、採血検査が行われます。肺炎は重症化すると酸素投与が必要となったり急変リスクが高くなったりするため、全身状態の観察が重要です。
主な治療は、抗生剤投与で感染の原因となっている細菌やウイルスの除去です。肺炎の予防には、肺炎球菌ワクチンの接種や日頃から手洗い、うがい、マスクの着用を行い、風邪をひかないように対策しましょう。喫煙されている人やCOPDを患っている人は、さらに肺炎のリスクや重症化するリスクが高いため予防が重要になってきます。