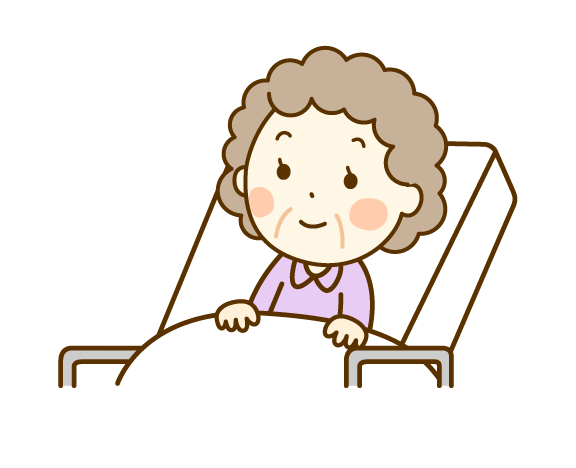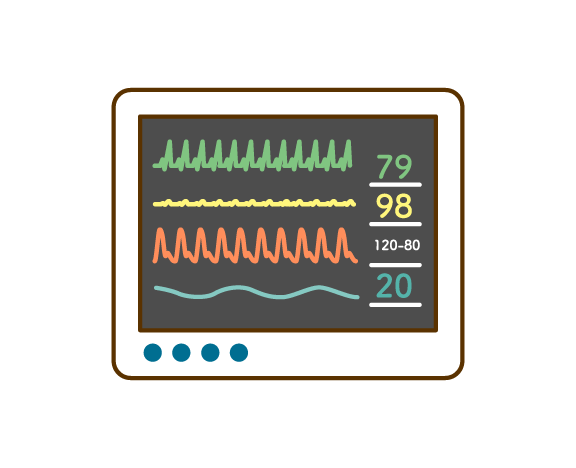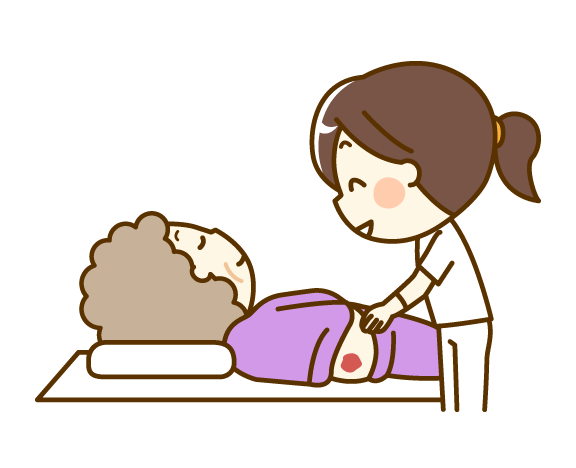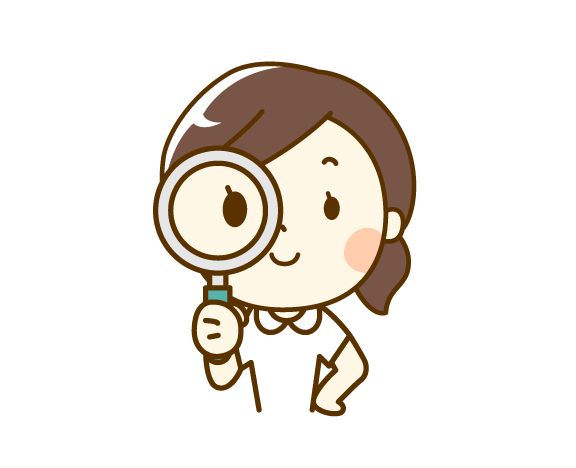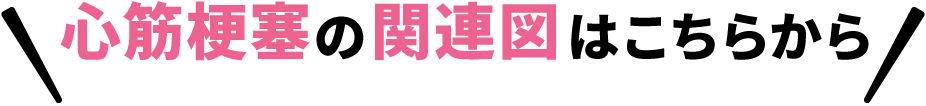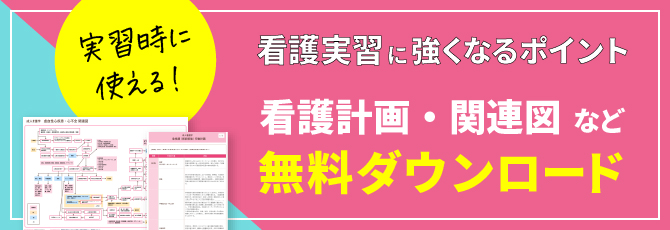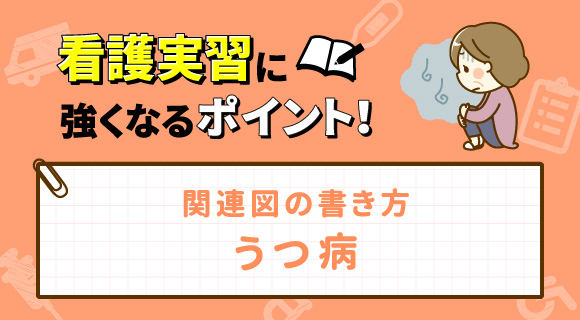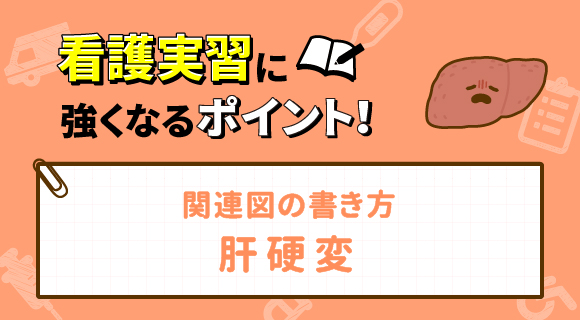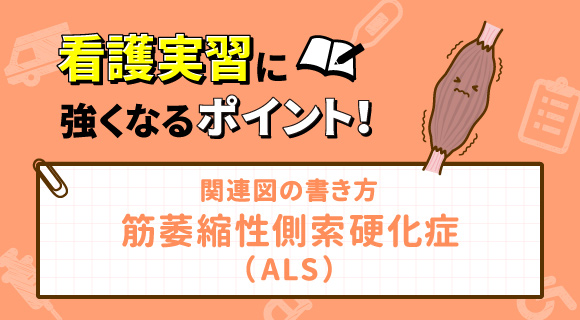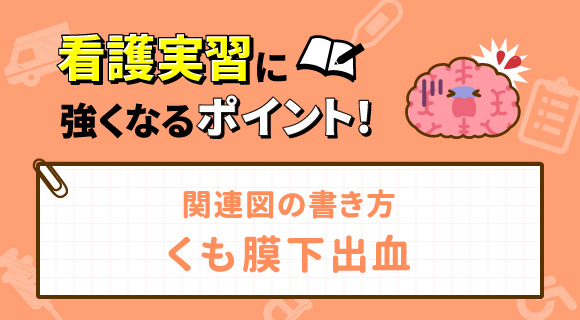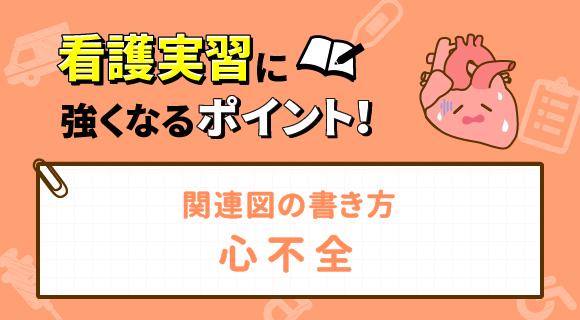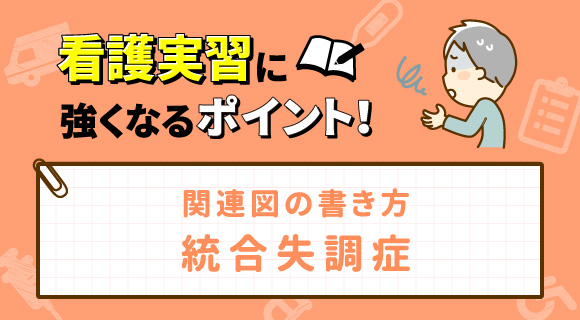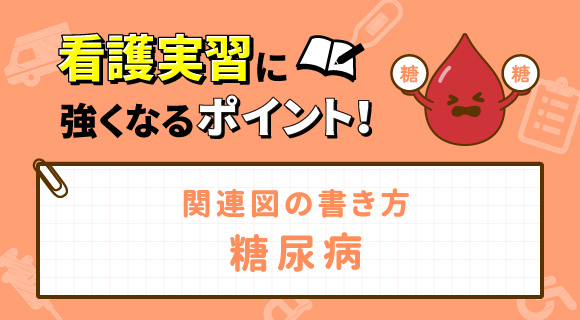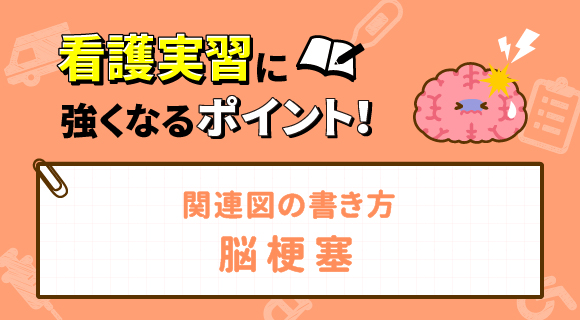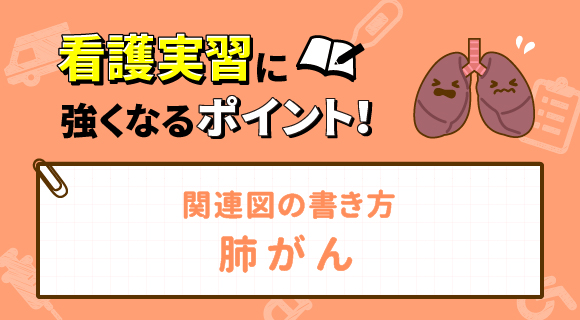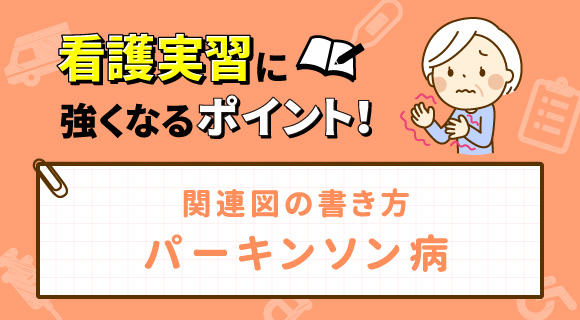心筋梗塞とは、主に心臓の栄養血管である冠動脈の動脈硬化が原因で起こる虚血性心疾患です。
血管壁の内側に入り込んだLDLコレステロールを退治するため、免疫細胞やその他の細胞が血管壁に入りアテローム(粥腫)を形成します。アテロームが増殖して隆起した病変がプラークです。
プラークの破綻やびらんの発生により血栓が形成され、冠動脈内腔が急速に狭窄・閉塞し、心筋が虚血・壊死に至ります。心筋が壊死すると全身に血液を送ることができず死に至るため、一刻も早い処置が必要です。
動脈硬化以外に、冠動脈の攣縮、冠動脈の血管炎、上行大動脈解離、心原性塞栓症が原因の場合もあります。
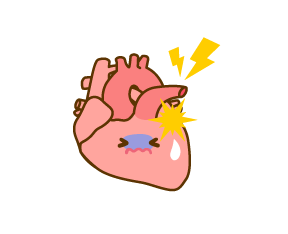
壊死した心筋の範囲により、非ST上昇型心筋梗塞(NSTEMI)とST上昇型心筋梗塞(STEMI)に分類されます。NSTEMIは、心内膜下の壊死にとどまり、STEMIは心筋全層の壊死を来たした状態で、STEMIのほうが緊急性が高いです。