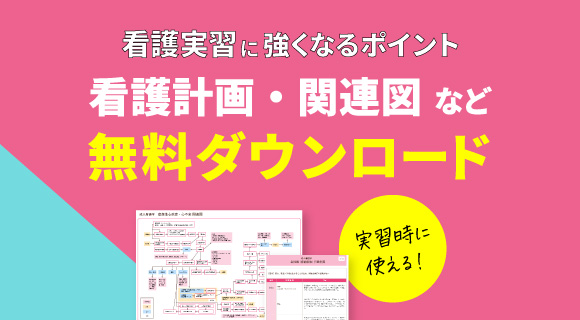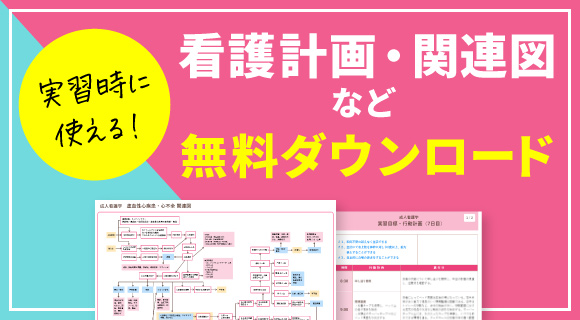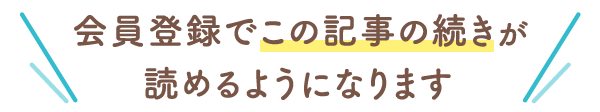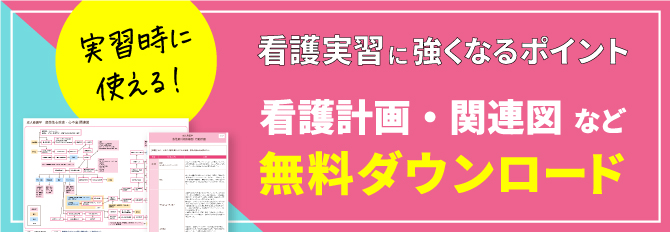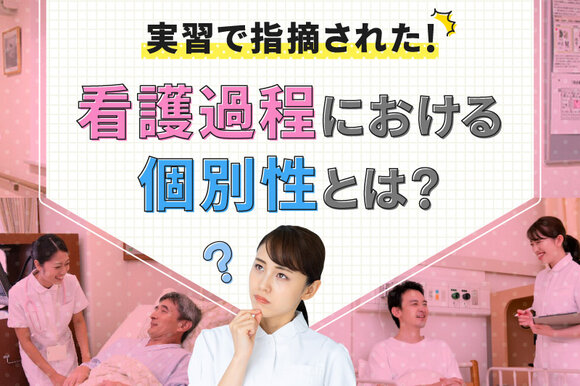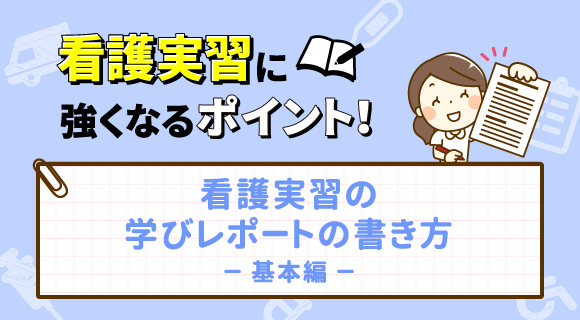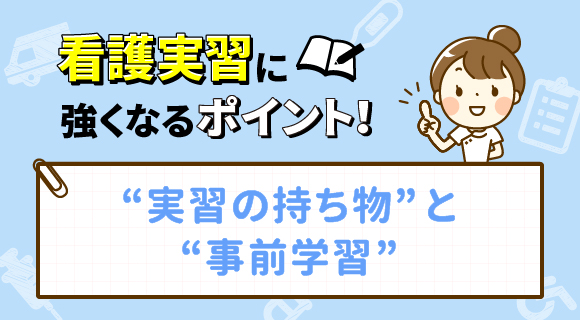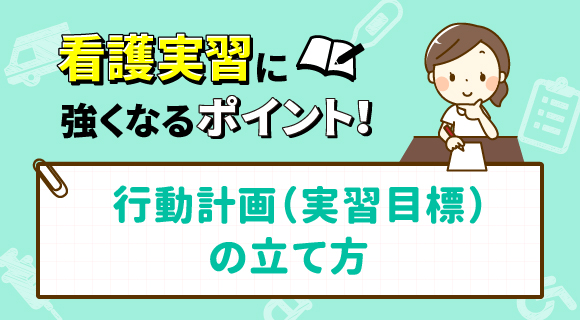事例あり!成人・急性期看護過程の書き方【看護問題・看護計画編】~急変リスクの考慮

急性期実習では、急変のリスクが常に伴うため、わずかな状態の変化が生命に直結する可能性があります。現在の状態を的確に把握し、今後起こり得るリスクを予測し、適切な看護を提供する力が求められます。
本記事では、アセスメント編の事例をもとに、成人・急性期看護過程における看護問題や看護計画の書き方を具体的に解説しています。
急変リスクを考慮した看護問題を考えよう!
急性期の特徴
急性期における患者さまは他の領域と異なって、疾患や外傷などによって身体機能が急激に低下しており、生命の危機に直面している場合が多いのが特徴です。
状態が急激に変化するリスクを常に抱えているため、急性期実習では患者さまの全身状態を正確に把握し、常に変化に注意を向ける必要があります。
バイタルサインの微細な変動や自覚症状の訴え、表情や動作などから、急変の兆候をいち早く察知しましょう。
現在の病態だけでなく、予測されるリスク要因を理解し、先手を打った観察やケアを行うことが重要です。
例えば、出血、呼吸状態の悪化、感染症の進行など、予測される合併症を頭に入れ、日々の看護に活かしていく姿勢が必要です。
周手術期でよくあげられる看護問題の例
周手術期の看護問題を取り上げる理由として、看護学生は急性期実習において、周手術期の患者さまを受け持つことが多いからです。
周手術期では、生理的・心理的な影響や急変のリスクが高く、適切な看護計画の立案が求められます。
周手術期の看護問題を考える際には、以下の3点が重要となります。
患者さまの状態把握
手術に伴う身体的変化はもちろん、手術への不安や恐怖といった精神的な側面も含め、総合的に評価することが大切です。
合併症の予防と予測
手術後は感染や深部静脈血栓症(DVT)、呼吸器・循環器系のトラブルなど、さまざまな合併症のリスクがあるため、早期から予測を立て、適切な予防策を講じる必要があります。
疼痛の管理
手術後の疼痛は早期離床を妨げ、身体の回復に大きな影響を与えます。
患者さまの訴えを的確に把握し、鎮痛薬の適切な使用や非薬物療法(温罨法、リラクゼーション、姿勢の調整など)を症状に合わせて個別に対応することが重要です。
看護問題の具体例
♯1 心不全による呼吸困難感と心不全増悪のリスク
♯2 冠動脈再狭窄・血栓形成のリスク
♯3 再発や退院後の生活に対する不安とストレス
♯1 心不全による呼吸困難感と心不全増悪のリスク
S氏は、左前下行枝(LAD)近位部の高度狭窄による急性心筋梗塞を発症しました。
LADは、左心室前壁・心尖部・心室中隔前2/3を栄養する主要な冠動脈であり、LAD近位部の高度狭窄により急性心筋梗塞を発症した場合、左心室の収縮機能が低下し、左心不全を引き起こりやすくなります。それに伴い、心機能低下や肺うっ血を引き起こしており、体動時の酸素需要が増大し、息切れや呼吸困難が生じている状態です。
適切な全身管理を行うことで体動時の呼吸困難感の軽減や睡眠障害の改善、ADLを向上させることを目指す必要があります。加えて、S氏は高血圧や糖尿病といった基礎疾患を抱えており、慢性的な心不全へ進行するリスクが非常に高い状況です。
心不全の進行を予防するためには、病態のモニタリング、適切なセルフケア支援、生活習慣の改善へ向けた指導が不可欠となります。
♯2 冠動脈再狭窄・血栓形成のリスク
血管内にステントを留置したことによる血栓形成リスクに加えて、S氏は糖尿病や高血圧、脂質異常症などの既往歴や、LAD近位部の病変であることからも、再狭窄・血栓形成のリスクが高いことが予測されます。
抗血小板薬の確実な服薬管理、 血圧・血糖値の管理を行うとともに、自覚症状の観察や心電図波形のモニタリングを強化する必要があります。
♯3 再発や退院後の生活に対する不安とストレス
S氏の発言から、突然の発症による心理的ショックや、生活習慣の制限へのストレス、仕事復帰や社会的役割の喪失に対する不安などが感じられます。
心理的なストレスや不安は、心臓にさらなる負担をかけるため、心理的サポートも重要な支援となります。
患者さまの状態に合わせた看護計画を書く時のポイント
患者さまの状態を詳細に把握する
急性期においては異常の早期発見が重要です。
こまめにバイタルサインを測定し異変の有無を確認するとともに、呼吸状態や循環動態の変化を見逃さないよう注意しなくてはいけません。さらに、患者さまの訴えを丁寧に聞き、些細な変化にも敏感に対応することが求められます。
患者さまの状態によって看護計画を見直す
急性期では病状が急激に変化する可能性があるため、看護計画は常に患者さまの状態を観察しながら柔軟に修正する必要があります。
バイタルサインの変動や呼吸・循環の変化、意識レベルの変化などをこまめに評価し、必要に応じてケアの方針を見直すことが重要です。また、治療の進行や医師の指示の変更時にも迅速に看護計画を見直し、患者さまの状態に合わせた適切な看護を提供することが求められます。
看護計画の具体例とポイント
心不全による呼吸困難感の軽減と増悪リスクの低減
| 看護問題 |
|---|
| ♯1 心不全による呼吸困難感と心不全増悪のリスク |
| 目標 |
|
| OP |
|
| TP |
|
| EP |
|
看護計画記載のポイント
心不全の増悪は急速に進行するため、早期発見・早期対応が重要であり、バイタルサインや呼吸状態の変化を細かく観察することが必要です。また、患者が心不全の増悪兆候を自身でも認識できるよう自己管理能力を向上させる教育を行いましょう。
医師・薬剤師・栄養士・リハビリスタッフと連携し、多職種による包括的なケアを提供するとともに、安静が必要な時期と離床を促す時期を見極め、患者の状態に合わせた無理のない活動量の調整を行います。加えて、患者の状態に応じて看護計画を適宜見直し、継続的な観察と適切な介入を行うことで、心不全による呼吸困難感の軽減と増悪リスクの低減を目指します。
安心して社会復帰できるよう支援する
| 看護問題 |
|---|
| 不安を軽減し、安心して社会復帰できるよう支援する |
| 目標 |
|
| OP |
|
| TP |
|
| EP |
|
看護計画記載のポイント
患者さまの不安に寄り添い、否定せずに傾聴しながら適切な情報提供を行うことで安心感を与えます。
漠然とした説明ではなく、患者の生活スタイルに合わせた具体的な指導を行い、行動変容を促しましょう。
また、退院後の生活設計や職場復帰に向けて、家族やリハビリスタッフ、ソーシャルワーカーなどと連携し、社会復帰へのサポートを強化します。加えて、継続的な服薬や生活習慣の改善の重要性を理解し、実践できるよう指導することで、再発予防の意識を高めていきます。
患者の心理的ケアと具体的な生活指導を組み合わせることで、不安を軽減し、安心して社会復帰できるよう支援する必要があります。