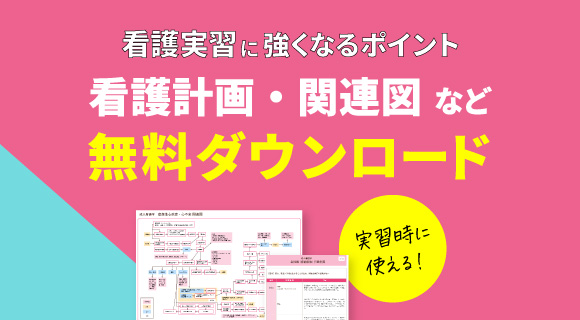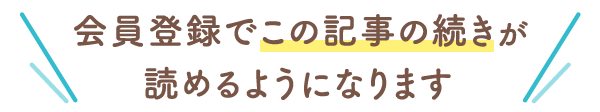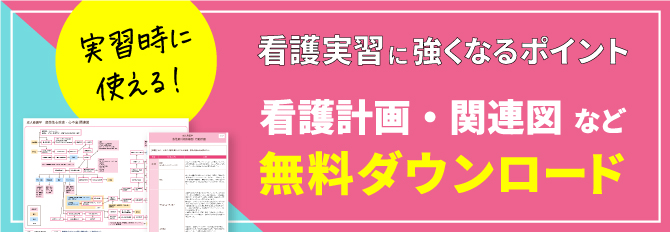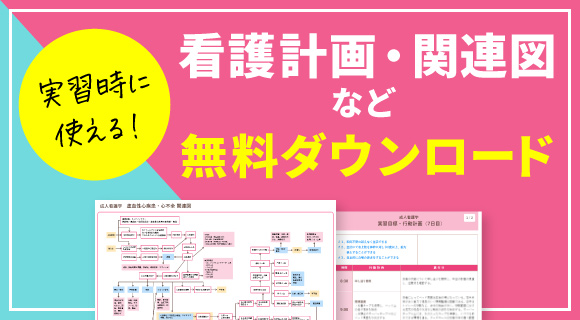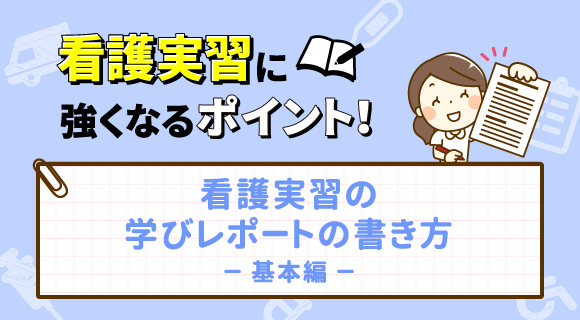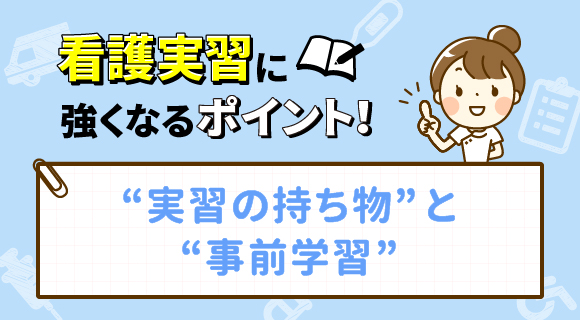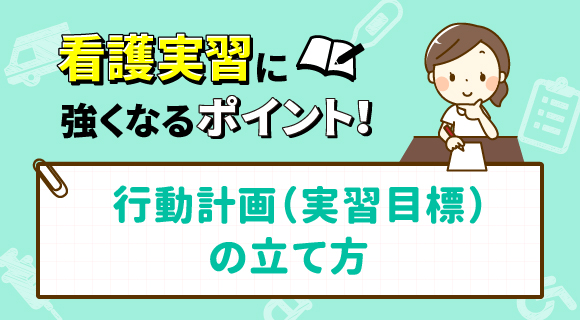事例付き!退行性変化・進行性変化から考える看護計画の立て方~子宮復古と乳房観察~

産褥期には「退行性変化」と「進行性変化」が同時に進みます。看護実習での褥婦さんへの看護ケアでは、この両面を観察し、正常な経過かどうかを判断することが重要です。
退行性変化(子宮復古)の観察項目
観察する目的
子宮復古の観察は、褥婦の回復過程を把握し、異常の早期発見や予防につなげるために行います。具体的には以下の点に注意して観察します。
- 子宮が正常に収縮・退縮しているかを確認する
- 感染や出血の兆候を早期に発見する
- 異常な経過(子宮復古不全)を予防・早期介入につなげる
観察項目と観察方法
子宮底や悪露は、産褥期の母体が正常に回復しているかを判断する重要な指標です。以下の表では、胎盤娩出直後から産褥14日目までの経過日数に応じて、子宮底の高さや硬さ、悪露の量や性状の目安をまとめています。観察時には、この標準的な経過と照らし合わせながら、個別の変化を確認することが大切です。
子宮の復古と悪露の変化
| 経過日数 | 子宮底の高さ | 子宮底長 | 悪露 |
|---|---|---|---|
| 胎盤娩出直後 | 臍下2〜3横指 | 11〜12cm | 赤色〜暗赤色 多量 新鮮血性 甘酸っぱい特有の臭い |
| 分娩後12時間 | 臍高〜臍上1横指 | 15cm | |
| 産褥1〜2日目 | 臍下1〜2横指 | 12〜13cm | |
| 産褥3日目 | 臍下2〜3横指 | 10〜12cm | 暗褐色〜褐色出血量減少 血液成分減少 白血球増加 血色素が変色して褐色化 軽い臭気 |
| 産褥4日目 | 臍と恥骨結合上縁の中央 | 9〜10cm | |
| 産褥5日目 | 恥骨結合上縁3横指 | 8〜10cm | |
| 産褥6日目 | 恥骨結合上縁2横指 | 7〜8cm | |
| 産褥7〜10日目 | 恥骨結合上縁にわずかに触れる | 6〜9cm | 黄色〜クリーム状 悪露量減少 漿液あるいはクリーム状 血球成分は白血球が主体 |
| 産褥11〜14日目 | 腹壁上から触知不可 | 灰白色〜透明悪露量大幅 減少 子宮腺分泌成分が主体 血液成分は殆どなくなる |
出典元「医学書院 ウェルネスからみた母性看護過程」
観察にあたって
まず母体を仰臥位にし、膀胱を空にした状態で恥骨結合を基準に子宮底を触診し、高さや位置、硬さを評価します。硬さは収縮の良否を反映し、軟らかい場合には弛緩性出血の可能性があるため注意が必要です。また、圧痛の有無は感染や血腫の兆候を示すことがあります。
悪露の観察
パッドを確認して色・量・臭いを観察します。赤色から褐色、漿液性、白色へと変化していくのが正常な経過であり、量の急な増加や悪臭を伴う場合は異常のサインです。
全身状態の観察
全身状態の観察は欠かせません。バイタルサインに加えて、顔色や皮膚の状態、発汗の有無を確認することで、出血や貧血、感染の早期発見につながります。母体の表情や疲労感も回復状況を把握する手がかりとなります。
排尿や排便の状況
排尿や排便の状況も子宮復古に影響します。膀胱の充満は子宮底を押し上げて収縮を妨げるため、排尿困難がないか観察することが重要です。便秘も腹圧の影響で不快感を増し、母体の安静を妨げる要因になります。
このように、子宮底や悪露の数値的な変化だけでなく、全身状態や生活行動の観察を組み合わせることで、母体の回復過程をより正確に把握することができます。
子宮復古不全とは
子宮収縮が不十分で、 子宮底の下降が遅れたり、悪露が長期間にわたり多量・鮮紅色で持続する状態を指します。原因には、弛緩出血、胎盤・卵膜遺残、感染、母体の全身状態不良(貧血、疲労)などがあります。
これらの異常の早期発見のためには、「子宮底の高さ・硬さ」「悪露の量・色・臭気」を毎日観察し、異常の有無を記録・報告することが大切です。
進行性変化(乳房)の観察項目
観察する目的
乳房の観察は、産褥期の進行性変化を把握するうえで欠かせません。授乳が始まる時期には乳房が急激に変化するため、母体の負担やトラブルのリスクが高まります。そこで、観察の目的を明確にし、母親の身体的・心理的サポートにつなげることが大切です。
- 授乳がスムーズに開始できるよう母乳分泌の準備状況を確認する
- 乳汁分泌不全や乳腺炎などのリスクを早期に発見する
- 乳房の変化を通じて、母親の育児への適応を支援する
観察項目と観察方法
乳房の変化は、母乳分泌が順調に進んでいるか、また授乳に伴うトラブル(うっ滞、乳腺炎、乳頭損傷など)のリスクがないかを確認する上で重要な指標です。
とくに分娩直後から産褥1週間にかけては、乳房の張りや乳汁分泌が急激に変化するため、経過日数ごとの標準的な観察ポイントを押さえておくことが大切です。以下の表に、一般的な変化の目安をまとめます。
乳汁量と性状の経日的変化
| 産褥日数 | 乳汁量(1日総量) | 呼称 | 色 | 乳房緊満 | 性状 |
|---|---|---|---|---|---|
| 産褥0〜1日 | 5〜20ml | 初乳 | 透明水様 | (−) | 蜜のようにやや粘稠 |
| 産褥2日目 | 50〜70ml | 初乳 | 帯黄色 | (±) | 粘稠性強 |
| 産褥3日目 | 140〜250ml | 初乳 | 帯黄色 | (+) | 粘稠性強 |
| 産褥4日目 | 230〜310ml | 初乳 | クリーム色 | (+) | 粘稠性やや弱 |
| 産褥5日目 | 270〜400ml | 移行乳 | クリーム色 | (±) | 粘稠性やや弱 |
| 産褥6日目 | 290〜450ml | 移行乳 | 薄クリーム色 | (±) | 不透明 |
| 産褥7日目 | 320ml〜 | 移行乳 | 乳白色 | (−) | 不透明 |
| 産褥8〜14日目 | 500ml〜 | 移行乳 | 乳白色 | さらさらしている | |
| 産褥15〜28日目 | 700ml〜 | 成乳 | 帯青白色 | さらさらしている | |
| 産褥29日目〜 | 900ml〜 | 成乳 | 帯青白色 | さらさらしている |
出典元「医学書院 ウェルネスからみた母性看護過程」
基準+個別性を押さえた退行性変化・進行性変化の報告
母性看護学実習での報告では、教科書的な基準をただ伝えるだけでは「その褥婦さんが今どうなのか」が分かりにくくなります。そのため基準+個別の経過を意識することが重要です。
基準と照らし合わせる
教科書には「産褥2日目には子宮底は臍下1横指に下降する」といった基準値が示されています。報告の際には、まずこの基準を頭に置いたうえで、自分が実際に観察した褥婦さんの状態を重ねて伝えることが大切です。
【例】「産褥2日目で子宮底は臍下1横指にあり、基準通りの退行がみられます。」
例えば、「基準通りに下降しているか」「想定より遅れているか」「早めに退行しているか」といった比較を行うことで、その人の回復が順調かどうかが判断できます。
ただ単に「子宮底は臍下1横指です」と報告するだけでは、基準と比べてどうなのかが分からず、指導者やチームに伝わりにくくなります。「教科書的な基準」+「自分が観察した事実」を組み合わせて報告することが重要です。
個別性を入れて具体的に表現する
行動や発言を含めて報告することで、単なる身体所見だけでなく「その人がどのように過ごしているのか」「どんな思いや不安を抱いているのか」といった個別性を明確に示すことができます。
【例】「悪露は血性で中等量です。昨日は2時間ごとにパッド交換をしていましたが、今日は3時間ごとの交換で済んでいます。」
【例】「乳房は張りがあり、乳頭に軽度の発赤が見られます。授乳時に痛みを訴えており、『続けられるか不安』との発言も聞かれています。」
授乳時の痛みだけでなく、「痛みにより授乳をためらう姿が見られた」や『続けられるか不安』と話していた、といった観察や発言を加える ことで、患者の状態変化や心理面をより具体的に表現できます。
時系列で比較する
「時系列で比較する」というのは、単に“今どうか”を伝えるのではなく、昨日(または前回)と比べてどう変わったかを示すことです。変化を追って報告することで、回復が順調か、停滞しているのか、悪化しているのかが一目で分かります。
【例】「昨日よりも悪露の量が減っています。」
【例】「昨日は子宮底は臍高にありましたが、今日は臍下に下降しています。」
特に産褥期は日ごとの子宮底の位置や悪露の量・性状が変化していくため、昨日との違いを具体的に伝えることが大切です。例えば「昨日は臍高でしたが、今日は臍下に下降しています」と言えば、子宮の復古が正常に進んでいることが明確になりますし、逆に「昨日よりも悪露が増えている」と伝えれば異常の兆候を早く共有できます。
このように時系列で比較することで、母体の経過をチーム全体で的確に把握し、必要な援助につなげやすくなります。
観察目的とつなげて報告する
事実を並べるだけでは、聞き手に“その観察が何を意味しているのか”が伝わりません。報告では「悪露を観察するのは子宮復古や感染の有無を判断するため」「子宮底の高さを測るのは復古不全を早期に発見するため」といった目的と結びつけて説明することが大切です。
【例】悪露 → 子宮復古の状態や感染徴候を把握するため
【例】子宮底の高さ → 子宮復古不全を早期に発見するため
【例】乳房の張り・乳汁分泌 → 授乳が順調に進んでいるか確認するため
目的を意識して伝えることで、単なる状態の共有ではなく、“その所見から何を評価すべきか”をチーム全体で理解でき、次の看護行為につなげやすくなります。
正常分娩の褥婦の事例をもとに看護計画を作成してみよう
正常分娩の褥婦Aさんの場合
基本情報
Aさん、30歳、初産婦。経膣分娩にて出生児の体重は2,980g。分娩所要時間10時間、出血量は正常範囲
経過
現在産褥2日目。体温36.8℃、脈拍78回/分、血圧118/70mmHgで全身状態は安定している
子宮復古
子宮底は臍高で硬く触知。悪露は血性・中等量。強い臭気はなし
乳房の変化
やや張りを認め、乳頭から初乳が分泌されている。授乳時に「乳頭が痛い」と訴えており、乳頭に軽度の発赤あり
心理面
初めての育児に不安を抱いており、「母乳がきちんと出るのか心配」「授乳が痛くて続けられるか不安」と話している
生活背景
実母が産後1週間ほど同居してサポート予定。夫は仕事が忙しいが、夕方以降は面会に来て育児に協力的
看護診断の具体例
♯1 授乳を通して母乳育児の知識と技術を身に付けはじめている
♯2 子宮復古を順調に進めるための生活が整っている
♯3 母親としての役割を受け入れ始めている
看護計画の具体例(進行性変化)
看護診断
♯1 授乳を通して母乳育児の知識と技術を身につけ始めている
看護目標
- 新生児に乳頭を適切に含ませることができ、浅吸いが改善する
- 正しい抱き方・授乳姿勢を理解し、安楽で安定した授乳ができる
- 母乳育児に関する疑問や不安を言語化できる
- 授乳に自信を持ち、前向きな言葉(満足感・安心感)を表出できる
1. 観察計画(OP)
- バイタルサイン:体温、脈拍、血圧
- 乳房の状態:張り(乳房緊満)、乳頭・乳輪の発赤、亀裂、疼痛の有無
- 授乳後の乳房の硬さや乳汁分泌量
- 新生児の授乳姿勢・乳頭の含み方・吸啜の強さ
- 授乳時間、授乳間隔
- 母親の表情、声かけ、感情表出
- 母乳育児に関する疑問や不安の言語化の有無
- 全身状態(倦怠感、睡眠状態、子宮復古、悪露の状態)
2. 援助計画(TP)
- 授乳時に母親と一緒に抱き方・乳頭の含ませ方を実践
- 浅吸いの改善のため、乳房マッサージや乳頭刺激を支援
- 乳頭痛軽減のため、授乳クッションやラノリン軟膏の使用を促す
- 授乳タイミングに合わせて訪室し、授乳をサポート
- 母親の不安や痛みに対して傾聴し、共感的に対応
- 家族(夫・実母)へのサポート方法を調整し、協力体制を整える
- 授乳環境を整備(静かで落ち着ける環境、適温、照明など)
3. 教育計画(EP)
- 正しい授乳姿勢、抱き方、乳頭の含ませ方の指導
- 授乳間隔やタイミング、乳汁分泌を促す行動(乳房マッサージ、水分補給、安静)の説明
- 授乳中の痛みの対処法の指導
- 母乳育児に関する疑問や不安への説明・指導
- 家族(父親・実母)への育児参加方法、母乳育児支援の方法を教育
看護計画の具体例(退行性変化)
看護診断
♯2 子宮復古を順調に進めるための生活が整っている
看護目標
- 子宮底の位置が順調に下降し、硬さを保っている
- 悪露が正常範囲で、悪臭や量の異常がない
- 休息・睡眠・栄養など生活リズムが整い、産褥体調が安定している
- 家族の協力を得ながら無理のない生活行動が継続できる
1. 観察計画(OP)
- バイタルサイン:体温、脈拍、血圧
- 子宮底の位置・硬さ(臍高、収縮状態、硬さ)
- 悪露の量・色・性状・臭気
- 下腹部の疼痛の有無
- 全身の倦怠感、疲労感
- 睡眠・休息状態
- 食事摂取量・水分摂取量
- 排尿・排便の状態
- 家族による支援の状況
2. 援助計画(TP)
- 母乳育児をサポートし、子宮収縮を助ける
- 過度な負担にならない範囲での日常活動を促す
- 適度な安静と休息が取れるよう環境を整備
- 栄養バランスのとれた食事・水分補給を支援
- 排泄介助や排便コントロールのサポート
- 家族に対して、母体の安静や回復を促す協力方法を助言
- 痛みや不快感に対して傾聴し、共感的に対応
3. 教育計画(EP)
- 子宮復古の経過や正常な悪露の説明
- 安静の取り方や無理のない日常動作(起き上がり方、歩行)の指導
- 栄養や水分摂取、睡眠の重要性の説明
- 適切な排便・排尿の方法や注意点の指導
- 家族への協力の必要性や支援方法の教育
終わりに
産褥期の母体は「退行性変化」と「進行性変化」が同時に進行しており、子宮復古や乳房の観察を通して回復の経過を把握することが重要です。観察結果を基準と比較しつつ、個別の状態や変化も含めて報告・記録することで、褥婦さんに安全で適切なケアを提供することができます。日々の観察・援助・教育を丁寧に行い、母体と新生児の健やかな回復を支えていきましょう。