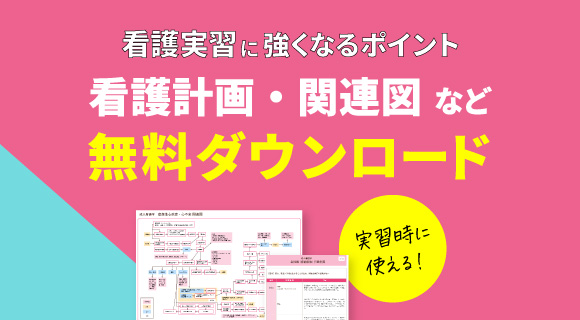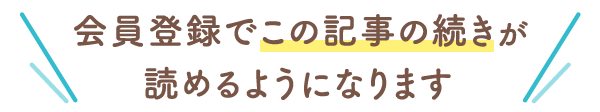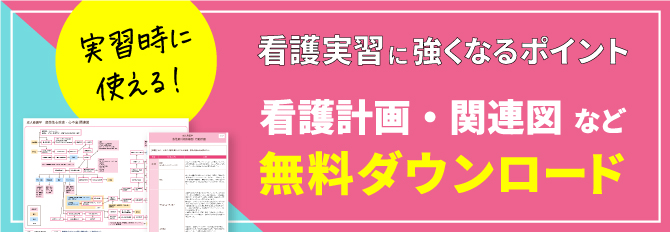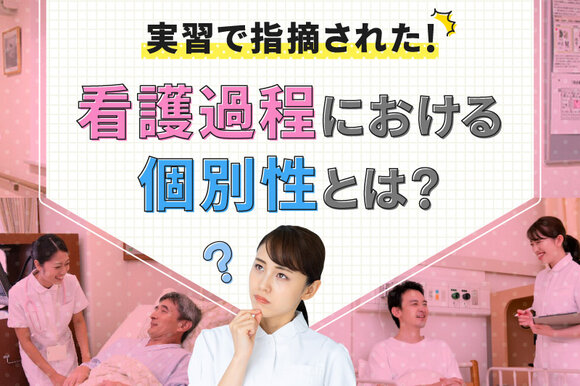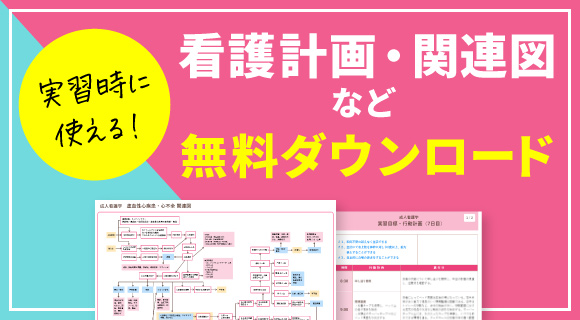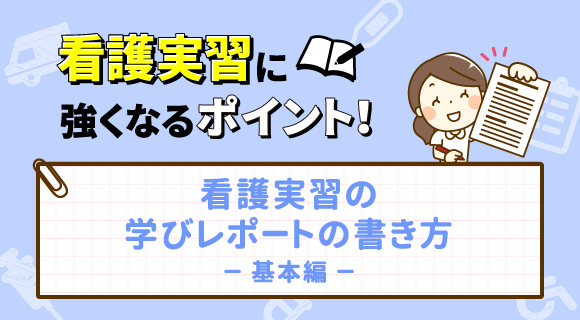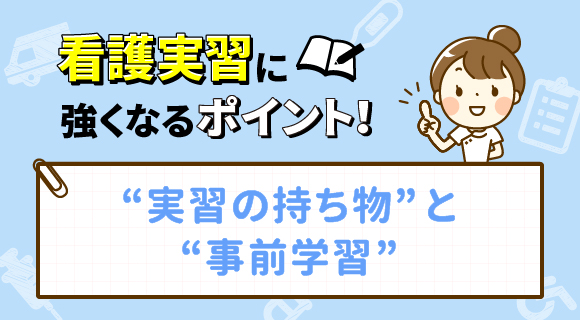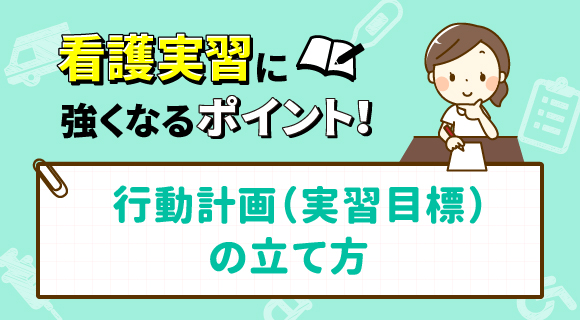事例あり!小児看護過程の書き方【アセスメント編】~家族看護と成長発達段階の理解~
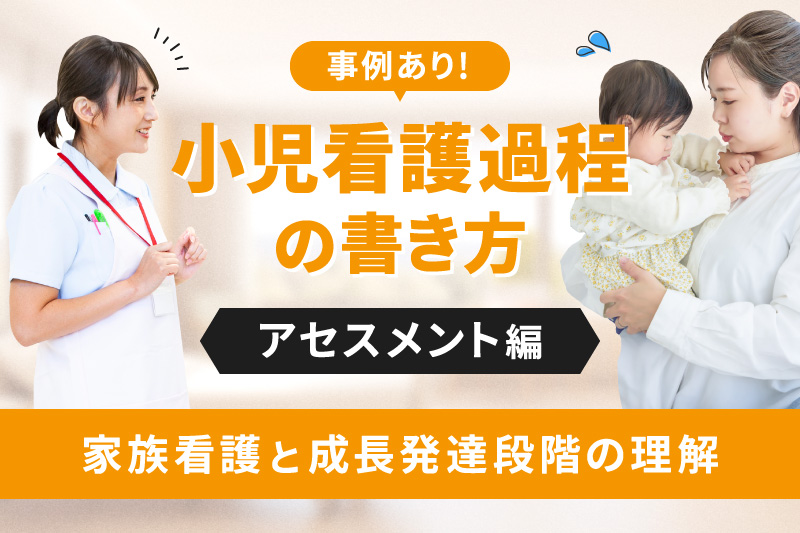
小児看護では、子どもとその家族全体をとらえたケアを実践することが重要となります。
子どもとその家族を包括的に支援するためには、子どもの成長発達段階を理解し、総合的な視点からアセスメントすることが求められます。
今回は、急性胃腸炎で入院となった1歳女児の看護過程を、ゴードンの機能的健康パターンを用いて展開していきます。小児看護における家族を含めた看護と成長発達段階の理解を深め、ケアを実践できるようにしましょう。
小児看護過程の特徴とは?
子どもの看護を実践するうえで最も重要なことは、子どもはどのような病気を持っていても日々成長し続けている存在であるという視点を持ち、成長発達段階における身体的・精神的・社会的な側面を総合的に評価することです。
小児看護過程においてゴードンの機能的健康パターンは、健康に関わる11の領域に基づいて子どもの健康を多面的に評価することができるため、看護過程が展開しやすく有効です。
子どもの健康や生活は、家族の考えや価値観に大きな影響を受けます。とくに乳幼児期では、影響がより顕著です。
機能的健康パターンに影響を与える因子として、成長発達段階はもちろん、環境因子の一つとして家族の影響についてもしっかりと意識し看護展開していく必要があります。
小児看護過程の情報収集のポイント
成長発達段階を踏まえた情報収集とは?
小児看護をするうえで、子どもが現在どのような成長発達段階にあるかを知ることは、子どもの身体的・心理的・社会的な成長に応じた異なるニーズや課題に対するケアを提供するためにとても重要です。
子どもの心理社会面の発達を理解するためには、「エリクソンの自我発達理論」や「ビアジェの認知発達理論」、「ボルビィのアタッチメント理論」などが参考になります。
これらの理論をもとに、小児看護過程の情報収集する際に重要な視点となる小児の各時期の特徴を身体的・心理社会的・認知思考的に分けて以下にまとめます。
乳児期(生後1ヶ月〜1年未満)
乳児期は新生児期を経て身体的にも心理社会的にも発達が著しい時期です。この時期は生活の全てを親や養育者に依存しなければ生きていけません。同時にその人々から受ける影響がその後の発達に大きく関係します。
身体的特徴
- 体重は出生後1年間で約3倍、身長は約1.5倍に増加。
- 粗大運動では4ヶ月で首がすわり、7ヶ月でお座り、生後1年で一人歩きができるようになる。
- 微細運動では8ヶ月頃には母指、示指、中指で物をつかみ、1歳頃には母指と示指の指先で物をつかむことができるようになる。
- 栄養面では乳汁栄養から離乳食へ移行する過程で、この時期の適切な栄養摂取がその後の成長や発達に大きく影響を与える。
- 生理機能面は、免疫機能が未熟であり抵抗力が弱いため、病気に罹りやすく、重症化しやすい時期。
心理社会的特徴
乳児期は、母親との間に基本的信頼関係を築く重要な時期である。子どもは母親の養育によって身体的安全と情緒的安定を得る。
認知・思考的特徴
乳幼児期は身近な環境に関わり、吸う・掴むなど身体活動と感覚的知覚により対象を認知していく。徐々に、目的を果たすために意図的に対象に働きかけるようになる。
幼児期(1歳から6歳)
身体の構造や機能が成人に近い状態まで成長・発達し、言語や思考も活発になる時期です。同時に一人の人間として生きていく基盤を形成する時期であり、基本的生活習慣や社会性を得る重要な時期でもあります。
身体的特徴
- 乳児期に比べて身体発育の速度は緩やか。
- 一方、姿勢の保持や粗大運動は著しく発達し、手足の細かい運動へと発達が進む。
心理社会的特徴
- 行動範囲が急激に広がり、同時に言語の発達も著しく、自分でさまざまなことをやろうとする。自分でできることを体感すると自律性を獲得していく。
- 幼児期後期では運動機能や言語機能がさらに発達し、基本的生活習慣がほぼ自立する。
- できること、やりたいことが増え、家庭の外にも興味をもつ。
認知・思考的特徴
- 幼児期前期は、自己中心的思考が強い時期であり、誰でも自分と同じように考えているととらえる。
- ごっこ遊びが盛んで、象徴機能が発達する。
- 幼児期後期になると、徐々に自己中心的思考を克服していくが、子ども自身が経験している範囲の認知にとどまる。
- 言語は非常に発達するが、言葉の意味を十分に理解せず使用する場合も多い。
学童期(6歳から12歳)
学童期は、小学校入学から第二次性徴が出現する前までをさします。心身ともに比較的安定した時期であり、疾病罹患率や死亡率も低いです。基本的生活習慣を確立、維持していく時期でもあります。
身体的特徴
- 学童期は、身長と体重の増加が一定となり、全体的に均整のとれた体型へと移行する。
- 走行力、跳躍力、球技力などの運動能力が発達し、さまざまな運動に積極的な興味を示す。
心理社会的特徵
- 親からの自立を始める時期。
- 就学とともに生活の中心は家庭から学校や友人へと移行し、仲間集団との関係を良好に保つことが重要課題となる。
- 自己中心性が徐々に減少し、他者から期待される役割を理解しそれに応えようと努力する。
- 一方で、同年代の仲間との比較、競合から劣等感を味わう。
認知、思考的発達
- 知的側面が目覚ましく発達し、物事を全体的にとらえ理解できるようになる。
- 他者との相互作用を通して自分と異なる考えがあることを理解する。
- 言語の発達は著しいが、十分に自分の考えや思いを表現することは難しい。
思春期(12歳から18歳)
思春期は、自己のアイデンティティを獲得することが発達課題とされ、「自分とは何か」「自分は何になりたいのか」など過去からの自分を認め、現在の自己を知り、さらに未来の自分を求めて試行錯誤する時期です。
身体的特徴
- 身体発育に伴い、運動能力や体力も急速に増加し、多くの体力要素が20歳までにピークを迎える。
- 第二次性徴は、生殖器官がホルモンの急激な分泌により成熟することに伴って起こる現象で、男子は精巣容積の増大、女子では乳房の発育によって発来する。
心理社会的特徴
- さまざまな体験を通して自己を見つめ、社会に存在する意味や将来を考え、自己の価値観を築いていく時期。
- 親子関係や仲間関係を通して「自分とは何か」について深く考え、混乱しやすい時期でもある。
- 「仲間と同じ」「仲間と一緒」など帰属意識が強く、仲間と異なることに疎外感をもつ。
- 思春期から青年期にかけて徐々にアイデンティティを確立していく。
認知・思考的特徴
- 物事をより論理的にとらえ、抽象的思考が可能になる。
- 仮説をもとに推測ができるようになり、将来を見通した考えも可能となる。
こうしたそれぞれの成長発達段階に関連する基礎知識をしっかりと理解し、小児看護課程を展開する必要があります。
家族看護を意識した情報収集
親子は、愛着という強い絆で結ばれており、唯一無二の特別関係といえます。
小児看護が子どもを対象としながらも、常に家族を含めて視野に入れる理由は、親子関係が健全であるということが子どもの成長発達過程においても、子どもが健康な生活を送るうえでも、とても重要であるからです。
とくに乳幼児期の子どもは、食事・排泄・休息・睡眠などのすべてを他者に依存しなくては生きていけません。
成長とともに基本的生活習慣を獲得し、自立へ向かう過程のなかでも、家族のあり方や関わり方が、子どもの発達や健康に直接的な影響を及ぼします。乳幼児期の子どもは、自身の病状を言葉で伝えることは困難です。そのため、小児看護では家族の存在の意味は大きく、子ども本人から得られる情報のみでなく、家族からの情報も大変重要なものとなります。
小児看護学実習でよく受け持つ事例
<事例>A子ちゃんの一般情報
| 基本情報 |
|---|
| A子ちゃん 1歳4ヶ月 女児 |
| 現病歴 |
| 入院2日前、保育園から帰宅後より機嫌が悪くなりぐずる時間が長くなった。 昨日より38.0℃の発熱あり。食欲なくほぼ摂取していない。水分はコップ1杯(200ml)程度飲み。本日朝にお茶を飲んだ後すぐに嘔吐。黄色水様便が続けて3回あり受診、急性胃腸炎の診断となる。 |
| 既往歴 |
| なし |
| 家族関係 |
| 母親27歳パート、父親28歳会社員と3人暮らし 父親の両親は他県で遠方だが、母親の両親が近所に住んでいる。 |
| 社会状況 |
| 母親が平日9時から15時までパート勤務をしており、その間保育園に通っている。ワクチン接種はB型肝炎、ロタウイルス、ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合一期の3回目まで、BCG、麻疹・風疹、水痘の1回目まで接種済みである。 |
| 心理状態 |
| 母親は「まさか入院になるなんて・・どうしよう。」と初めてのA子ちゃんの入院に動揺や不安を感じている様子あり。また、「いつもよりすごく機嫌も悪いし、ぐったりしているし心配です。大丈夫なのでしょうか。もっと早く病院に連れてきてあげれば良かった。」とぐったりしているA子ちゃんを見て自責の念を感じている。 |
S情報・O情報から導き出せるアセスメント例と押さえておきたいポイント
ゴードンの機能的健康パターンを用いてアセスメントを展開します。
健康知覚-健康管理パターン
乳幼児の場合は、健康管理の多くを養育者に依存している段階です。子どもの健康に対する養育者の認識や管理方法を明らかにしましょう。
子ども自身の健康への関心や行動に関しては、各年齢での基本的生活習慣の獲得段階とあわせて判断する必要があります。幼児期以降では、手洗いや歯磨き習慣の様子、それらに対する行動や反応、親の対応について確認してください。病気や入院の理解、入院による反応、服薬行動や反応も含まれます。
アセスメント例
| S情報・O情報 | アセスメント |
|---|---|
| 正常分娩で問題はなかった。 |
| S情報・O情報 | アセスメント |
|---|---|
| Aちゃんは1歳4ヶ月で、第一子 | |
| 1歳2ヶ月頃から一人歩きができるようになった。 | 1歳4ヶ月頃は、運動機能として一人歩きができるようになり、小さい物をつかめるようになる時期である。一人歩きができるようになっており、現時点で運動機能に関する問題はないと考えられる。 |
| アレルギーなし | |
| 入院2日前から機嫌が悪く、ぐずる時間が長くなった。 | |
| 入院前日から38.0℃の発熱、入院当日には嘔吐、下痢が続きぐったりしてきたため病院を受診、急性胃腸炎と診断され入院。 | |
| 母は「もっと早く病院に連れてきてあげれば良かった。」と話す。 | 母親はAちゃんの状態に合わせて受診行動をとれていたが、入院となり、自身の受診行動の遅さや自責の念を感じていると考えられる。 |
| 入院後より末梢静脈内持続点滴が開始。医師より、経口摂取は水分のみ少量ずつ可だが嘔吐や下痢が悪化するようであれば絶飲食の指示が出ている。 | |
| 点滴は左手背から刺入されシーネと包帯にて固定されている。 | |
| 既往歴や入院歴はなく、今回がはじめての入院。 | |
| 母親「いつもよりすごく機嫌も悪いし、ぐったりしているし心配です。大丈夫なのでしょうか。はじめての入院でどうしたらいいのか…」「まさか入院になるなんて…どうしよう。」 | 第一子ではじめての育児であり、今回、突然具合が悪くなったことや入院になったことで、母親の動揺が大きくなっていると考えられる。 |
| S情報・O情報 | アセスメント |
|---|---|
| 平日は母親、休日は父親とお風呂に毎日入っている。 | 乳幼児期は、子ども自身による健康管理に関するセルフケアは難しいが、家族による健康管理が行われており、現段階の健康管理は適切であると判断できる。 |
| 予防接種はB型肝炎、ロタウイルス、ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合1期の3回目まで、BCG、麻疹・風疹、水痘の1回目を接種済み。 | |
| 歯みがきは母親が食後に行い、嫌がらずに行えている。 | |
| Aちゃんの手洗い、うがいに関する情報はない。 | 平日9時から15時まで保育園に通っており集団行動によって感染を受けやすい状況である。 |
| 痛みや嫌なことに対しては「イヤー」と表現する。 | |
| 両親の感染予防行動についての情報はない。 | 保育園や両親の感染予防行動に関する情報はないが、急性胃腸炎と診断されたことから、保育園または両親から何らかの感染があったと考えられる。 |
栄養-代謝パターン
水分出納バランスは、栄養摂取状態によって崩れることがあるため、排泄パターンと合わせてアセスメントすることが必要です。
乳幼児期では、食物の形態が乳汁から固形物に移行していくため、発達段階に応じた適切な食物形態で、栄養が適切に確保されているのかを確認します。発達段階に合った嚥下機能や咀嚼機能であるかも重要な情報です。
栄養状態の判断には検査データや発育の経過、指数などによる発育評価が重要な指標となります。養育者の嗜好や食習慣が、子どもの食習慣にも大きな影響を与えることため確認が必要です。
アセスメント例
| S情報・O情報 | アセスメント |
|---|---|
| 平日は保育園で昼食を摂取している。 | 経口摂取前後での幅気、幅吐、下痢などの症状の有無を観察することが必要。 |
| 保育園では幼児食を摂取している。 | |
| 自宅では食事は大人と同じ内容で、一口大にカットしている。 | |
| 手づかみ食べがほとんどだか、スプーンやフォークを使って食べようとする様子もある。 | |
| 1日3食摂取している。 | |
| 入院後、経口摂取は水分のみである。 |
| S情報・O情報 | アセスメント |
|---|---|
| 普段は好き嫌いなく、食欲があり、よく食べている。 | 食欲旺盛で、偏食もなく食事がとれている。 |
| S情報・O情報 | アセスメント |
|---|---|
| 入院2週間前:身長 76cm、体重10kg | 体重が2週間前と比較して 7%減少し、口唇乾燥、ツルゴール低下.末梢冷感、啼泣時の涙が少ないことから、中等度の脱水があると考えられる。 |
| 入院時:身長 76cm、体重 9.3kg | |
| 入院時:体温 38.5°C、脈拍150回/分、呼吸40回/分、血圧は啼泣のため測定不可、脈拍の不整はなし | |
| 乳歯は、臼歯と犬歯以外生えてきた。 | 歯の萌出に問題はない。 |
| 入院時、口唇は乾燥しており、ツルゴールは低下し、末楷に冷感があった、採血などの処置のときに泣いていたが、涙は少なかった。 | |
| 活気がなく、ぐったりと母親に抱かれていた。 | |
|
【血液データ】 RBC450x104/μL Hb13g/dL Ht43% WBC13.000/μL TP7.5g/dL Alb4.7g/dL BUN21mg/dL Na135mEq/L K4.0mEq/L Cl102 mEq/L |
Hb. TP は問題ないが、Ht, BUNの上昇が脱水を示している。 |
| S情報・O情報 | アセスメント |
|---|---|
| 入院2週間前:身長 76cm、体重10kg | 入院前のカウプ指数は 17.3で正常である。 |
| 身長が75パーセントタイル値。体重は75パーセンタイル値以上90バーセンタイル値未満である。 |
排泄パターン
乳幼児では、体内水分バランスが多いことや腎機能の未熟性などにより、脱水を生じる危険性が高くなるため、水分出納バランスに十分注意しなくてはいけません。
栄養-代謝パターンの情報ともあわせてアセスメントしましょう。
アセスメント例
| S情報・O情報 | アセスメント |
|---|---|
| 入院前:排尿 5~7回/日、排便1~2回/日 | 幼児期には、排尿7~12回/日、排便1~2回/日が見られる。 |
| 排尿や排便後に「しっこ」と教えることがたまにある。 | 排尿、排泄があったことを周囲に伝えられるようになっており、発達段階相応の排泄状況であると考えられる。 |
| 終日紙おむつを着用 | |
| 入院前日から陰部、肛門周囲が発赤しており、おむつ交換のときに陰部、肛門周囲を拭くと「イヤー」と嫌がる。母親は「赤みが強くなっています」と話す。 | 陰部、肛門周囲の発赤は入院前日から見られている。下痢が続くと発赤がさらに悪化する可能性が高い。 |
| S情報・O情報 | アセスメント |
|---|---|
| 入院前は、麦茶や水を1日 500~700mL摂取。 | 幼児の必要水分量は 100mL/Kg/日である。Aちゃんの場合は入院前の体重が10kgであり1,000mL/日が必要。 |
| 入院前は1日3回の食事を摂っていることから、水分と食事に含まれる水分量を考慮すると、生理的必要水分量は摂取できていたと考えられる。 | |
| 入院前日から 38.0℃の発熱があり、食欲もなく、食事はほぼ摂取できておらず、水分もコップ1杯(200mL)程度のみ。 | |
| 入院前日の夕方から少量の水機便が5~6回見られた。 | |
| 入院当日の朝、おむつに少量の排尿があった。 | |
| 入院当日の朝、水分を欲しがったため麦茶を飲ませたが、すぐに嘔吐と、黄色の水様便が3回続けてあった。その後嘔吐は見られていない。 | 入院前日から水様便が続き、経口での水分摂取が困難であることから生理的必要水分量を摂取できない可能性が考えられる。そのため、嘔吐や下痢などの消化器症状の有無と程度とともに、水分摂取状況、持続点滴での水分量も含め、水分出納バランスを注意して観察していく必要がある。 |
| 入院時、腹部膨満はなく、腸婦動音が亢進していた。 | |
| このまま症状が続き、経口摂取困難の状況が続くと、水分・電解質を喪失し、脱水が進む可能性が考えられる。 | |
| 腸液分泌の促進や栄養・水分の吸収障害から下痢となり、水分・電解質を喪失し、脱水に至っている。 | |
| 胃腸炎症状の有無と程度、経口摂取状況、体重の推移、検査データの推移について引き続き情報収集することが必要である。 |
活動-運動パターン
発達状況を知るうえで、遊びや1日の活動の様子なども重要な情報となります。このパターンには、活動を維持するための呼吸、循環機能を示すデータも重要な指標です。
アセスメント例
| S情報・O情報 | アセスメント |
|---|---|
| 一人歩きができるようになり、よくおしゃべりをしている。 | 今回の点滴は左手に固定されているが、食事や遊びなどの活動へ影響することが考えられるため、観察が必要である。 |
| 右手でスプーンを持ったり、TVのリモコンを持ったりする。 | |
| 点滴は左手背に固定されている。 |
| S情報・O情報 | アセスメント |
|---|---|
| 家の中では活発に動き回っていることが多い。 | 持続点滴をしているため。普段と同じような感覚運動遊びができない可能性があり、発熱や脱水の状態に合わせて援助を考えていく必要がある。 |
| S情報・O情報 | アセスメント |
|---|---|
| 平日は9時から15時まで保育園に通園している。保育園では、近所を散歩したり公園に行ったりして機嫌よく過ごしている。 | 入院前は保育園や家庭で活発に遊んでいたが、入院によりベッド上での生活となることで、これまでと同じように遊べなくなる可能性がある。 |
| 今回、感染予防対策にて個室に入院となった。 | 入院後の経過のなかでのAちゃんの遊びの様子について情報収集していく必要がある。 |
| S情報・O情報 | アセスメント |
|---|---|
| 現在は母親が着替えをさせている。 | 1歳頃から着ているものに興味をもちはじめ、1歳半頃から一人で脱ごうとする時期である。現時点で母親が着替えをさせていることにとくに問題はない。 |
| S情報・O情報 | アセスメント |
|---|---|
| 入院時:体温 38.5℃、脈拍150回/分、呼吸40回/分、血圧は啼泣のため測定不可。脈拍の不整はなし。 | 脈拍と呼吸数の増加は、発熱や脱水による影響であると考えられる。 |
睡眠-休息パターン
乳幼児は、月齢や年齢にふさわしい睡眠時間や睡眠パターンに加え、睡眠・休息がとれる環境であるかどうかも重要な情報です。
子どもの睡眠・休息は、養育者の生活習慣からも影響を受けるため、養育者の生活習慣や睡眠習慣も重要な情報となります。
アセスメント例
| S情報・O情報 | アセスメント |
|---|---|
| 6時半に起床し朝食 | 1歳頃の睡眠時間は、昼寝と合わせて約12時間となる。入院前の睡眠時間は11~13時間であるから、十分な睡眠をとれていた。 |
| 9時登園 | |
| 11時半頃昼食 | |
| 12時半頃から2時間程度の昼寝 | |
| 17時半~18時半頃に入浴と夕食 | |
| 20時半には就寝 | |
| 昼寝と合わせて、睡眠時間は12時間程度 | |
| クマのぬいぐるみがお気に入りで、寝るときは必ずそのぬいぐるみを抱きかかえて寝ている。 | 寝るときは必ずぬいぐるみを抱きかかえて寝ており、Aちゃんにとってこのぬいぐるみはとても大切なものである。とくに入院中は、このぬいぐるみは睡眠に欠かせないものであると考えられる。安心して睡眠をとるためにも、両親に持参してもらうよう伝える必要がある。 |
| クマのぬいぐるみがないと、ぐずったり、途中覚醒したりする。 |
認知-知覚パターン
乳幼児の場合は、認知や知覚に関する反応、コミュニケーションの手段やその特性をふまえた判断が必要です。
人見知りの出現は、他者と自己を区別することや、他者のなかでも重要他者を特別な人として認知できるようになったことを表す情報となります。発達段階を考慮して確認しましょう。
アセスメント例
| S情報・O情報 | アセスメント |
|---|---|
| 嫌なこと、痛いことに対しては、泣いて「イヤー」と表現することが多い。 | 「イヤー」と、言葉で嫌なことや痛いことを表現していることから、このような言葉が聞かれたときに、嫌なことがあるのか、身体的に痛みを感じているのかを全身状態と合わせて観察していく必要がある。 |
| TVに食べ物が出てくると「マンマ」と言うことがある。 |
| S情報・O情報 | アセスメント |
|---|---|
| 「パパ」「ママ」など、話す言葉が多くなってきている。 | 1歳~1歳半は一語文を中心とする時期であり、Aちゃんは年齢相応の発達である。 |
| S情報・O情報 | アセスメント |
|---|---|
| 両親や母親の両親(母方祖父母)にはなついているが、母親の友人など普段あまり会わない人には、人見知りをして泣いてしまう、慣れるのにも時間がかかる。 | 7ヶ月頃から人見知りをするようになる。Aちゃんにとってはじめての入院であり、見知らぬ人に囲まれた環境に不安を感じると考えられる。 |
自己知覚-自己概念パターン
乳幼児期の養育者との愛着や基本的信頼関係がどのように構築されているかが子どもの自己概念の発達に大きな影響を与えます。そのため、親の養育度や子どもへのかかわり方もあわせて確認することが重要です。
アセスメント例
| S情報・O情報 | アセスメント |
|---|---|
| 食事を自分で食べたがる、スプーンを持って口まで持っていくが、上手に食べられないことも多く、母親が手伝おうとすると嫌がる。 | 1歳頃から自我が芽生え、自己主張するようになる時期である。 |
| S情報・O情報 | アセスメント |
|---|---|
| 情報なし |
役割-関係パターン
子どもの急な入院は、家族へ大きな悪響を与えます。とくに母親は、自らの養育行動に対する自責の念、育児への自信喪失などを生じやすくなります。
「健康知覚-健康管理パターン」「役割-関係パターン」から、家族の不安などを確認してください。
アセスメント例
| S情報・O情報 | アセスメント |
|---|---|
| 家族構成は、28歳の父親、27歳の母親との三人暮らし。 | 家族三人暮らしの核家族。 |
| 母親は平日パート勤務をしている。 | |
| 父親の両親は遠方だが、母親の両親は近所に住んでいる。 | 父親の両親は遠方だが、母親の両親は近所に住んでおり、時折Aちゃんを預けるなど普段からの交流もある。 |
| S情報・O情報 | アセスメント |
|---|---|
| Aちゃんは母親の両親にはなついており、時々預けているが、機嫌よく過ごしている。 | 母親の両親から入院中の協力を得られやすいと考えられる。 また、父親は仕事で不在にすることもあるが、子育てには積極的に参加しており仕事の状況によっては、母親との付き添い交代も可能だと考えられる。 |
| 父親は育児を積極的に手伝ってくれているが、仕事が多忙で出張で長期間不在になることもある。 | |
| 母親が付き添いで入院することになった。 | |
| 母親「まさか入院になるなんて・・どうしよう。」 | 入院という環境の変化がはじめての体験であり、母子ともに不安に感じている。 |
| 母親「Aは、自宅と私の両親の家以外で寝るのがはじめてです。Aもいつもより機嫌が悪いし、何だかぐったりしているし、大丈夫なのでしょうか。もっと早く病院に連れてきてあげれば良かった。」と落ち着かない様子で話す。 |
セクシュアリティー生殖パターン
乳幼児期では第一次性徴や成長に伴う性別の意識や性への関心に関することを確認します。
アセスメント例
| S情報・O情報 | アセスメント |
|---|---|
| 情報なし | 幼児期では、2歳頃から外見の違いにより性別に気づき、区別するようになる、Aちゃんは1歳3ヶカ月であり。 現時点ではこのバターンに関する問題は考えられない。 |
コーピングーストレス耐性パターン
1~3歳児は、分離不安が強い時期であることを理解したうえでの対応が必要です。
一方で付き添いの家族にとっては疲労につながる場合もあるため、状況を確認しましょう。
アセスメント例
| S情報・O情報 | アセスメント |
|---|---|
| 普段は機嫌よく過ごしていることが多い。 | 生後6ヶ月~2、3歳頃までは、愛着をもつ人に対して、愛着行動を示す時期である。 |
| 母親が付き添いで入院することになった。 | 母親が入院準備をする短時間であても、Aちゃんは母親から離れることに強い不安反応を示しているが年齢から考えれば不安反応は通常の反応といえる。 |
| はじめての入院である | |
| 入院準備のために母が一度帰宅する際、Aちゃんを看護師に預けようとするも、Aちゃんは母親から離れようとしなかった。 | |
| 看護師がAちゃんを抱きかかえると激しく泣きはじめ、母親が部屋を後にしてからもしばらく泣いていた。 | Aちゃんの心身の安定をはかるための工夫と、子どもの反応による母親自身の不安の解消や疲労への対応が重要である。 |
| 母親と一緒にいたときも、看護師が抱きかかえたときも、「あっち!あっち!」と泣きながら病室の出入口を指さしていた。 | 病室にいたくないということを表現しており、入院という環境の変化に気づいていると考えられる。 |
| Aちゃんの機嫌がいつもより悪く、母親からなかなか離れられず、母親は「普段から人見知りだけど、こんなに離れられないことってなくて・・・どうしたらいいんだろう・・・」と戸惑っている様子が見られた。 | 環境の変化によるAちゃんのストレスが考えられる。 |
| 嫌なこと、痛いことには、泣いて「イヤー」と表現することが多い。 |
価値ー信念パターン
乳幼児期は養育者の影響を受けやすく、養育者の言動や考えが子どもの将来の価値、信念、道徳観などに影響を与えます。
そのため、養育者の子育てやしつけに関する考え、価値を明らかにします。
アセスメント例
| S情報・O情報 | アセスメント |
|---|---|
| 情報なし | 家族の子育てに関する価値観などが子どもへの対応にも影響するため、家族がどのような価値観をもってAちゃんに接しているかなどは今後情報収集する必要がある。 |
| S情報・O情報 | アセスメント |
|---|---|
| 情報なし |
成長発達段階を考慮し、家族を含めた看護を実践しよう
小児看護は元気になっていく子供たちの経過を間近で見守ることができ、大きなやりがいを感じられます。そして、家族にとっても大きな支えとなる存在になれるはずです。
実習でも、成長発達段階に応じたニーズや課題を意識し、家族を含めた看護過程を実践していきましょう。