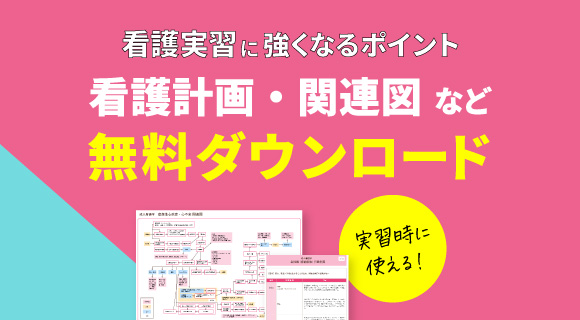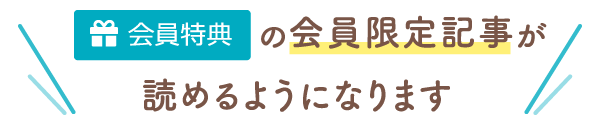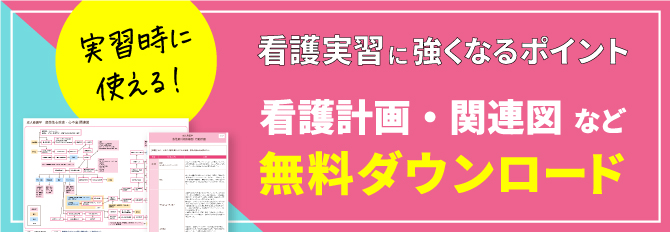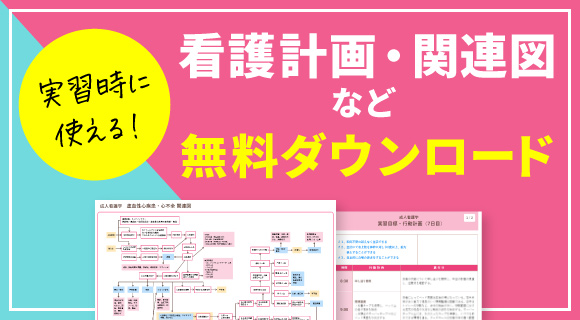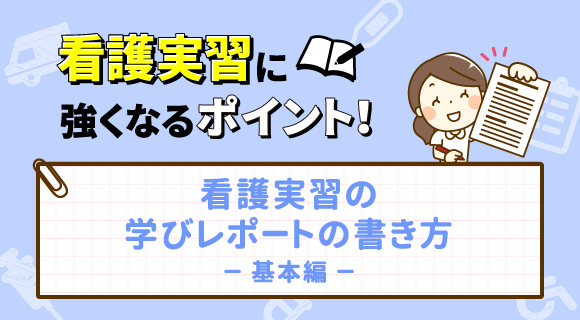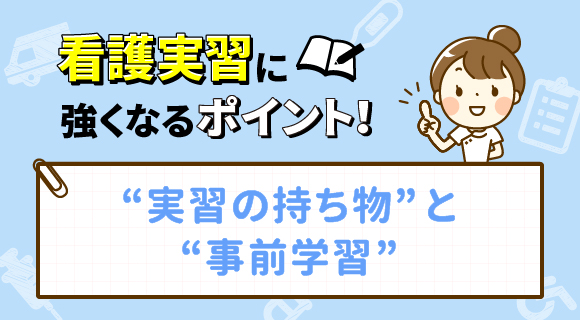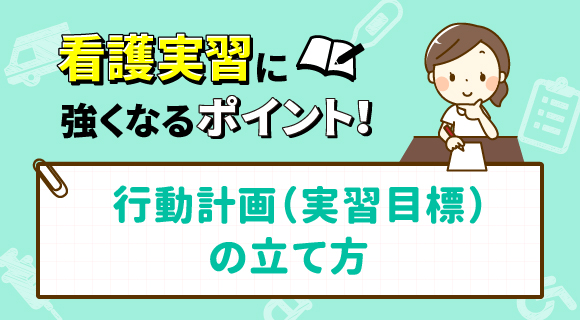看護実習で使える!精神疾患を持つ方とのコミュニケーションのコツ【精神看護学実習】

精神看護学実習に臨む看護学生の皆さんにとって、精神疾患を持つ患者さまとのコミュニケーションは大きな課題の一つです。
本記事では、実習で直面しがちなコミュニケーションの難しさを乗り越えるためのポイントや具体的な対処方法を紹介します。患者さまとの信頼関係を築くためのスキルを身につけ、安心して実習に取り組めるよう、ぜひ参考にしてください。
精神看護学実習で配慮するべきコミュニケーションのポイント
精神疾患を持つ患者さまと接する際には、相手の状態や気持ちを尊重しながら、適切な距離感と態度で関わることが重要です。
以下のポイントを意識することで、患者さまと良好な関係を築きやすくなります。
傾聴する
患者さまの話に耳を傾け、否定せずに受け止める姿勢が大切です。
たとえ幻覚や妄想の内容であっても、「それは違いますよ」と否定するのではなく、病状や感情に理解を示し、「そう感じたのですね」と共感的に返答することで安心感を与えられます。アイコンタクトやうなずき、穏やかな表情といった非言語的コミュニケーションも効果的です。
患者さまとの適度な距離感
患者さまの気持ちに寄り添いながらも、自立を支援する姿勢が求められます。
過度に距離が近すぎると、プレッシャーを感じたり不安を強めてしまったりする可能性があります。物理的な距離だけでなく心理的な距離も意識し、過度な干渉や依存を避ける適度な距離感を保ちましょう。
患者さまのプライバシーを尊重し、無理に話を引き出そうとしないこともポイントです。
患者さまが安心して話せる環境を作りましょう。
代表的な精神疾患の理解
代表的な精神疾患についての理解を深めることで、患者さまの行動や反応に対して適切に対応できます。
| 代表的な 精神疾患 |
特徴 |
|---|---|
| 統合失調症 |
|
| てんかん |
|
| 依存症 |
|
| 不安障害 |
|
それぞれの疾患には個別性があり、同じ診断でも症状の現れ方や性格、背景は患者さまごとに異なります。
相手の特性を理解し、柔軟に対応する姿勢が重要です。
精神疾患を持つ患者さまとのコミュニケーションに困ったときの対処方法
幻聴や幻覚、妄想などの症状を訴える場合
統合失調症の患者さまは、幻聴や被害妄想を訴えることが多く、特に病状が悪化している時や過度なストレスがかかった時に症状が強く出る場合があります。
具体的には、「誰かに監視されている」「声が聞こえる」「自分の悪口を言われている」といった幻覚や妄想を話すことがあります。
声かけの例とポイント
【例】
「それは怖かったですね。今は私がここにいるので大丈夫ですよ。」
「そんなことはありませんよ」など訴えを否定することは不信感につながります。
落ち着いた態度で不安に寄り添う言葉をかけ、安心できる雰囲気を作ります。
ただし、幻覚や妄想に同調しすぎると、「やはり現実だ」と確信を強め、症状が悪化する可能性があり、注意が必要です。
妄想や幻覚の内容ではなく、それらによって引き起こされている感情を全面的に受け止めるようにしましょう。
同じ精神疾患でも人によって症状が様々な場合
同じ診断名がついていても、それぞれの患者さまによって症状の出方や強さが異なることはよくあります。
これは、病気の進行度や個人のもともとの性格、生活環境やストレスの有無、服薬状況などが異なるためです。
双極性障害の場合は、同じ診断でも躁状態と抑うつ状態による症状の違いが見られるため、症状に合わせた対応が必要になります。
声かけの例とポイント
【例】
「今は少し座って、飲み物でも飲みながらゆっくりお話ししませんか」
躁状態の患者さまは、気分が高揚し、活動的で自信過剰になりやすい一方で、衝動的な行動や攻撃的な態度が見られることがあります。
躁状態の患者さまに対して落ち着きを促す場合は、「落ち着いてください」と直接言うのではなく、自然な形でペースを落とす声かけが効果的です。
患者さまの気持ちを否定せず受け止め、衝動的な行動をその場で止められる工夫をします。
躁状態のときは刺激に敏感になっているため、低めの声でゆっくりと話すよう心がけましょう。
【例】
「そんなふうに思ってしまうほどつらいのですね。そう感じていることを聴かせもらえて良かったです。」
「無理なくできそうなことはありますか」
うつ状態の患者さまは、気分の落ち込みや意欲の低下、自責感が強いため、「そんなことないですよ」などの安易な励ましは逆効果になってしまう場合があります。
気持ちに寄り添いながら、焦らせず、安心できる環境を提供することが必要です。
また、「ちゃんと〇〇しないとダメですよ」など指導的に言うのではなく、患者の全身状態を確認しつつ、小さな行動から始められるように提案します。
日々の表情や行動、言動の変化に気を配り、個々の状態に応じた対応を心がけましょう。
マニュアル通りの対応ではなく、その人に合った関わり方を探していく姿勢が大切です。
患者さまの反応が見られない、予測できない場合
精神疾患を持つ患者さまは、その日の体調や症状の変動が大きいため、看護者が話しかけても反応が見られなかったり、予想不能な反応が返ってきたりすることもあります。
声かけの例とポイント
【例】
「お話ししたくないときもありますよね。無理に話さなくても大丈夫です。」
「今日は静かに過ごしたい日かもしれませんね。話がしたくなったら、いつでも聞きますね」
「びっくりしましたね、でも大丈夫ですよ。」
「少し時間をおきましょうね」
無理に会話を続けようとせず、患者さまのペースに合わせることが重要です。
静かな時間を共有することも、大切なコミュニケーションの一環です。
突然怒り出したり、大声を出したりと攻撃的になる場合は、刺激を与えないよう落ち着いたトーンで話し、反論はせず患者さまの気持ちを受け止めます。
その場合、必要であれば距離を取り、 安全確保を優先しましょう。
実習で押さえておくべきコミュニケーション技法
精神看護実習では、看護師の患者さまとの関わり方そのものが治療の一環となるため、以下の技法を意識して実践することが求められます。
| コミュニケーション 技法 |
実践方法 |
|---|---|
| ミラーリング | 相手の姿勢や話し方をさりげなく真似ることで、親近感を与える。 |
| ペーシング | 話す速度や声のトーン、考え方を相手に合わせ、共感している印象を相手に自然に与える。 |
| バックトラッキング | 相手の話を要約し聞き返すことで、会話内容の確認や相手に共感していることを伝える効果がある。 |
| オープンクエスチョン | イエス・ノーで答えられない質問を投げかけ、相手の気持ちを引き出す。 |
| What(なに)・ Why(なぜ)の質問 |
相手の価値観を理解し、深く関わるためには「What/Why」での質問が有効。相手に関心を持っていることを示すとともに、相手の発言を掘り下げてより深く相手を知ることができる。オープンクエスチョンでは答えにくい場合にも有効な場合がある。 |
精神科では、こうしたコミュニケーション技法が患者さまの安心感や自己理解を促進し、治療の一環として重要な役割を果たします。看護師の関わりが患者さまの回復に直結することを意識しながら実習に取り組んでみてください。
患者さまの心と向き合う看護実習
精神看護学実習は、初めは戸惑うこともあるかもしれませんが、患者さま一人ひとりと真摯に向き合うことでコミュニケーションの大切さが実感できると思います。患者さまの心に寄り添うことで、治療につながる大きな力となります。