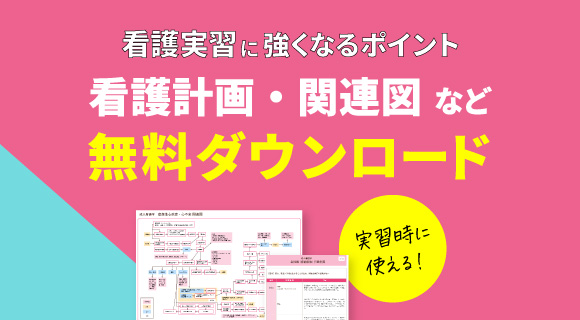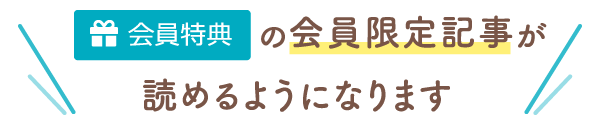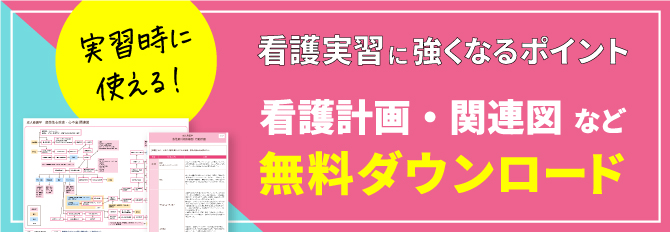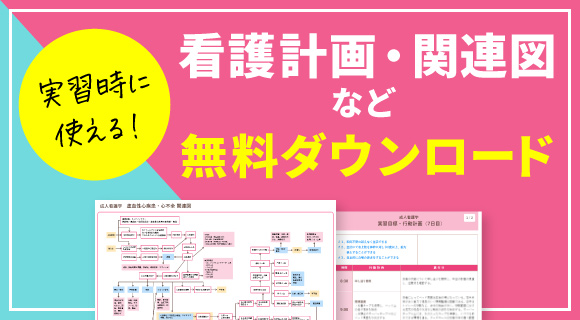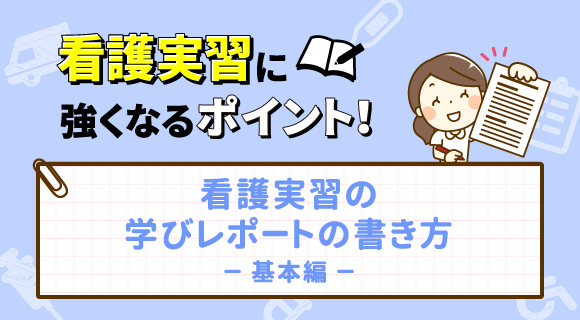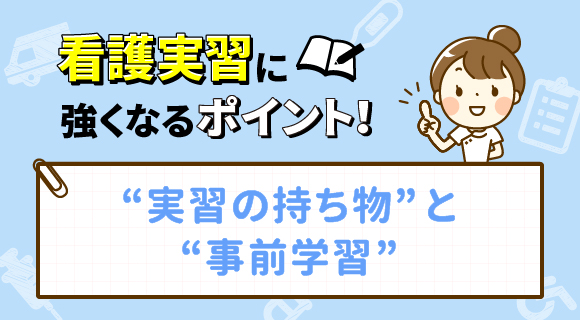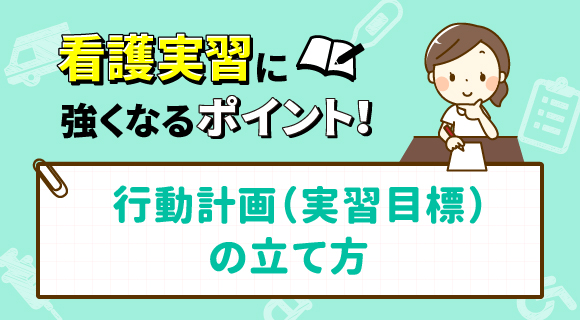看護実習で使える!患児とのコミュニケーションのコツ【小児看護学実習】

小児看護学実習では、患児やその家族と良好な関係を築くことが、看護ケアの質を高めるための重要なステップとなります。
子どもの発達段階や個性に応じた関わりによって、患児やその家族が安心してケアを受けられる環境が整います。本記事では、小児看護学実習を控える看護学生に向けて、患児やその家族と円滑にコミュニケーションをとるための具体的なコツを解説しています。
子どもとのコミュニケーションの目的とは?
小児看護において子どもとのコミュニケーションは、単に言葉を交わす情報伝達だけでなく、子どもの心と身体の状態を理解するための重要な手段です。子どもとのコミュニケーションの目的は、以下の通りです。
不安や恐怖心の軽減
病院という環境は、子どもにとって慣れない場所であり、不安や恐怖を感じることが少なくありません。優しい言葉や態度で接することで、緊張感を和らげます。
信頼関係の構築
子どもが安心して自分の気持ちや症状を伝えられるようになることで、看護師は適切なケアを提供できます。
治療やケアへの協力の促進
コミュニケーションを通じて子どもが看護師に対して「信頼しても大丈夫」と感じてもらえば、治療やケアに積極的に協力してくれる可能性が高まります。
発達を促す関わり
年齢や成長に応じた言葉や行動を用いることで、子ども自身が「理解できた」「頑張れた」という成功体験を得られるよう支援します。
患児とのコミュニケーションのポイント
円滑なコミュニケーションは、子どもとの信頼関係を構築する基盤となります。コミュニケーションが円滑に行われることで子どもは安心感を抱き、看護師を信頼しやすくなります。信頼関係が構築されると、治療やケアを実施する際に子どもがより積極的に協力できる環境を作り出すことが可能です。
子どもと接する際は、言語的コミュニケーションと非言語的コミュニケーションをバランスよく活用することが重要です。
以下のポイントは、年齢や状況にかかわらず、コミュニケーションにおいて役立つ基本的な姿勢です。子どもと接する際にも意識をしましょう。
笑顔で接する
子どもは、大人の表情を敏感に察知します。
温かい笑顔は非言語的コミュニケーションの一つであり、親しみやすさを感じさせ、不安を和らげる効果があります。特に初対面の際には、緊張を解くきっかけとなるため、心がけましょう。
子どもの目線に合わせる
高い位置から見下ろされると、子どもは威圧感を感じます。
しゃがんだり椅子に座ったりして子どもの目線に合わせることで安心感を与え、対等な立場でのコミュニケーションが取りやすくなります。
優しい声のトーンを心がける
言葉の内容だけでなく、声のトーンも子どもへ与える影響が大きいです。
声のトーンは言語的コミュニケーションの一部であり、柔らかな声で話しかけることで、子どもに安心感を与えられます。
遊びを取り入れる
言葉での説明が難しい場合には、遊びや道具を活用しましょう。おもちゃや絵本、歌などを使って関心を引き、楽しみながらコミュニケーションを進めることで、自然に心を開いてもらえます。
子どものペースに合わせて時間をかけて関わる
急かすことなく、子どものペースに合わせてコミュニケーションを行うことも大切です。
無理に子どもから言葉を引き出そうとせず、時間をかけて信頼関係を構築しましょう。
子どもの発達段階に合わせたコミュニケーション方法
子どもは、発達段階によって言語の理解力や感情の表現力、社会性が大きく異なります。
発達に応じた言葉や方法で接しなければ、子どもに正しく意図が伝わらないだけでなく、不安や緊張感を増幅させかねません。そのため、発達段階に合わせたコミュニケーションを実践することが必要です。
各発達段階の子どもの特徴
| 乳児期 (0〜1歳) |
言葉を理解することは難しい時期ですが、笑顔や声のトーンなどの非言語的コミュニケーションに反応します。 抱っこやタッチングを通じて安心感を与えます。 |
|---|---|
| 幼児期 (1〜6歳) |
自己主張が強くなり、言葉や身体を使ったコミュニケーションが活発となります。 想像力が豊かで好奇心が旺盛ですが、感情のコントロールはまだ困難で不安や恐怖を感じやすい時期です。 簡単な説明は理解しやすい反面、抽象的な概念や複雑な説明は混乱を招く恐れがあります。 |
| 学童期 (6〜12歳) |
理解力が発達し、具体的な説明を好みます。 学校生活や友人関係を通じて社会性が向上し自分の意見や感情を表現できるようになります。 一方で失敗や批判に敏感であり、自信を失いやすい面もあります。 仲間意識が強まり、個性が際立つ時期でもあります。 |
| 思春期 (12〜18歳) |
自立心や自己意識が急速に発達します。 自分の価値観やアイデンティティーを模索し、他者からの評価や承認に敏感になります。 プライバシーや自分の意見を尊重されることを強く求める一方で、不安や悩みを抱えることも増えます。 大人との信頼関係を築くには対等な立場で接し、対話の中での共感や理解が重要です。 |
乳児期のコミュニケーション
診察室で医療器具を見て泣きそうな場面
【例】
「このガラガラ、音がするね!触ってみようね。」
乳児は視覚や聴覚への刺激に興味を示すので、不安をそらす手段として効果的です。
診察や処置前の待機時間
【例】
「大丈夫だよ〜」と優しく背中をなでながら穏やかに声かけをする
表情や声のトーンなどの非言語的コミュニケーションを工夫しながら抱っこやタッチング、撫でるなどのスキンシップをとることで安心感を得られ、処置前の緊張感を和らげます。
幼児期のコミュニケーション
注射や採血などの痛みを伴う処置の前
【例】
「ちょっとチクっとするけどすぐ終わるからね。一緒にがんばろうね!」
子どもに何が起きるかを事前に伝えることで不安を軽減します。 難しい言葉を避け、短く簡単な言葉で説明することが大切です。
処置が終わった後
【例】
「すごく頑張ったね、とってもえらかったよ。頑張ったからシールあげるね。」
頑張ったことを褒めることで、子どもに自信を与えられ、次の処置への不安の軽減につながります。ちょっとしたご褒美を用意しておくと、子どもは前向きな気持ちになりやすいです。
学童期のコミュニケーション
処置や検査の内容を伝えるとき
【例】
「今からやることを順番に説明するね。質問があれば教えてね。」
具体的で分かりやすい説明を心がけることで、理解力を高めます。自分で選択や意見を述べられる場を提供することも大切です。
子どもが治療や検査について質問したとき
【例】
「どうして注射をしなくちゃいけないの?」と聞かれた場合、「体の中に必要な薬を届けるためだよ。薬を注射すると早く元気になれるから一緒に頑張ろうね」
子どもの疑問に真摯に向き合い、わかりやすく伝えることで信頼関係を築きます。
思春期のコミュニケーション
治療や検査に対する不安や恐怖を感じているとき
【例】
「何か心配なことや、相談したいことはあるかな?教えてくれると助かるよ。」
プライバシーを尊重しながら、相手の意見に耳を傾けます。命令口調を避け、対等な立場で接することで信頼関係を築きます。
治療方法や薬剤に対しての説明
【例】
「この薬がどんな役割を持っているのか、納得できるように説明するね。」
不安や疑問を持っている思春期の子どもには、詳細でわかりやすい正確な情報を提供し、安心感を与えることが重要です。
子どもの家族とのコミュニケーション
患児のケアにおいて、子どもの最も身近な存在である家族との関わりは必要不可欠です。
家族は子どもの健康や日常生活における重要な情報源であり、ケアの質を高めるうえで協力が求められます。
子どもは特に病気や入院という非日常的な環境において家族に大きく依存します。家族の存在が子どもに安心感を与え、不安や恐怖を軽減する役割を果たします。
看護師が家族と良好なコミュニケーションを築くことで家族自身がリラックスし、その安心感が子どもに伝わり、より穏やかに治療を受けることができます。
家族との関わり方のポイント
不安や心配事を聞く
家族が感じている不安や悩みに耳を傾け、共感を示し安心感を与えることで家族との信頼関係を深めます。
丁寧な説明
子どもの治療内容やケアについて、できる限り医療用語を避け、具体的で簡潔な言葉を使用し、わかりやすく伝えます。
家族の役割を尊重
看護師がすべてを引き受けるのではなく、家族の力を引き出し、協力しながら一緒にケアに参加できるよう働きかけましょう。
子どもを一人の人として尊重する看護
小児看護学実習は、子どもやその家族と関わる中で、コミュニケーションの奥深さを学ぶ貴重な機会となります。
年齢や発達段階にかかわらず、目の前の子どもを一人の人として尊重し、その気持ちに寄り添う姿勢を大切にしましょう。