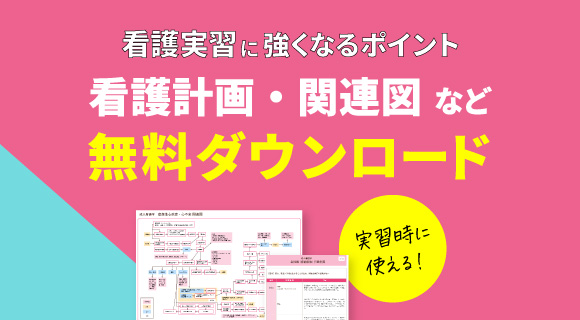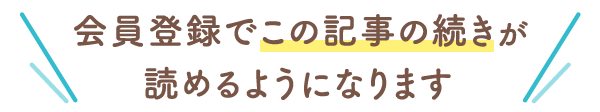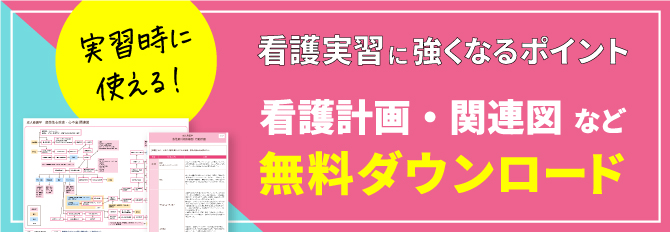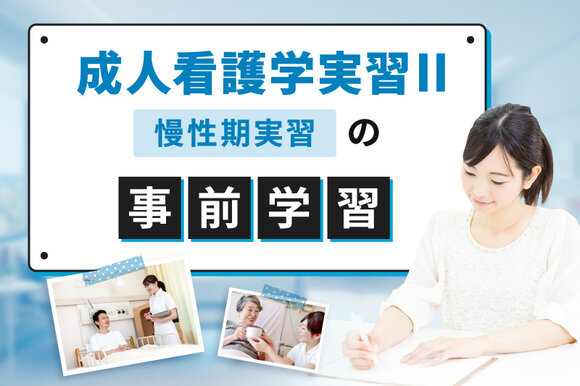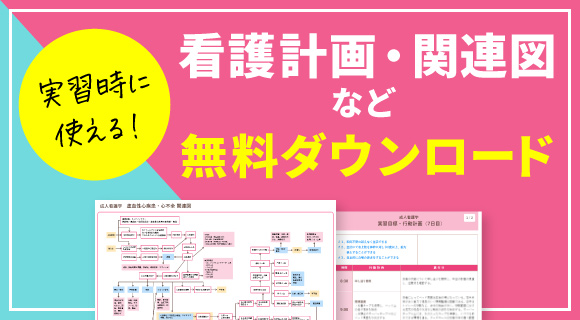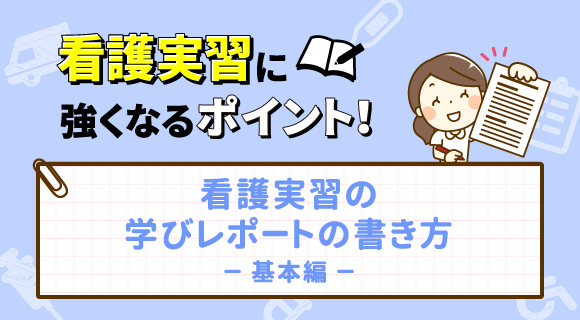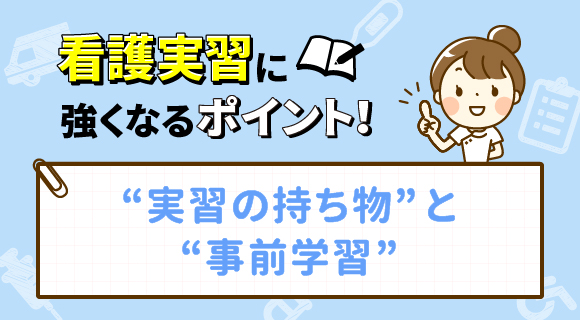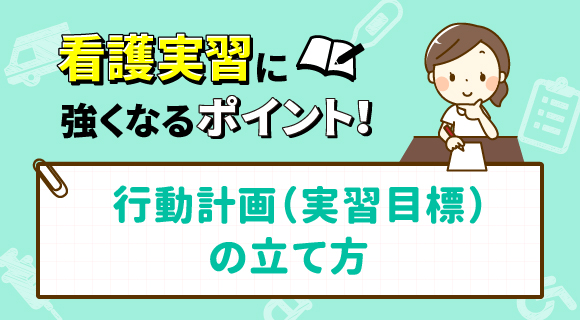事例あり!成人・慢性期看護過程の書き方【アセスメント編】~生き方や生活を捉える~
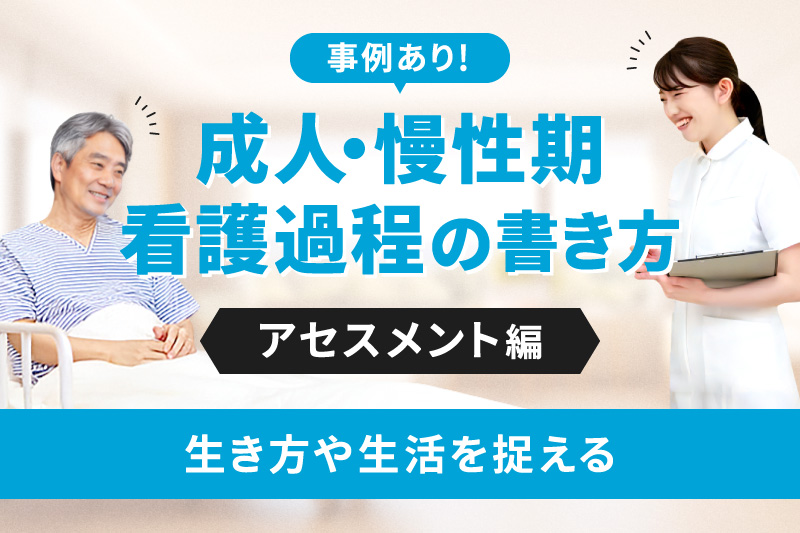
慢性期における看護過程のアセスメントは、急性期とは異なり、「その人らしさ」や「生活」に目を向けた個別性のある視点が求められます。
この記事では、成人看護学実習Ⅱにおいて、慢性期看護過程のアセスメントをどのように行えばいいのかを、事例を交えて分かりやすく解説しています。ぜひ、参考にしてください。
成人看護学実習Ⅱ(慢性期)の特徴とは?
成人看護学実習Ⅱでは、病状が安定しているものの、完全な回復が難しく、長期的な療養が必要な患者さまを受け持つことが多くあります。
対象となる患者さまの健康レベルはさまざまで、「治癒を目指す」よりも「日常の生活の質を保つ」ことを目的とすることが多くなります。
そのため、医療的ケアの必要性だけでなく、患者さま一人ひとりの生活背景や価値観を尊重し、個別性の高いケアを提供することが重要となります。
慢性期のアセスメントで押さえておくべきこと
慢性期のアセスメントでは、患者さまの身体的側面だけでなく、社会的・心理的側面も含めた多角的な視点からの評価が重要となります。慢性疾患を抱える患者さまは、長期にわたる治療や生活習慣の調整を強いられるため、病気そのものの状態だけでなく、日常生活の中での困りごとや不安、周囲との関係性、生活背景なども丁寧に把握する必要があるからです。
身体的・社会的・心理的側面を総合的にアセスメントすることで、患者さま一人ひとりに見合った、より個別性の高い支援・看護計画を立案することが可能になります。
以下に、それぞれの側面について、詳しく解説しています。
身体的側面
慢性期の患者さまは、疾患の種類や進行度、合併症の有無、そして日常生活動作(ADL)の能力など、身体的な状態が非常に多様であるため、それぞれの患者さまに適した視点から情報を収集し、アセスメントを行うことが求められます。
個々の患者さまの健康状態や生活背景を的確に把握することで、より的確で個別性のある看護計画へとつなげることができます。
糖尿病を患っている患者さまの場合
血糖コントロールの状況を把握することはもちろん、インスリンや内服薬の使用状況、低血糖や高血糖の既往、食事療法や運動療法の実施状況といった自己管理能力の評価も重要です。
さらに、糖尿病性網膜症や腎症、神経障害といった慢性的な合併症の有無についても把握し、病状の全体像を捉えることが求められます。加えて、自己管理が困難な場合には、家族や支援者の関与の有無、教育的支援の必要性なども評価する必要があります。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者さまの場合
日常的な呼吸状態や咳嗽・喀痰の有無、SpO₂(経皮的酸素飽和度)などの呼吸機能の評価に加えて、在宅酸素療法(HOT)の導入状況やその管理能力も確認する必要があります。
また、安静時や軽い動作時に呼吸困難感が生じていないか、日常生活における運動耐容能(どの程度の動作を継続できるか)を把握し、それに応じた生活指導やリハビリテーション支援の検討も行われます。
さらに、COPDの患者さまは病状の悪化(増悪)によって入退院を繰り返すケースも多いため、増悪の兆候をどのように察知・対応しているか、セルフモニタリングの状況も含めてアセスメントすることが重要です。
このように、慢性疾患を抱える患者さまの身体的側面を評価する際には、疾患ごとの特性に応じた視点を持ち、個別に必要な情報を丁寧に収集・分析していくことが不可欠です。
社会的側面
患者さまの家族構成や生活環境、経済的な状況、地域で利用できる社会資源の活用状況といった「社会的な背景」は、慢性期におけるアセスメントにおいて欠かすことのできない重要な要素です。
身体的・心理的側面と同様に、患者さまがどのような環境で日常生活を送っているのかを把握することは、実際の支援内容や退院後の生活を見据えた看護計画の立案に大きく関わってきます。
一人暮らしの高齢者の場合
日常生活において必要な買い物や食事の準備、掃除などの家事を自力で行えているかどうかを確認する必要があります。もしそれらが困難であれば、家族や近隣の支援が受けられるのか、または訪問介護や配食サービスといった地域資源の利用状況についても確認し、必要に応じて福祉制度の導入を検討します。
加えて、緊急時に誰に連絡をとるのか、連絡体制は整っているのかといった点も重要です。特に高齢者の場合、社会的孤立のリスクや、認知機能の低下によるセルフケア能力の低下が問題となることも多く、医療や介護だけでなく、行政や地域のネットワークを含めた支援体制の構築が必要です。
働き盛りの世代の患者さまの場合
治療と仕事の両立という視点からのアセスメントが求められます。通院や治療にどの程度の時間がかかるのか、それが勤務にどのような影響を与えているのかといった点などを確認します。
さらに、休職中であれば復職の可能性やタイミング、職場復帰支援の体制があるかどうかの確認なども含めた支援を検討する必要があります。仕事を持ちながら慢性疾患と向き合っている患者さまにとっては、身体的・精神的な負担が大きくなることもあるため、働くことが患者さまにとってのモチベーションである一方で、ストレスの原因になっている可能性もあるため、その点も丁寧に見極めていくことが重要です。
このように、患者さまの社会的背景を多角的に評価することで、治療だけでなく生活全体を支える包括的な支援へとつなげることができます。社会的要因の把握は、生活の質(QOL)の維持・向上を目指す慢性期看護において、極めて重要な視点です。
心理的側面
慢性疾患を抱える患者さまにとって、病気との長期的な付き合いは、身体的な負担だけでなく、心理的な側面にも大きな影響を及ぼします。慢性疾患は急性期のように短期間で完治するものではなく、継続的な治療や自己管理が必要となるため、患者さまは日々の生活の中でさまざまな不安やストレスを感じやすくなります。
特に、症状の進行や合併症の出現、生活の制限、治療の負担などが重なることで、精神的に落ち込みやすくなり、抑うつ状態や意欲の低下といった心理的問題を抱えることが少なくありません。
こうした背景から、患者さまの心理的状態を丁寧にアセスメントすることは、慢性期看護において非常に重要な役割を担います。
具体的には、患者さまが自身の病気をどのように受け止めているか(受容の程度)、将来に対してどのような展望や不安を持っているか、治療に対して前向きな気持ちで取り組めているかといった心理的な側面を注意深く観察し、対話の中からその兆候を見逃さないことが大切です。
病気の受け止め方には個人差があり、「一生この病気と付き合わなければならない」と感じて無力感に陥る方もいれば、「自分なりにできることをやっていこう」と前向きに捉えている方もいます。患者さまの心理的な反応に寄り添い、尊重しながら評価していく姿勢が求められます。
慢性疾患によって生活の質(QOL)が低下している場合は、そのことがさらに心理状態を悪化させる要因となることがあります。趣味や外出が制限されてしまったり、食事や活動内容に制約がかかったりすると、「自分らしい生活が送れなくなった」と感じ、喪失感を抱くこともあります。そのような思いを抱えている患者さまに対しては、看護師が共感的に関わることで、気持ちを整理する手助けができるだけでなく、前向きな行動変容へのきっかけをつくることも可能です。
このように、慢性期における心理的アセスメントは、単に感情の起伏を捉えるだけでなく、患者さまがその人らしい生活を取り戻すために何が必要かを見極めるための重要なプロセスです。心の動きに寄り添い、適切なサポートを提供することが、長期的な治療の継続とQOLの向上に直結することを理解しておく必要があります。
自己決定を支援する効果的なコミュニケーション
慢性期の患者さまにとって、自己決定を尊重したケアはQOLの向上に直結します。
しかし、患者さまと関わる中で「どんなふうに声をかけたらいいんだろう…」「うまく伝わっているか不安…」と、コミュニケーションに自信が持てない看護学生さんも多いのではないでしょうか。
以下に、学生の皆さんでも意識しやすく、実践しやすいコミュニケーションのポイントを紹介します。
傾聴
「ちゃんと聞いてくれている」と患者さまが感じることは、安心や信頼につながります。途中で患者さまの話を遮らず、うなずきや表情、相づちなどで「聞いていますよ」と伝えるだけでも、患者さまの心は少しずつ開いていきます。
情報提供
患者さまが理解しやすい言葉で、必要な情報を提供し、選択肢を提示します。専門用語を避け、やさしい言葉で説明することを意識してみましょう。「難しいことを分かりやすく伝える力」も、看護師としての大事なスキルです。
意思確認
患者さまの意向や希望を確認し、決定をサポートします。患者さまが本当に望んでいることは何か、そっと確認する姿勢を持つことが大切です。
たとえば、「どちらがいいですか?」「どう思われますか?」と優しく問いかけることで、患者さま自身の気持ちを大切にしていることが伝わります。
フィードバック
患者さまの決定に対して、肯定的なフィードバックを行い、自信を持ってもらいます。患者さまが決めたことに対して、「その選択、とてもいいと思いますよ」「しっかり考えられていてすごいですね」といった肯定的な言葉を伝えることは、患者さまの自信や安心感につながります。ときには、そうした一言が患者さまの心を軽くすることもあります。
これらのコミュニケーション技術を用いることで、患者さまが主体的に治療やケアに関われるよう支援します。こうしたコミュニケーション技術は、決して特別な才能がないとできないものではありません。少しずつ意識して繰り返すことで、誰でも自然に身につけていけるものです。
大切なのは、患者さまの気持ちに寄り添いたいという「まっすぐな思い」です。少しずつコミュニケーションの経験を積んできましょう。
成人看護学実習Ⅱ(慢性期実習)でよく受け持つ事例
2型糖尿病による血糖コントロール不良のため、教育入院した患者さまの事例を紹介します。
<事例>A氏の一般情報
| 基本情報 |
|---|
| A氏 67歳 男性 |
| 既往歴 |
|
| 心理状態 |
| 糖尿病の自己管理に疲れを感じており、「どうせ良くならない」と諦めの感情が見られる。インスリンの自己注射には抵抗感があり、拒否している。 |
| 家族関係 |
|
妻と二人暮らし。子どもは独立して別居。 関係は良好だが、妻も持病(高血圧・不整脈)があり、家事や通院の付き添いに負担を感じている。 |
| 社会状況 |
|
定年退職後は在宅中心の生活。 自宅のガーデニングを趣味としている。 介護保険申請済(要支援1)、地域包括支援センターとの関わりあり。 |
S情報・O情報から導き出せるアセスメント例
| S情報 | O情報 | アセスメント |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
押さえておきたいアセスメントのポイント
慢性期のアセスメントでは、身体的データだけではなく、生活背景や心理状態を含めて統合的に評価することが非常に重要です。今回の事例では、以下のポイントがアセスメントの核心となります。
1. 慢性疾患に対する受容度の把握と合併症のリスク
長年病気と向き合ってきたことで、患者さまは「頑張っても意味がない」と感じており、自己管理への意欲が低下しています。しかし、これ以上の病態の悪化は糖尿病性腎症や網膜症、神経障害などの合併症リスクを高めます。透析の導入や失明などは生活の質に大きな影響を及ぼします。これらの合併症は早期の発見と適切な管理によって予防や進行の遅延が可能です。
心理的な受容過程を把握しつつ、合併症のリスクとその予防について具体的に説明することで患者さまの自己管理の意欲を高める支援を行っていきます。
2. 生活環境と社会的支援体制の評価
A氏の在宅療養環境は一定の安定性を保っているものの、妻の体調や子どもとの距離など、支援体制には限界があると考えられます。A氏のような高齢世帯では、支援の空白に気づく視点が必要であり、地域包括支援センターや介護保険サービスなど、外部の支援資源の活用が重要です。
今後、A氏の継続的なケアを確保するためには、在宅での療養環境、家族の支援状況、地域とのつながりを総合的に評価し、必要に応じて外部の支援を導入することが重要です。
3. 精神心理面の変化への気づきと患者さまの価値観を尊重した支援
A氏は、糖尿病の長期的な治療に対して「どうせ良くならない」と感じ、自己管理への意欲が低下しています。しかし、「孫が生まれてね。可愛いよ。会って成長を見るのが楽しみなんだ」と話すなど、孫の存在が大きな喜びであり、生きがいとなっていることが伺えます。このようなポジティブな感情を活用し、治療や生活習慣の改善への意欲を引き出すことが重要です。
たとえば、「孫の成長を見守るために健康を維持する」という目標を共有し、具体的な行動計画を立てることで、自己管理へのモチベーションを高める支援が考えられます。また、A氏の趣味であるガーデニングも、生活の質を向上させる要素として活用できます。ガーデニングを継続するための体力維持や、日々の活動量の増加を目指すことで、自然と運動習慣の改善にもつながります。
このように、患者の価値観や生活背景を尊重し、ポジティブな要素を治療や生活習慣の改善に結びつける支援が、慢性疾患の自己管理において効果的であり重要です。
患者さまの生き方や生活を捉えてアセスメントしよう!
慢性期のアセスメントは、病気の進行状況だけでなく、患者さまの「生き方」や「生活」を捉える看護の醍醐味とも言えます。身体・社会・心理の側面を統合し、その人に寄り添ったアセスメントを行うことで、実習の中でも学びが深まるはずです。
患者さまの言葉に耳を傾け、変化に気づくことで、前向きな支援ができます。
成人・慢性期実習を通じて、看護の楽しさややりがいを感じてもらえることを願っています。