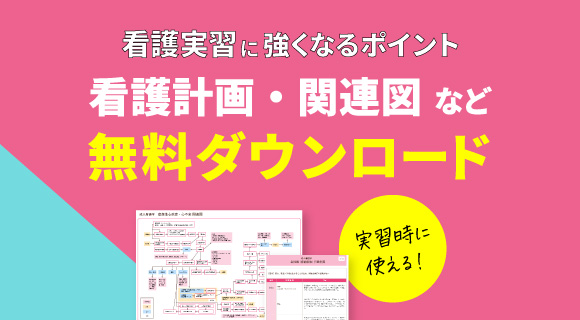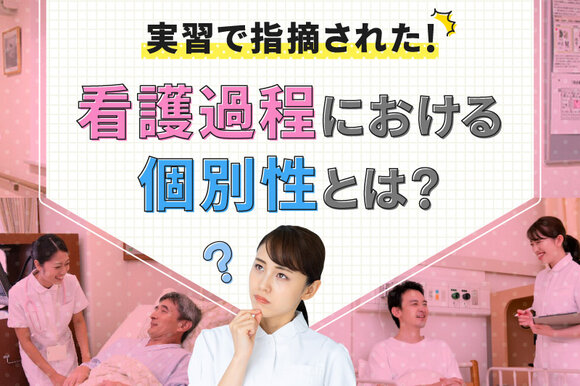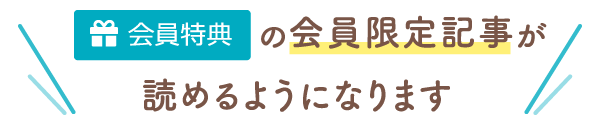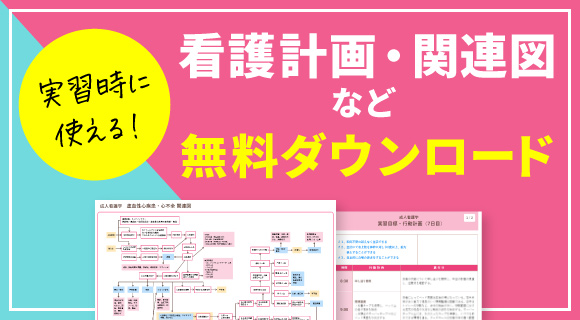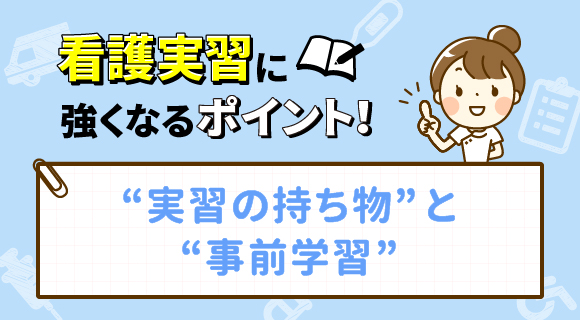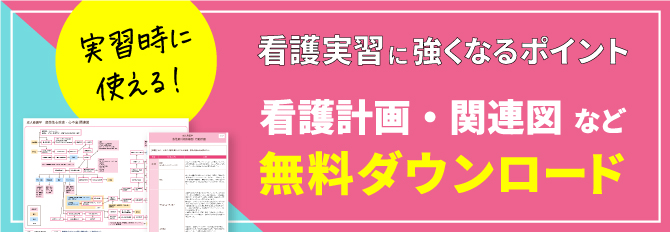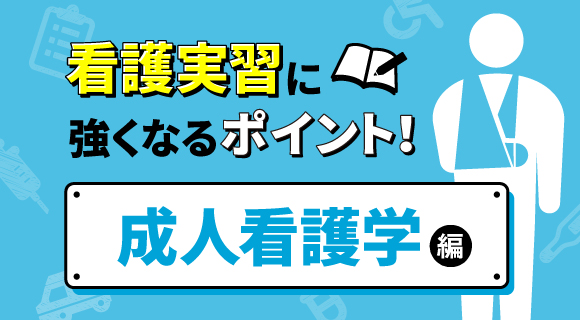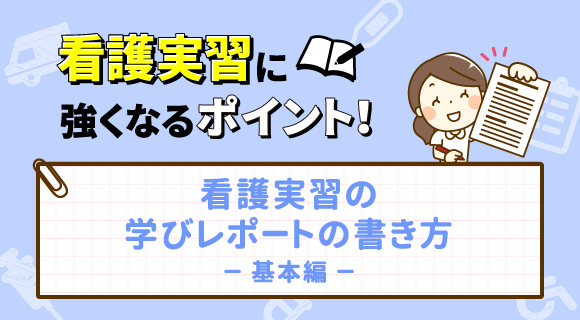成人看護学実習Ⅱ(慢性期実習)の事前学習

慢性期実習では、成人期におけるさまざまな健康レベルの人とその家族に対する看護過程の展開を行います。そのためには、対象理解のために事前学習をしておくことがとても大切です。ここでは、慢性期実習の特徴と事前学習のポイント、実際の実習場面で役立つ資料や持ち物について解説します。
成人看護学実習Ⅱ(慢性期実習)の特徴
慢性期実習は、さまざまな健康レベルにある対象者を身体的・社会的・精神心理的側面から統合的に理解し、それぞれに応じた療養生活の支援を行うことが特徴です。
健康の維持や社会生活の適応にむけて継続的な介入を行うためには、家族も含めたセルフケア能力を高める必要があるとともに、目の前の患者さまと看護者だけではなく、その後の生活において必要な体制や専門職者の連携にも目を向け、継続看護の観点からその人に合った支援を考えることが大切です。
また、慢性期実習の特徴の一つとして、看護の対象が若年層から老年層といった幅広い年代にわたることに加え、健康レベルに応じて介入の方法が大きく異なることがあげられます。
セルフケア能力の維持・向上にむけた積極的な支援が必要な場合もあれば、ターミナル期にある人のトータルペインの緩和が必要となる場合など、患者さまの疾患や療養生活もさまざまであるため、患者さまをとりまく環境を統合的に理解し、個別性に応じた看護介入を考えることが重要です。
慢性期実習前に勉強しておきたいポイント
慢性期疾患を有し、セルフケア能力が十分でない患者さまの看護においては、動作や食事、排泄の介助や清潔を保つための援助といった、日常生活動作の援助が必要とされます。
それぞれのセルフケア能力を理解し、必要とされる援助の実践につなげられるよう、看護技術を復習しておくことが大切です。
また、今後の療養生活にむけて、患者さま自身やご家族がセルフケア能力を獲得することが必要な場面も多くあります。
日常生活における指導を行うためには、看護者側が内容を十分に理解しておく必要があるため、知識を身に付け、指導の内容や方法を学習しておくことが大切です。
患者さまの特性や生活背景などに合わせて療養生活を共に考えるなど、個別性に応じた介入が求められる分野でもあるため、コミュニケーションをはじめとした関係性の構築も大切です。患者さまをとりまく環境や、家族も含めた介入方法を考えることがポイントとなります。
慢性期実習で役に立つ資料
病みの軌跡理論(モデル)
長い時間をかけて段階的に変化していくことの多い慢性期疾患を有する人の看護を行う上で、対象者がどのような段階にあるのかを理解し、方向づけるために理論を活用することが有効です。
| 局面 | 特徴 |
|---|---|
| 前軌跡期 | 病みの行路が始まる前、予防的段階、徴候や症状がみられない状況。 |
| 軌跡発現期 | 徴候や症状がみられる。診断の期間が含まれる。 |
| クライシス期 | 生命が脅かされる状況。 |
| 急性期 | 病気や合併症の活動期。その管理のために入院が必要となる状況。 |
| 安定期 | 病みの行路と症状が養生法によってコントロールされている状況。 |
| 不安定期 | 病みの行路と症状が養生法によってコントロールされていない状況。 |
| 下降期 | 身体的状態や心理的状態は進行性に悪化し、障害や症状の増大によって特徴づけられる状況。 |
| 臨死期 | 数週間、数日、数時間で死に至る状況。 |
病いの慢性性(Chronicity) における「軌跡」について:人は軌跡をどのように予想し, 編みなおすのか (gifu-cn.ac.jp)掲載元:「慢性疾患の病みの軌跡」(医学書院)
ヘンダーソン(14の基本的欲求)
人の基本的欲求と看護の構成要素を14項目に示したものです。対象者のセルフケア能力をアセスメントし必要な援助を考える上で、理論を活用することで客観的に評価し、理解することが必要です。
- 正常に呼吸する
- 適切に飲食する
- あらゆる排泄経路から排泄する
- 身体の位置を動かし、またよい姿勢を保持する
- 睡眠と休息をとる
- 適当な衣類を選び、着脱する
- 衣類の調節と環境の調整により、体温を生理的範囲内に維持する
- 身体を清潔に保ち、身だしなみを整え、皮膚を保護する
- 環境のさまざまな危険因子を避け、また他人を傷害しないようにする
- 自分の感情、欲求、恐怖あるいは“気分”を表現して他者とのコミュニケーションをもつ
- 自分の信仰に従って礼拝する
- 達成感をもたらすような仕事をする
- 遊び、あるいはさまざまな種類のレクリエーションに参加する
- 正常”な発達および健康を導くような学習をし、発見をし、あるいは好奇心を満足させる
フィンクの危機モデル
ショック性危機に陥った中途障害者を想定した障害受容のプロセスを示しており、慢性疾患を有する対象者の、疾病の受容を理解するうえで手がかりとなります。
障害受容のプロセスを示したもの。障害の受容に至るまでには4つの段階があり、危機段階に応じた介入が必要とされます。
| 段階 | 特徴 |
|---|---|
| ①衝撃 | ショックを受け、強い不安を感じ、混乱した行動をとる。 |
| ②防御的退行 | 現実逃避、怒りや避難、権威の誇示等で自己を守る時期。不安は減少し、急性身体状況も回復する。 |
| ③承認 | 逃避しきれずに現実に直面する時期。不安や焦燥感が現れる。 |
| ④適応 | 残存機能の発揮により、自己のアイデンティティを再認識し、 価値観を構築する時期。 |
慢性期実習に行く前に持ち物をチェック!
血圧計
慢性疾患を有する患者さまのフィジカルアセスメントを行う上で、血圧コントロールは重要です。身体状況の変化や急変時の対応に備えて、いつでも測定できるようにしておくことが大切です。
SpO2モニター
血圧と同様に、呼吸状態の変動も重要な観察ポイントとなるため、いつでも酸素飽和度を観察できるよう準備しておくことが必要となります。
聴診器
全身状態のアセスメントを行う上で、聴診は非常に大切な情報となります。聴診の手技や方法を予習し、適切なフィジカルアセスメントを行うことが大切です。
時計(ナースウォッチ)
バイタルサイン測定の際、呼吸数や脈拍を計測するのに使用します。また、輸液を使用している場合、点滴の滴下確認の際にも時計を使って、秒数あたりの滴下数から滴下速度を調整します。
また、患者さまの症状の変化においては、いつから症状が出現したかなどを時刻とともに把握する必要があるため、常に時間を確認できるようにしておくことが必要です。
メモ帳
バイタルサインや観察した内容、調べておく必要があるものをすぐに書き留められるよう、常にメモ帳を携帯しておくことが必要です。
個人情報保護の観点から、メモを取る際のルールやメモ帳の使用の可否については、学校や病院の規則を確認しましょう。
意識レベルのスケール
意識が清明でない場合、意識状態を評価する上でスケールを使用します。JCS、GCSなどそれぞれのスケールの判断基準が示されている資料を手元に持っておくことで、実際の患者さまの状態に照らし合わせて評価することができます。
ポケットサイズの参考書
血液検査のデータの基準値や使用している薬の作用など、観察内容やカルテの情報をその場でアセスメントできるようにするために、検査値やスケールが載っているようなものがあると良いです。
カードタイプやポケットマニュアルのようなものもあり、ユニフォームのポケットに入れて持ち運びができるものが便利です。
用意しておきたい項目
- 血液データの検査値
- バイタルサインの基準値
- 輸液管理の観察項目、管理方法
- よく使用される薬の作用一覧(診療科により違いがある)
- ペインスケール
- 心電図波形の見かた
- 清潔ケア、移動介助などの手順