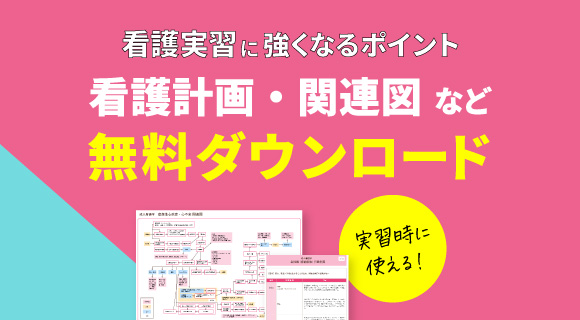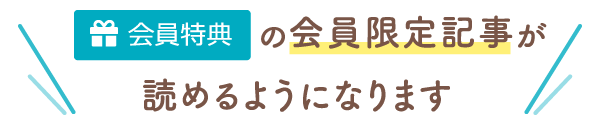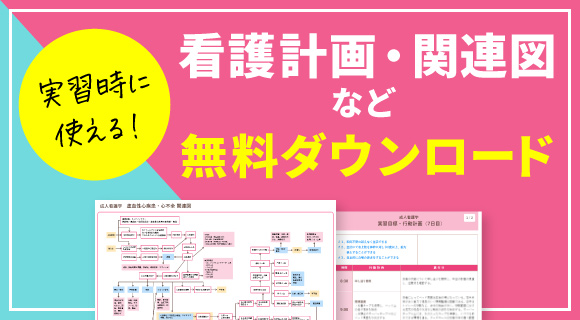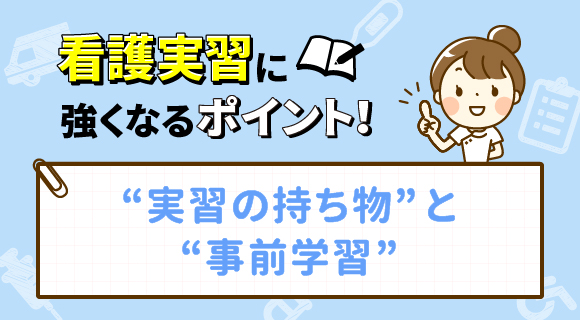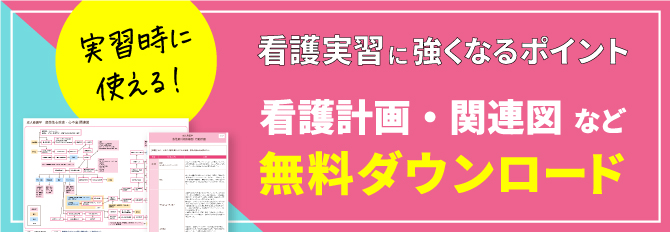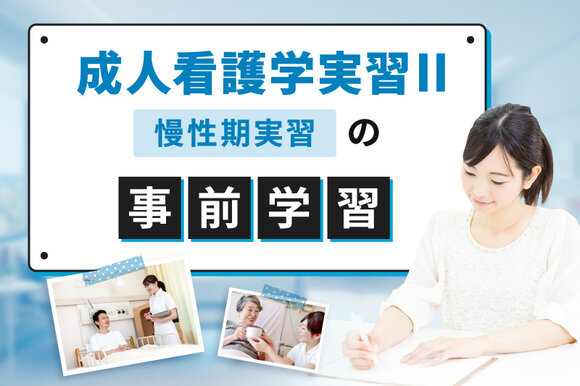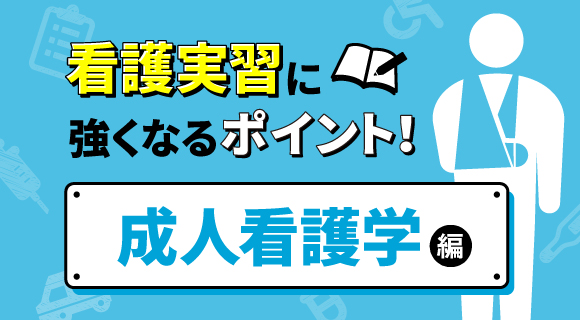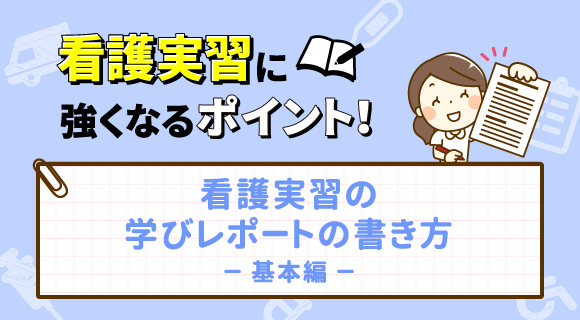成人看護学実習Ⅲ(終末期実習)の事前学習

終末期看護実習においては、終末期における対象が最期の瞬間までよりよく生きることができるよう、対象者の状態を正しく理解し、対象者や家族の苦痛の緩和を目指すことが大切です。ここでは、対象理解に必要な事前学習と、終末期看護実習で役立つ持ち物について解説します。
成人看護学実習Ⅲ(終末期実習)の特徴
終末期看護においては、さまざまな健康上の障害によって生じる課題に対処しながら、対象者本人や家族の思いに寄り添い、最期の瞬間までよりよく生きることを目指す支援をするということが特徴としてあげられます。
対象者はそれぞれの意思や思いを抱えており、それらの思いを尊重しながら終末期の生活に関わるには、対象の深い理解と、個別性のある看護が求められます。そのためには、対象者だけでなく家族も含めた苦痛の緩和をはかるとともに、対象を全人的に理解するという視点が大切です。
終末期実習前に勉強しておきたいポイント
終末期の看護においては、終末期における身体的変化を正しく理解しアセスメントするとともに、その時の症状や状態に応じたケアや苦痛の緩和を行うことが大切です。
また、対象者の精神心理的側面においても視点をおくとともに、死の受け入れや療養生活への希望についてもよく理解し、対象者の思いに寄り添った看護を目指す必要があります。
終末期実習で役に立つ資料
オピオイドの副作用と対応
オピオイドは、各種がんにおける疼痛に対し使用するほか、薬剤によっては慢性疼痛などに使用する場合もあります。
オピオイドの使用による身体的影響について正しく理解し、疼痛をアセスメントすることが大切です。
| 副作用 | 対応 |
|---|---|
| 便秘 |
|
| 嘔気・嘔吐 |
|
| 眠気 |
|
| せん妄 |
|
キューブラー・ロスの死の受容過程
死の受容過程を5段階で示したものです。現在の対象者の状態を客観的に評価しアセスメントする上で活用することができます。
| 第1段階 | 否認 | 「何かの間違いだ」「信じられない」といった反応を示し、病を現実のものと受け止めることができない段階 |
|---|---|---|
| 第2段階 | 怒り | 「自分だけがこんな目に遭うなんて」といった怒りがこみあげてくる段階 |
| 第3段階 | 取り引き | 「病気を治してくれたら、二度と悪いことはしない」などと、神や人と何らかの取り引きをしようとする段階 |
| 第4段階 | 抑うつ | 「もうだめだ」「生きていても仕方ない」と抑うつ状態になる段階 |
| 第5段階 | 受容 | 自らのおかれた状況を理解し、それを受け入れることができる段階 |
臨死期の兆候
臨死期には、身体面や精神面にさまざまな徴候が現れます。それらをよく観察しアセスメントすることが、対象の状態を理解する上で大切です。
| 呼吸 |
|
|---|---|
| 循環 |
|
| 排泄 |
|
| 精神状態 |
|
死の三徴候
- 心停止
- 呼吸消失
- 瞳孔散大・対光反射の消失
終末期実習に行く前に持ち物をチェック!
血圧計
終末期における慢性疾患を有する患者さまのフィジカルアセスメントを行う上で、血圧の変化は重要な観察ポイントです。数値だけでなく、見て、触れて五感を使って患者さまの状態を観察しましょう。
SpO2モニター
血圧と同様に、呼吸状態の変動も重要な観察ポイントとなるため、いつでも酸素飽和度を観察できるよう準備しておくことが必要となります。
時計(ナースウォッチ)
バイタルサイン測定の際、呼吸数や脈拍を計測するのに使用します。また、輸液を使用している場合、点滴の滴下確認の際にも時計を使って、秒数あたりの滴下数から滴下速度を調整します。
また、患者さまの症状の変化においては、いつから症状が出現したかなどを時刻とともに把握する必要があるため、常に時間を確認できるようにしておくことが必要です。
メモ帳
バイタルサインや観察した内容、調べておく必要があるものをすぐに書き留められるよう、常にメモ帳を携帯しておくことが必要です。
個人情報保護の観点から、メモを取る際のルールやメモ帳の使用の可否については、学校や病院の規則を確認しましょう。
意識レベルのスケール
終末期における患者さまの意識状態のアセスメントは重要です。意識状態を評価する上でスケールを使用します。
JCS、GCSなどそれぞれのスケールの判断基準が示されている資料を手元に持っておくことで、実際の患者さまの状態に照らし合わせて評価することができます。
医療用ペンライト
終末期において、瞳孔径の計測や対光反射の有無を判断する上で医療用のペンライトを使用します。
ペンライト本体に瞳孔径のスケールや目盛りが書いてあるものもあり、ベッドサイドですぐに計測できるような使いやすいものを選ぶとよいでしょう。
ポケットサイズの参考書
バイタルサインの変化や血液検査のデータの基準値、使用している薬の作用など、観察内容やカルテの情報をその場でアセスメントできるようにするために、検査値やスケールが載っているようなものがあると良いです。
カードタイプやポケットマニュアルのようなものもあり、ユニフォームのポケットに入れて持ち運びができるものが便利です。
用意しておきたい項目
- 血液データの検査値
- バイタルサインの基準値
- 瞳孔径のスケール
- 呼吸様式の種類の一覧(異常呼吸など)
- 輸液管理の観察項目、管理方法
- よく使用される薬の作用一覧(診療科により違いがある)
- ペインスケール
- 清潔ケア、移動介助などの手順