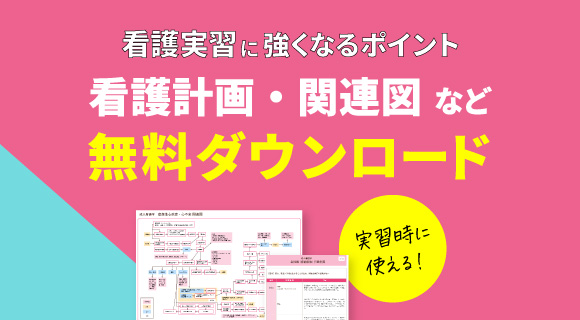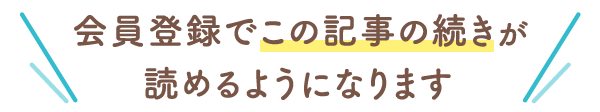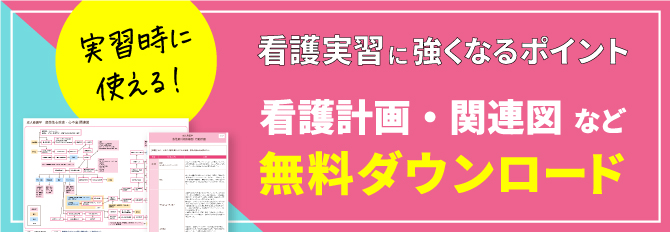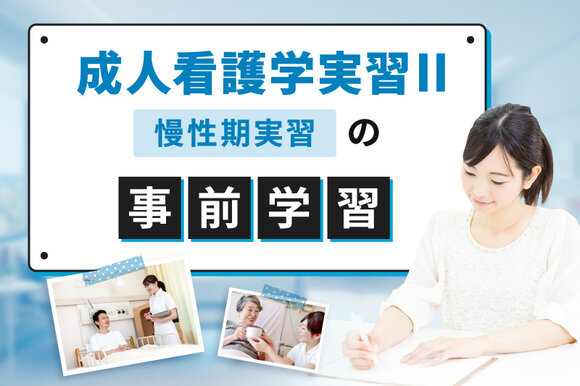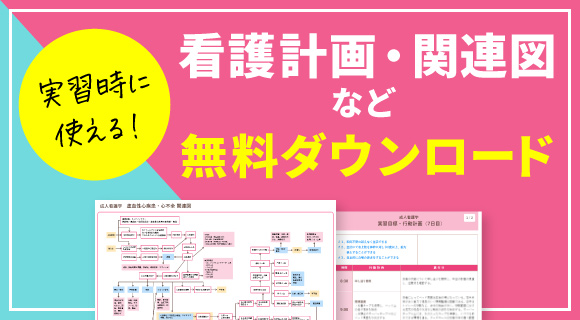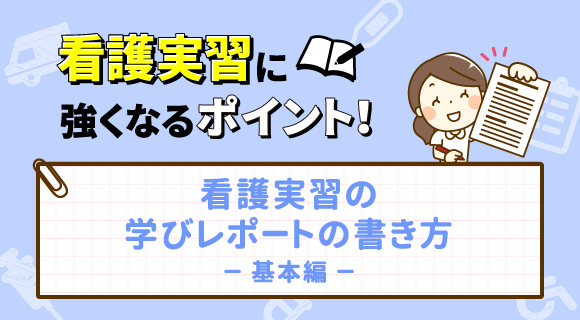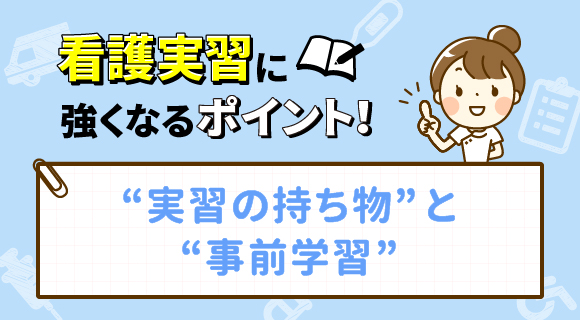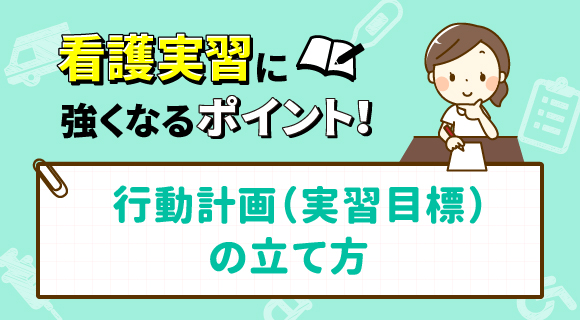事例あり!成人・慢性期看護過程の書き方【看護問題・看護計画編】

慢性期における看護過程の看護問題・看護計画は、急性期とは異なり、「その人らしさ」や「生活」に目を向けた個別性のある視点が求められます。この記事では、成人看護学実習Ⅱにおける慢性看護過程の書き方を、事例を交えて詳しく解説しています。ぜひ、参考にしてください。
身体的・社会的・心理的側面から看護問題を考える!
慢性期実習では、急性期と異なり身体症状が落ち着いている場合が多く、「看護問題が見つけにくい」と感じる看護学生も少なくありません。
慢性期の患者さまの看護では、「疾患を診る」のではなく、「その人を診る」といった視点が重要です。また、身体的側面だけではなく、生活背景や心理状態にも目を向けることで、より個別性のある看護問題を捉えることができます。
合併症のリスク
慢性疾患をもつ患者さまは、複数の疾患や既往歴を抱えていることが多く、それぞれが相互に影響し合い、重大な健康リスクを高める可能性があります。
たとえば、糖尿病に脂質異常症や高血圧が加わると、動脈硬化による血管障害のリスクが増大し、心血管疾患や脳血管障害の発症につながるおそれがあります。こうした背景をふまえ、既往歴や現在の疾患状況に基づいて看護問題を明確にし、合併症の予防や早期発見につなげる視点が重要です。
患者さまの背景や生活環境
患者さまの生活背景や家庭環境、経済状況、住環境などを把握することは、慢性期における個別性の高い看護を行う上で重要です。慢性期では医療的な治療だけでなく、身体機能の維持・改善、生活習慣の見直し、社会復帰への支援など、生活全体を支える視点が求められます。
たとえば、住環境や家族の支援状況を把握することで、退院後の生活を見据えた支援計画を立てやすくなり、患者さま自身の生活の質を高める看護問題を明確にすることができます。背景の把握は、患者さまが自立した生活を送るための支援につなげる第一歩となります。
不安・孤独感・モチベーション
慢性期にある患者さまは、長期にわたる療養生活の中で、不安や孤独感、抑うつ的な気分を抱えることがあります。こうした心理的な側面を的確に把握することは、個別性のある看護を行う上で欠かせません。
患者さまの表情や言動、生活リズムの乱れなどから心理状態を読み取り、精神的なサポートを行うことで、不安や孤独感の軽減、生活習慣の改善、治療へのモチベーションの向上といった看護課題に対応することが可能となります。心理的な支援は、患者さまが前向きに療養生活を送るための基盤を整える重要な看護の一つです。
看護問題の具体例
♯1 血糖コントロール不良による合併症発症のリスク
♯2 治療に対する意欲低下により、自己管理が困難な状態にある
♯3 家族の支援体制に限界があり、在宅生活への不安がある
♯1 血糖コントロール不良による合併症発症のリスク
A氏は長年Ⅱ型糖尿病の治療を継続しているものの、間食の習慣や運動不足、治療に対するモチベーションの低下から、血糖コントロールが不良な状態が続いています。
現在のHbA1cは8.3%、空腹時血糖値は180mg/dlと高値であり、すでに糖尿病性腎症ステージ3を発症しています。また1年半眼科を受診していないことから、糖尿病性網膜症の発症リスクも懸念されます。血圧や脂質異常も認められており、神経障害や心血管イベントなどの合併症を招く可能性も否定できません。
このように、血糖コントロール不良な状態が続くことで、日常生活に大きな影響を与える深刻な合併症を引き起こすリスクが非常に高い状態です。患者さま自身の治療への無力感やインスリン治療への抵抗感といった心理的背景にも配慮しながら、まずは病状の理解と、自己管理の重要性を実感できるような支援が必要です。医師や栄養士などの他職種と連携しながら、患者さまの生活に寄り添った現実的な目標を共有し、血糖コントロールの改善を目指す必要があります。
♯2 治療に対する意欲低下により、自己管理が困難な状態にある
A氏は糖尿病の自己管理に対して「もういいかな」「どうせ治らない」と発言しており、長年の治療継続に対する疲労感や諦めの感情が強く見られます。これらは慢性疾患を抱える高齢者にしばしば見られる心理的な反応であり、治療に対する意欲やエネルギーの低下が明らかです。実際に、食事療法に関しては指導内容が実行されておらず、服薬の管理も自己任せで、インスリン治療には強い抵抗感を示しています。
このような心理的要因は、血糖コントロールや合併症予防の妨げとなるだけでなく、患者自身の治療への主体性を損ない、治療の継続性を不安定にするリスクがあります。したがって、A氏が自らの健康状態を受け止め、自己管理の目的や必要性を納得できるような支援が求められます。特に、孫との関わりやガーデニングといった生きがいに注目し、ポジティブな動機づけを通して治療への意欲を回復させる関わりが重要です。
♯3 家族の支援体制に限界があり、在宅生活への不安がある
A氏は妻との二人暮らしで、子どもは遠方に住んでおり、日常的な支援は受けられない状況です。妻自身も高血圧や不整脈といった持病を抱えており、「主人が投げやりで困っている」と語るように、家事や通院の付き添いに対してすでに負担を感じています。今後、A氏の病状が進行し、さらに支援が必要となった場合、現在の家族構成では対応が難しいことが予想されます。
また、地域包括支援センターとの関わりはあるものの、日常生活において必要な支援が十分に活用されていない印象もあります。今後、在宅療養を安定的に継続するためには、家族の負担を軽減しつつ、外部資源の活用を具体的に検討する必要があります。介護保険サービスや地域支援体制と連携し、退院後の生活を見据えた支援体制の再構築が求められます。
看護計画を書く時のポイント
長期的な視野を持つ
慢性疾患を抱える患者さまに対しては、入院中の症状改善だけでなく、退院後の生活まで見据えた長期的な支援が求められます。A氏の場合では、長年Ⅱ型糖尿病と付き合ってきており、現在は糖尿病性腎症ステージ3を併発し、生活習慣の見直しや治療に継続が必要な段階にあります。入院期間が長くなることで、血糖コントロールや生活習慣の変化により身体的・精神的な状態が変動する可能性もあるため、看護計画は画一的ではなく、定期的な評価と見直しを行う柔軟な姿勢が重要です。
また、今後の生活を考えたとき、退院後も継続して自己管理が行えるように、環境調整やサポート体制の調整、地域包括支援センターとの連携なども視野に入れる必要があります。患者さまが安定した療養生活を送るためには、「これからどのように暮らしていくのか」という長期的な視野を持った支援が不可欠です。
患者さまの意思決定を反映する
慢性期の看護では、患者さまがご自身の疾患と向き合い、納得したうえで治療に取り組めるよう支援することが大切です。A氏は長年にわたって糖尿病の治療を継続してきましたが、自己管理に対する疲れや無力感から、「もういいかな」「どうせ治らないし」といった発言がみられ、治療への意欲が低下しています。また、インスリン注射に対しても強い抵抗感を示しており、新たな治療方針の受け入れが難しい状況です。
このような患者さまに対しては、看護師が一方的に治療を押し付けるのではなく、不安や思いに丁寧に耳を傾け、心理的な受容の過程を支えることが求められます。インスリン治療の必要性についても、選択肢を提示しながら段階的に説明し、患者さまご自身が納得して意思決定できるように援助することが重要です。
また、A氏は「孫に会えるのが楽しみ」と話しており、それが大きな生きがいとなっていることが伺えます。このようなポジティブな感情や価値観を、治療の目標に結びつけることで、自己管理への意欲を引き出すきっかけとなる可能性があります。たとえば、「健康を維持して孫と過ごす時間を大切にしたい」といった目標を共有することにより、生活習慣の改善に前向きに取り組む支援が期待されます。
このように、慢性期の看護計画では、患者さまの価値観を尊重し、個別性を重視した関わりを通して、患者さまが「自分で選んだ」と実感できるような治療や生活のあり方を支援することが、継続的な療養生活の質を高める上で非常に重要です。
【事例つき】看護計画の具体例とよくある間違い
血糖コントロール不良による合併症発症のリスク
| 看護問題 |
|---|
| ♯1 血糖コントロール不良による合併症発症のリスク |
| 目標 |
|
短期目標:自己の血糖管理状況を理解し、必要な生活習慣の見直しができる 長期目標:安定した血糖コントロールが維持され、合併症を予防できる |
| OP |
|
| CP |
|
| EP |
|
【NG①】抽象的で汎用的なOP(観察項目)
例:「バイタルサインの変動」だけを記載
糖尿病に特有の観察ポイント(血糖値、末梢循環、皮膚状態など)に触れられておらず、合併症発症リスクに対する具体性が欠けている。
【NG②】CP(実施項目)が「指導する」「促す」だけ
例:「インスリン自己注射を指導する」「規則正しい食事を促す」
どのように、どんな工夫で実施するのか記載がありません。また、本人の理解度や拒否感への配慮がなく、単なる「やることリスト」にとどまってしまいます。
【NG③】EP(教育項目)が一方的、非段階的
例:「血糖管理の大切さを説明する」
知識の伝達だけで、患者の納得や受け入れ状況に配慮できていません。「説明した=理解した」と思い込んでしまう点が看護学生に見られがちです。
【NG④】目標が曖昧
例:目標が「血糖コントロールができるようになる」
どのような状態になれば「血糖コントロールができた」と評価できるのか不明瞭です。 具体的な数値や、行動や発言の変化などを基準に目標を設定する必要があります。
治療に対する意欲低下により、自己管理が困難な状態にある
| 看護問題 |
|---|
| ♯2 治療に対する意欲低下により、自己管理が困難な状態にある |
| 目標 |
|
短期目標:現在の健康状態や治療の目的について自分の言葉で表現できるようになる 長期目標:自身の価値観や生活の楽しみと結びつけた目標を持ち、治療への意欲が持てるようになる |
| OP |
|
| CP |
|
| EP |
|
【NG①】OP(観察項目)が曖昧
例:「意欲の有無を観察」「不安の有無を観察」
「意欲」や「不安」は非常に主観的なもので、具体的な言動や表情、発言を通して観察するべきです。
【NG②】CP(実施計画)が一方的
例:「生活指導を行う」「インスリン療法の必要性を説明する」
本人が受け入れられていない段階での一方的な指導は、むしろ反発を招いてしまいます。本人の気持ちや生活習慣に寄り添ったアプローチが不可欠です。
【NG③】EP(教育項目)で「説明する」のみ
例:「自己管理の重要性を説明する」
教育項目=説明ではありません。看護学生は「説明したからOK」と思いがちですが、慢性期看護では、本人の価値観やペースに合わせた継続的な対話と支援が重要です。
【NG④】目標が曖昧、行動レベルに合っていない
例:「意欲が向上する」「自己管理ができるようになる」
何を持って「意欲が出た」とするのか、行動で測れないと評価はできません。「食事管理に前向きな発言が聞かれる」など行動変化を基準とするべきです。
おわりに
慢性期看護学実習では、「病気と共に生きる」患者さまの人生に深く関わり、一人ひとりの価値観や生活に寄り添う看護の奥深さとやりがいを強く感じられるはずです。ぜひ、頑張ってください。