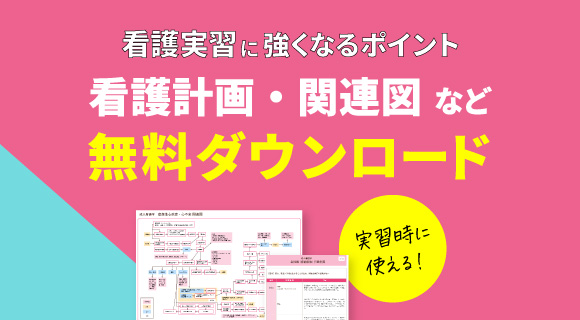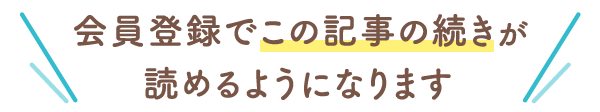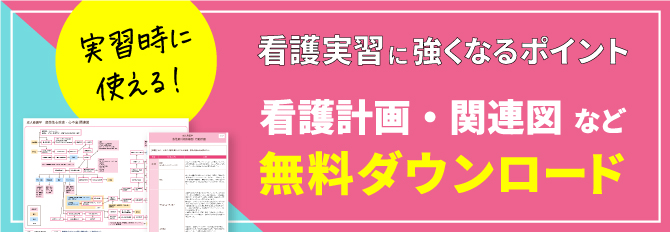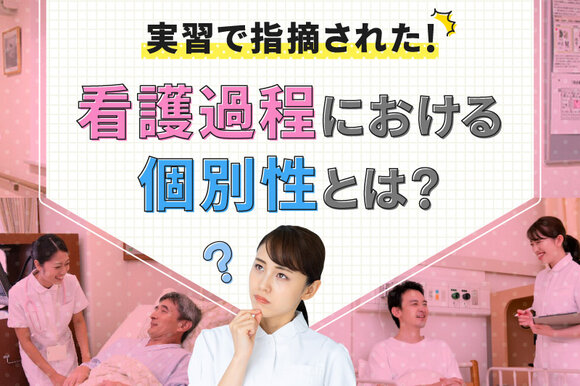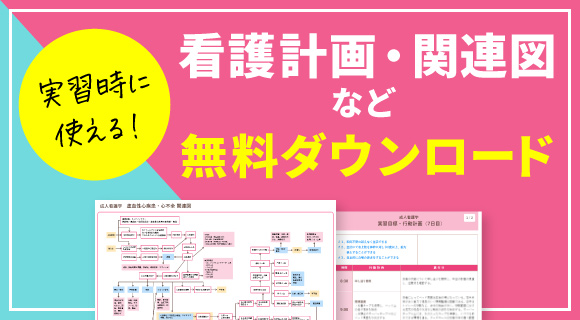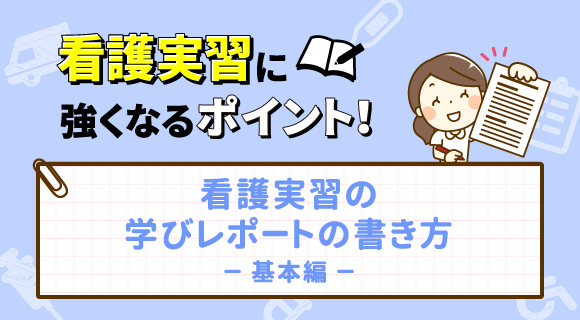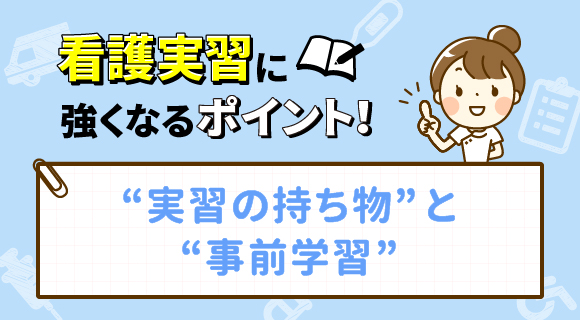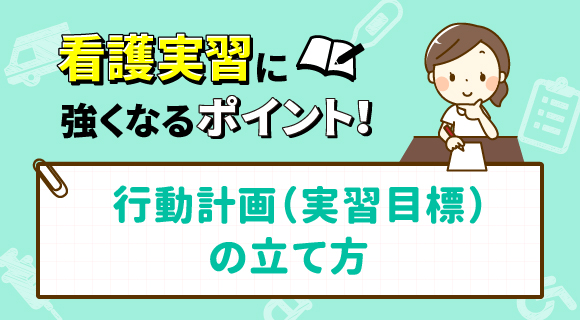事例あり!精神看護過程の書き方【看護問題・看護計画編】~統合失調症の具体例~

精神看護では、「その人らしい暮らし」や「必要な支援」に目を向けた看護問題の把握が大切です。この記事では、オレムのセルフケア理論を用いて、統合失調症の事例から看護問題の見つけ方と看護計画の立案方法を詳しく解説しています。ぜひ、精神看護実習の参考にしてください。
看護問題の見つけ方と優先順位の考え方
看護問題を見つけるポイント
看護問題を見つけるポイントは、「セルフケアの、どの部分に障害があるか」を軸に考えることです。これは、オレムのセルフケア理論に基づいた考え方で、セルフケア要求(食事、清潔、排泄、治療の継続など)を満たすために必要な能力が欠けているとき、看護の必要性が生じるとされています。
精神疾患をもつ患者さまは、疾患そのものや症状の影響でセルフケアの多くが困難になっていることが多く、それが看護問題となって表れます。
統合失調症の患者さまの場合
「薬の自己管理ができていない」「対人関係がうまく築けず社会生活に支障がある」「幻聴や妄想のために現実認識が乏しい」といった問題がよく見られます。これらはすべて、セルフケアに必要な知識・判断力・意欲・社会的スキルの欠如ととらえることができ、オレム理論における「セルフケア不足の状態」です。患者さまがどのセルフケア項目を自立して行えず、どの部分に援助が必要かを丁寧にアセスメントすることで、看護問題が明確になります。
精神科看護においては、身体疾患と異なり急変が少ないことから、「生命の危機」を最優先とする考え方よりも、「患者の主観的苦痛の強さ」「社会生活への影響の大きさ」「再発予防の必要性」といった観点を重視して看護問題の優先順位を判断します。
薬の自己中断歴がある患者さまの場合
薬の自己中断歴がある患者さまでは再発のリスクが高いため、服薬支援が優先されます。妄想による被害意識が強く、家族や周囲との関係性が悪化している場合は、社会的孤立を防ぐために早期の介入が必要です。
このように、オレム理論によってセルフケアの欠如を明確にし、そこから導かれる看護問題を個別的に整理しながら、 精神科特有の観点から優先順位を検討していくことが大切です。症状の重さだけではなく、患者さまの生活機能や将来的なリスク、再発の可能性なども踏まえ、実践的で意味のある看護計画へとつなげていきましょう。
看護問題の具体例
♯1 被害妄想による対人関係の困難と社会的孤立
B氏は被害妄想が持続し対人緊張が強いため、他者との信頼関係が築けず孤立している状態にあります。妄想を頭ごなしに否定せず、安心できる関係性の中で徐々に他者との関わりを広げられるような支援をしていく必要があります。
♯2 気力・無為によるセルフケアの困難
B氏は陰性症状による無気力から、洗面・更衣・服薬などの日常生活全般に支援が必要な状態でセルフケア能力が低下しています。小さな成功体験を積み重ねながら活動意欲と自信を引き出す支援が必要です。
♯3 病識の欠如および治療意欲の低下
B氏の「このままでいい」といった発言から病識や治療意欲の低下がみられ、主体的な行動が乏しい状態です。本人の価値観に寄り添いながら病状への理解を促し、内発的動機づけにつながる支援が必要です。
♯4 家族の理解不足と退院後支援への不安
家族は支援に協力的であるものの、病気に対する理解が十分ではなく、退院後の関わり方に不安を抱えています。精神教育を通じて理解を深め、今後の支援体制を整えるための関わりが求められます。
看護計画の具体例とポイント
統合失調症は時期によって症状や生活の課題が異なります。回復期では「症状の再燃予防」「生活リズムの再構築」などの課題が中心となり、慢性期では、「意欲低下への支援」「社会参加の促進」などが重要です。
看護問題を時期ごとに分けることで、その時期に最も必要な支援に焦点を当てられます
回復期
♯2 気力・無為によるセルフケアの困難 の看護計画
| 看護問題 |
|---|
| 気力・無為によるセルフケアの困難 |
| 長期目標 |
|
| 短期目標 |
|
| OP |
|
| TP |
|
| EP |
|
慢性期
♯1 被害妄想による対人関係の困難と社会的孤立 の看護計画
| 看護問題 |
|---|
| 被害妄想による対人関係の困難と社会的孤立 |
| 長期目標 |
|
| 短期目標 |
|
| OP |
|
| TP |
|
| EP |
|
♯4 家族の理解不足と退院後支援への不安 の看護計画
| 看護問題 |
|---|
| 家族の理解不足と退院後支援への不安 |
| 長期目標 |
|
| 短期目標 |
|
| OP |
|
| TP |
|
| EP |
|
看護計画を書く時のポイント
精神看護学における看護計画では、統合失調症の症状や回復段階に応じた「個別性」と「段階的支援」が重要なポイントです。特に回復期と慢性期では、患者さまのニーズや支援の方向性が異なるため、それぞれに応じたアプローチが求められます。
「回復期」のアプローチ方法
回復期では、陰性症状(無気力・自閉傾向・意欲低下など)が目立ちやすく、基本的な生活リズムやセルフケアの再構築が目標となります。看護計画では、「日中の活動性を高める支援」「服薬自己管理の促進」「対人場面への段階的参加の支援」などが中心となります。患者さまの自己決定を尊重しながら、小さな成功体験を積み重ねていく視点が大切です。
「慢性期」のアプローチ方法
一方、慢性期では再発予防と地域生活への適応支援が主な目的となります。「服薬継続の動機づけ」「ストレス対処スキルの強化」「地域資源の活用支援」などが計画に盛り込まれます。家族との関係や生活環境の調整も重要な要素となります。
おわりに
精神看護においては、精神症状への対応だけでなく、患者さまの自己効力感や生活の質の向上を目指す看護計画を立てることが求められます。根拠ある視点で、段階的に支援内容を構成することが、信頼関係の構築にもつながります。
精神看護実習では、患者さまの症状だけでなく、生活背景や思いに寄り添う視点が求められます。一人ひとりの「その人らしさ」を大切にしながら、自分自身の看護観を育てる大切な機会として、ぜひ頑張ってください。