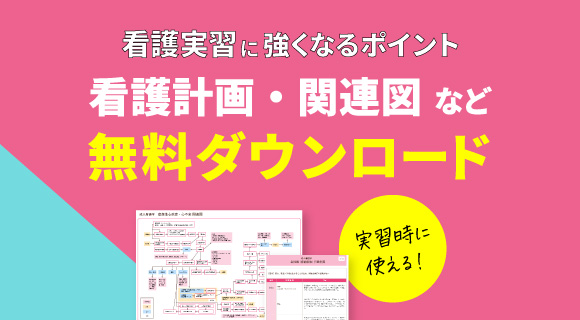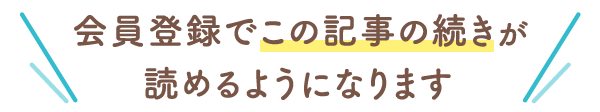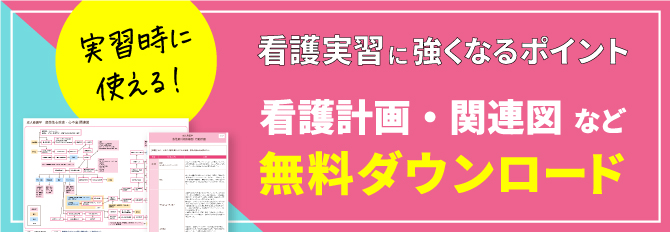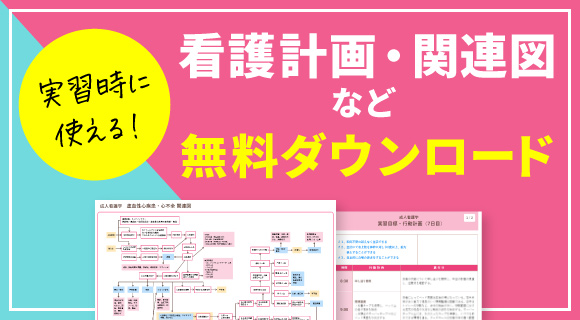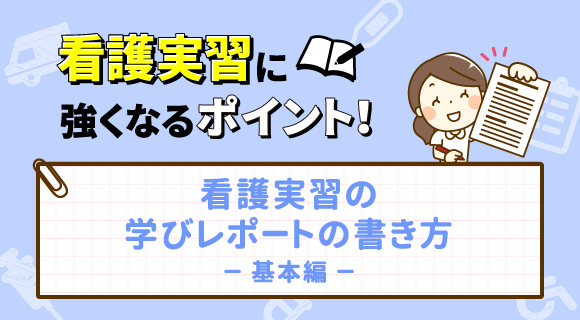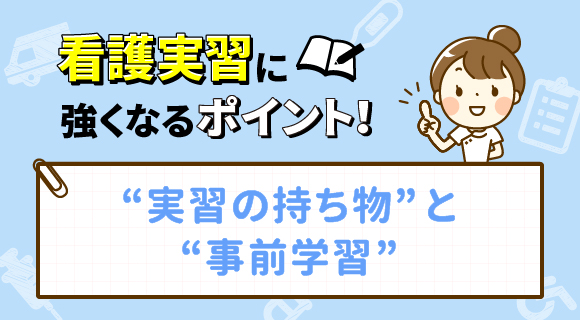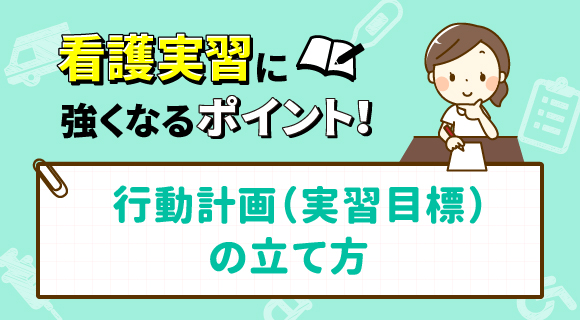保育園実習の目標の決め方・学びレポートの書き方【小児看護学】

小児看護学の実習の中でも、保育園実習は「医療的ケア」ではなく「生活を支えるかかわり」を学ぶ貴重な機会です。病院実習では出会えない「健康な子どもたち」の姿から、成長発達の過程や、生活リズム・遊び・対人関係の形成などをリアルに観察できます。
本記事では、保育園実習の目的・目標の立て方から、学校提出用の目標例文、さらに学びレポートのテーマ・書き方のコツまで、看護学生がそのまま使える形で詳しく解説しています。
保育園実習の目的と目標 ~実習では何をする?~
保育園実習の目的
学校や養成機関によって表現は異なりますが、保育園実習のシラバスに記載される目的には、以下のような内容が多く見られます。
- 乳幼児の成長・発達段階を理解し、発達に応じた援助や関わり方を学ぶ
- 健康な子どもの生活リズム(遊び・食事・排泄・休息)を観察し、生活支援の重要性を理解する
- 子ども・保護者・保育士との関わりを通して、対人関係形成能力を養う
- 集団生活の中での子どもの社会性や個性を理解し、その違いを尊重する態度を養う
保育園実習の目的は「看護技術を学ぶ場」ではなく、子どもの生活そのものを支える視点を身に付けることにあります。
保育園実習の目標の決め方
シラバスに記載されている全体目標をベースに自分が実習を通してできるようになりたいことをより具体的に落とし込む必要があります。
【例】シラバス目標
乳幼児期の子どもの成長発達を評価し、発達に応じた子どもへの援助が実践できるようになる
これを自分の目標に変換する際は、以下のポイントを入れていきましょう。
| 要素 | 考え方の例 |
|---|---|
| 対象児の年齢 | 0歳児・1歳児・年少クラスなど |
| 関わりの場面 | 遊び・食事・トイレ・午睡・着替えなど |
| どんな姿勢で関わるか | 安心感を与える声かけ、自立を促す援助など |
実際の保育園実習で行う年齢別の関わり方は、以下の通りです。
| クラス | 主な関わり内容 |
|---|---|
| 0歳児クラス | 抱っこ・ミルク・午睡の見守り・ハイハイやつかまり立ちの観察 |
| 1〜2歳児クラス | ブロック・おままごと遊び・食事介助・トイレトレーニングの補助 |
| 年少〜年長クラス | 鬼ごっこ・お絵描き・工作、給食は以前のお手伝い・集団活動の見守り |
保育園実習の目標を決める際は、まず 学校のシラバスに記載されている「実習の目的・目標」をしっかり確認する ことから始めます。シラバスの内容は、学校が学生に「どんな力を身につけてほしいか」を示した大切な指針です。
指針を理解した上で、自分が配属されるクラス(年齢層)や期間、関心のあるテーマを踏まえて、「自分自身の到達目標(個人目標)」を設定します。
到達目標を作成する際の3つのポイント
①シラバスの目的を確認する
「乳幼児期の子どもの成長発達を評価し、発達に応じた子どもへの援助が実践できるようになる」など実習全体の方向性を把握する。
②自分の実習環境を具体化する
どのクラスでどんな子ども達と関わるのかを想定する。
【例】1歳児クラス:集団生活に慣れていない子が多いなど
③自分の課題や関心を反映させる
「子どもの自立を支える声かけを学びたい」「発達に合わせた援助を実践したい」など、自分の成長目標を加える。
このようにして、学校の目的(大きな方向性)と自分の学びたいテーマ(個人の焦点)を組み合わせることで、提出用の目標として具体性と個別性が出ます。
保育園実習の個人目標例3選
【例1】1歳児クラスで関わる子どもの発達段階を観察し、一人ひとりのペースを尊重した声かけや援助を行う。
【例2】遊びや食事の場面で子どもが安心して関われるよう、笑顔や姿勢、言葉遣いに配慮しながら信頼関係の形成を目指す。
【例3】生活リズム(排泄・睡眠・遊び)を通して子どもの自立を促す援助を学び、看護職として適切な関わり方を考察できるようにする。
保育園実習の学びレポートテーマ例
保育園実習の学びレポートのテーマ例を分類別にまとめました。
| 分類 | テーマ例 |
|---|---|
| 成長発達の観察 | 1歳児の自己主張とイヤイヤ期の対応から学んだこと |
| 遊びの意味 | ごっこ遊びを通して見えた子どもの社会性の発達 |
| 食事の援助 | 「自分で食べたい」という子どもの自立心への関わり |
| 食事の援助 | 「自分で食べたい」という子どもの自立心への関わり |
| 感情への寄り添い | ケンカ後の仲直りを支える保育士の声かけの工夫 |
| 安全管理 | 午睡時の見守りから学んだ「命を預かる責任」 |
| 家庭との連携 | 送迎時の保護者対応を見て感じた信頼関係の築き方 |
レポートテーマの活用例
それぞれの分類には、「実際の保育場面で観察できること」や「看護の視点につながる学び」が含まれています。
たとえば次のように活用できます。
成長発達の観察
子どもの年齢や発達段階を踏まえ、「どんな行動がどんな成長を示しているのか」を考察するテーマ
遊びの意味
遊びを通して子どもの社会性・創造性がどう育まれているかを学ぶテーマ
食事の援助
自立や生活リズムの確立など、看護にもつながる生活支援の視点で書けるテーマ
感情への寄り添い
子ども同士のトラブルや気持ちの変化にどう関わるかを考察するテーマ
安全管理
午睡や遊び場面などでのリスク管理を通して、「命を預かる責任」を学ぶテーマ
家庭との連携
保護者対応を通して「信頼関係」「チームで支える子育て」を学ぶテーマ
学びレポートの書き方のポイント
保育園実習後に提出する「学びレポート」は、単なる感想文ではなく、子どもの発達や援助の意味を看護の視点で振り返るレポートです。実習中に見た子どもの姿や、保育士の関わりを自分なりに分析し、「なぜそうしたのか」「どんな意図があったのか」を考えることが大切です。
ここでは、「学びレポートを書くときの3つのポイント」を紹介します。これらを意識してまとめることで、より具体的で看護的な内容に仕上げることができます。
「ただの感想」ではなく「成長発達と援助の視点」を入れる
×「子どもがかわいかったです」
○「2歳児がスプーンを反対向きに持って食べていた。発達段階として手指の巧緻性の発達途中であり、保育士は無理に直さず見守っていた。この関わりから“自立を促す支援”の重要性を学んだ。」
「保育士の関わり」も必ず観察して書く
子どもとの関わりだけでは看護的考察になりにくいため、保育士の声かけ・距離感・援助のタイミングを分析しましょう。
2歳児が他児とのおもちゃの取り合いで泣いてしまった場面で、保育士はすぐに介入せず、少し距離を置いて見守りながら「どうしたのかな?」と優しく声をかけていた。その後、子ども自身が言葉で気持ちを伝えられるようになった。
この対応から、子どもの自立心や社会性を育むためには、必要以上に介入せず“見守る支援”が大切であることを学んだ。
「看護と保育の共通点・違い」を最後にまとめる
保育園では「できるまで待つ支援」が多く見られた。病院では安全上、援助の介入が早くなる場面も多いが、自立発達を促すには「待つ勇気」も重要であると感じた。
おわりに
保育園実習は「遊びに行く場」ではなく、成長発達を観察する専門職としての視点が求められます。明確な目標を立て、自分なりの学びの視点を持って臨めば、短期間の実習でも多くの気づきが得られます。この記事の目標例・レポートテーマを活用し、自信を持って実習に臨んでください。