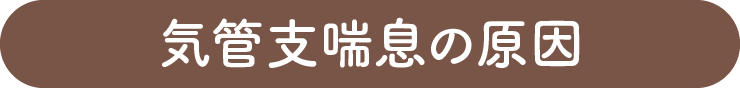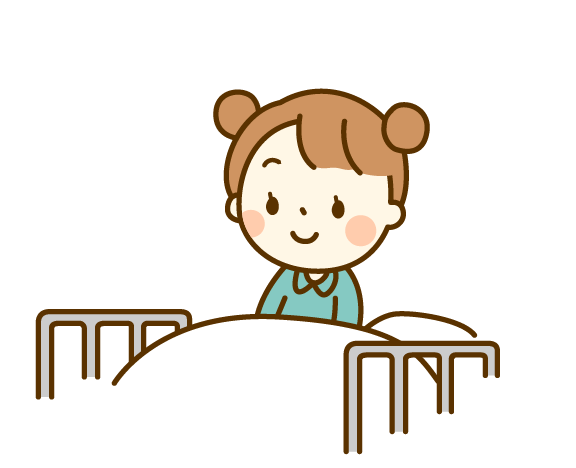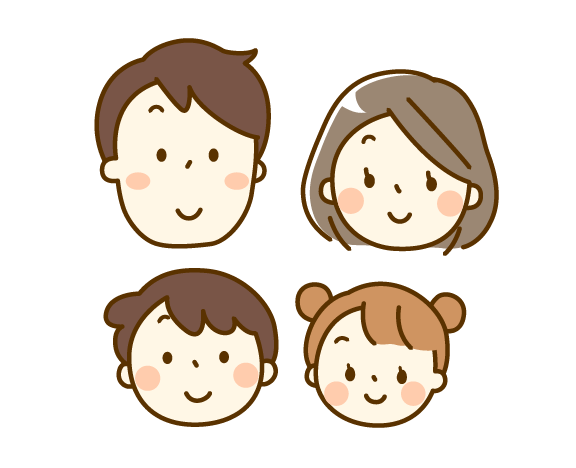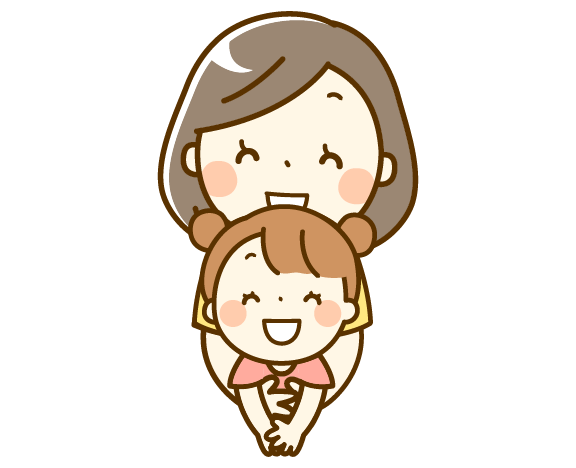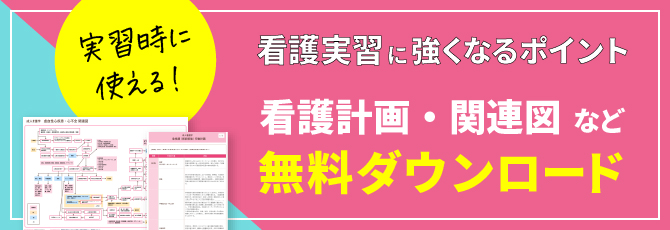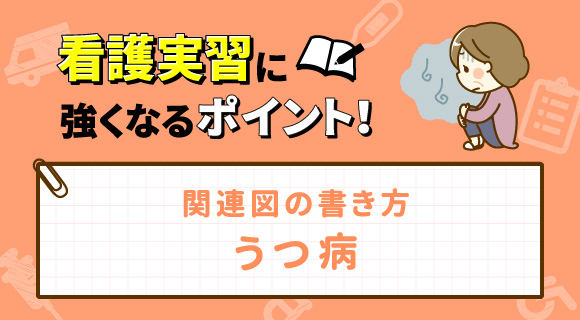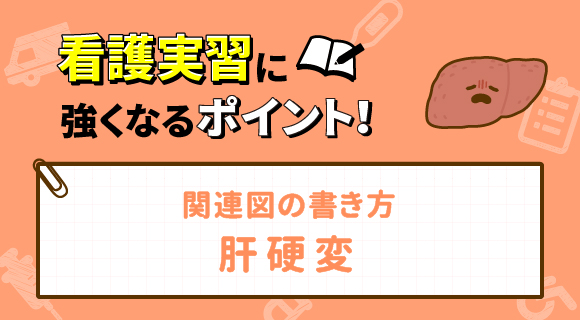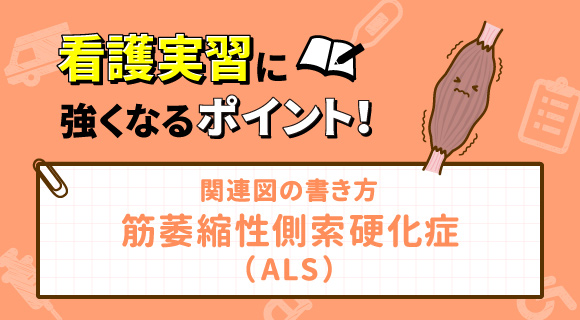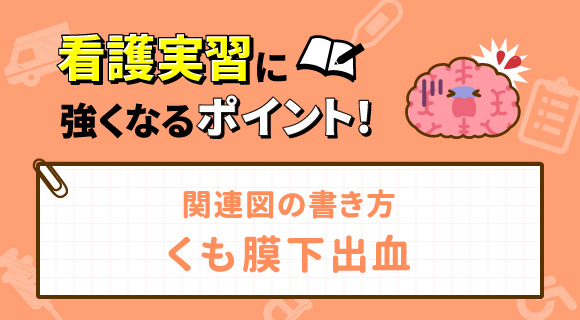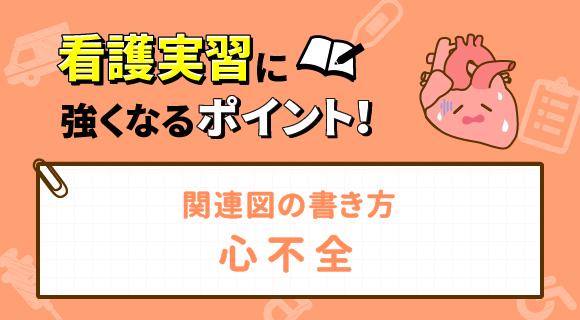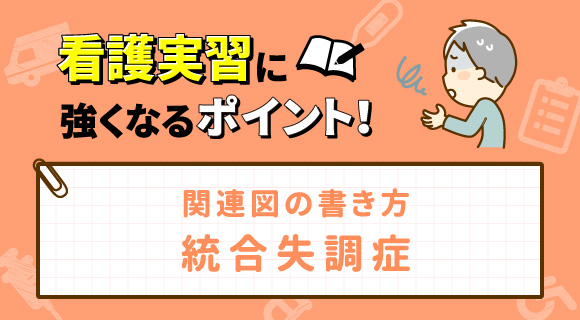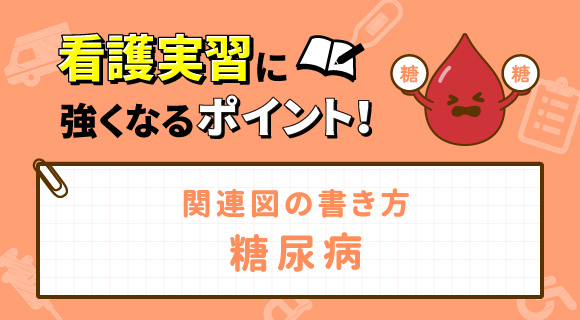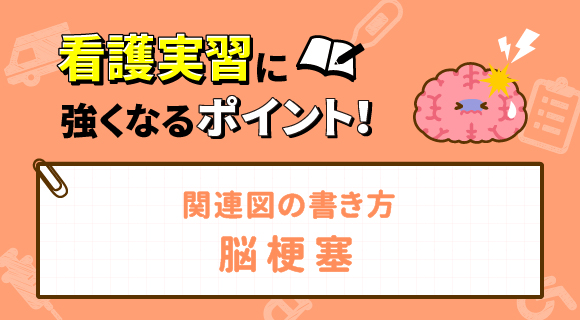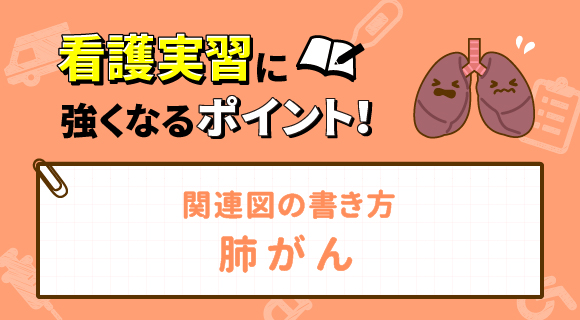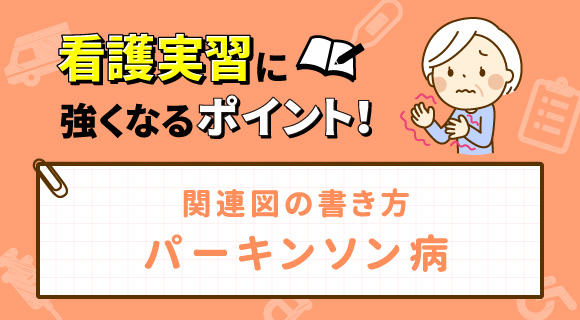気管支喘息とは、空気の通り道である気管支が慢性的に炎症を繰り返すことで狭くなり、呼吸時にヒューヒューやゼーゼーといった異常音が発生する喘鳴や、呼吸困難などの発作が生じる病気です。
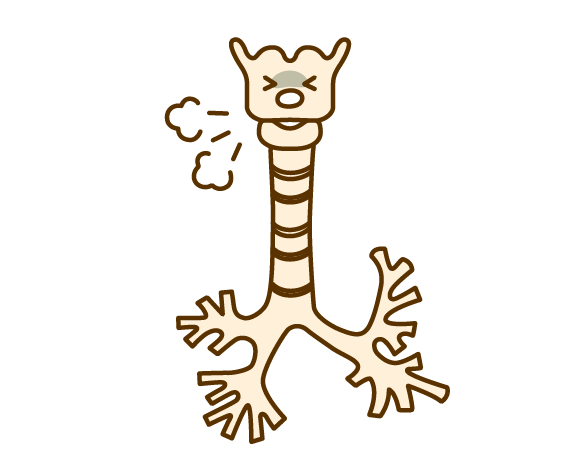
アレルゲン
主なアレルゲンは、ハウスダスト、ダニ、ペットの毛やフケ、カビ、花粉などです。血液検査や皮膚検査で調べることが可能です。
感染症
風邪やインフルエンザなどのウイルス感染によって気道が炎症し、喘息発作を起こすことがあります。風邪が治ってから咳が続く咳喘息を放置していると、気道の過敏性が増し、炎症が悪化するため気管支喘息に移行する場合があります。
大気汚染
PM2.5や黄砂、排気ガスなどの大気汚染物質は体内に入るとアレルギー反応を引き起こし、喘息発作を誘発します。
たばこの煙
たばこには数千種類の化学物質が含まれており、自身が喫煙者ではなくても、副流煙による受動喫煙が発作や症状の憎悪の要因になります。線香や花火の煙などでも発作を起こす可能性があります。
運動
運動をすると呼吸が速くなり、乾燥した冷たい空気が気道に入るため、それが刺激となって喘息を誘発する場合があります。空気が乾燥して冷たい冬期は特に発作が起きやすいです。
気象条件
気温・湿度の変化が大きい季節の変わり目や、台風での低気圧などが発作を起こす誘因になります。
ストレス
過労や睡眠不足など、身体的なストレスや心理的なストレスも喘息発作に影響します。
気管支喘息は、重症度によって4つに分類されます。

間欠型
症状の出現が週1回未満で、日常生活に大きな影響がない状態です。症状が出現しても救急薬のみで治まり、持続しない状態です。
軽度持続型
軽い症状が週1回以上出現するが毎日ではなく、症状の持続は短い状態です。月1回以上、日常生活や睡眠に影響が出ます。
中等度持続型
軽い症状が毎日生じ、ときに中・大発作となる状態です。週1回以上、日常生活や睡眠に影響を及ぼします。
重症持続型
毎日症状が出現し、週1、2回は大きな発作があり日常生活に制限がある状態です。