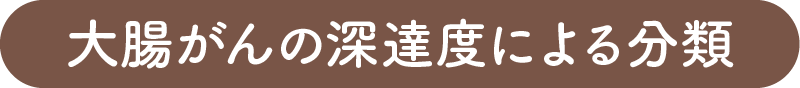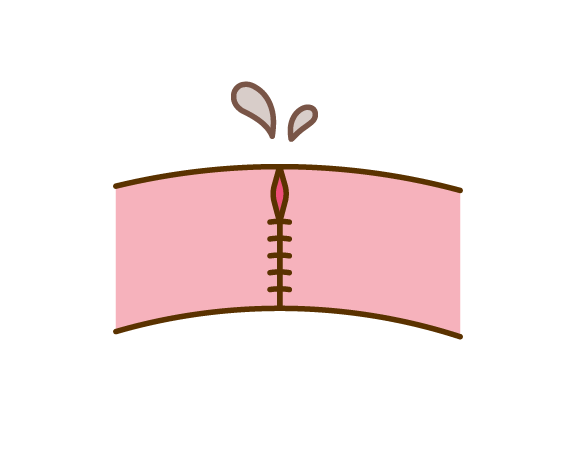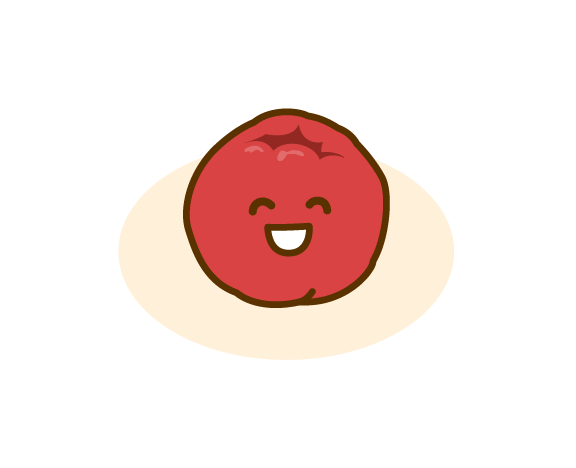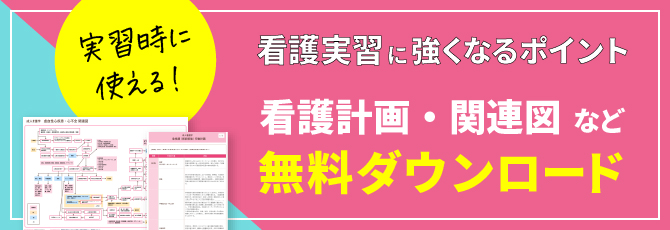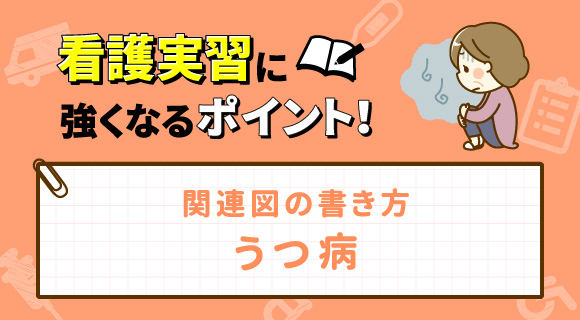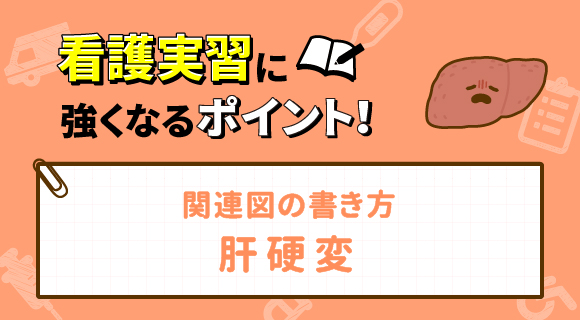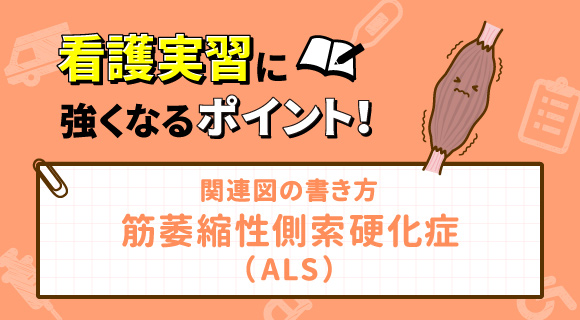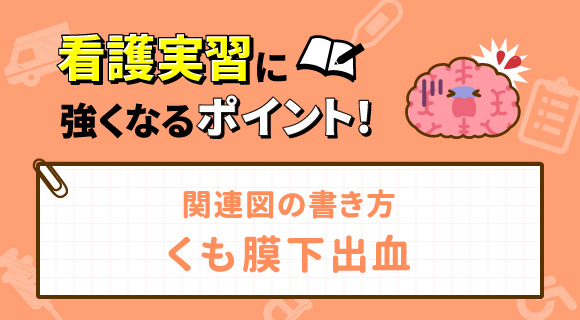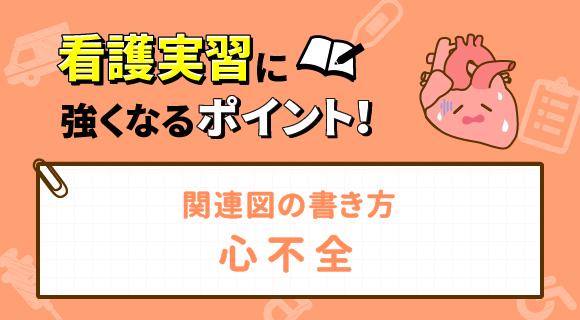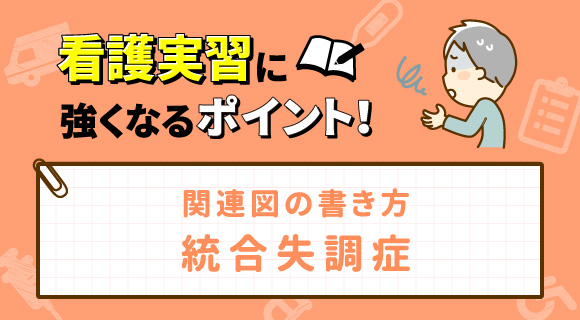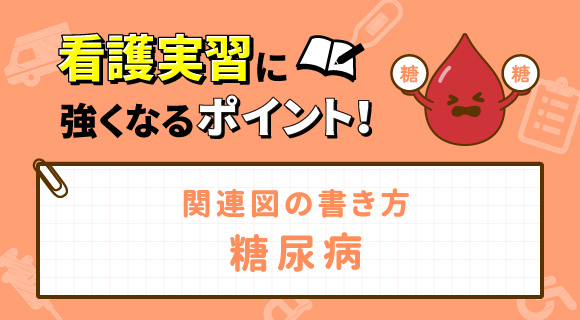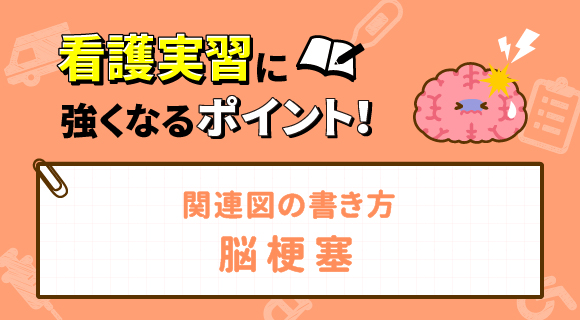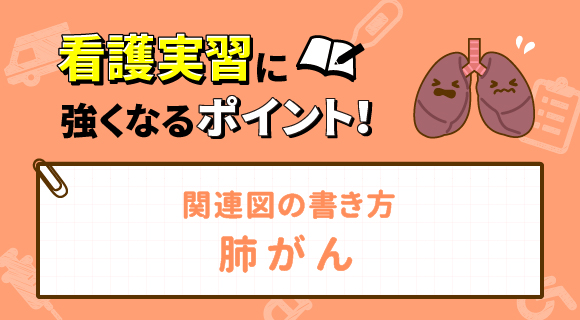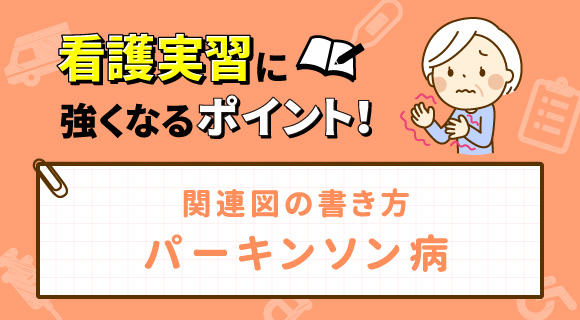大腸がんとは、大腸の粘膜から発生する悪性腫瘍の総称です。
大腸は結腸と直腸から構成されており、大腸がんは全ての粘膜で発生のリスクがあります。日本人では大腸がんの約70%がS状結腸と直腸に発生しています。また、男女比はやや男性に多く、大腸がんは40代から増加傾向となる疾患です。
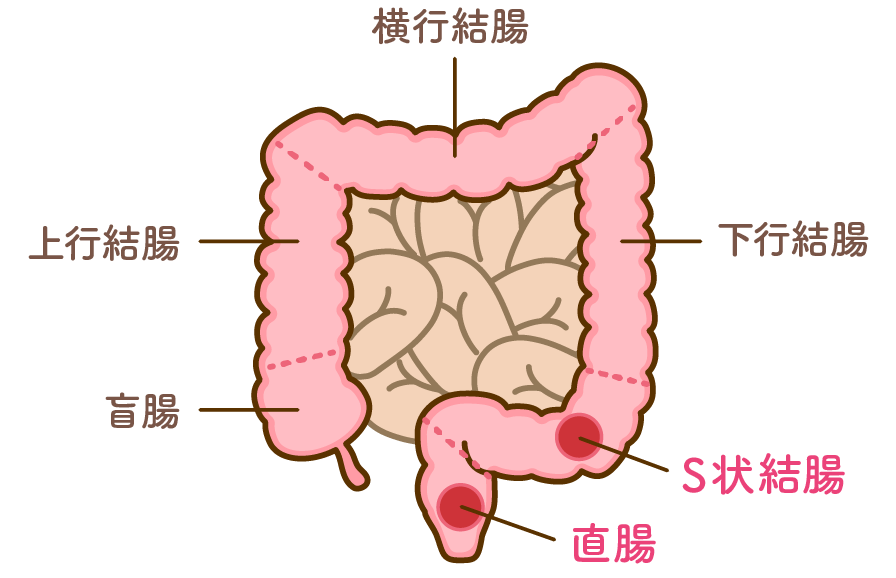
大腸がんは良性ポリープの腺腫が大きくなる段階でがん化する場合と、正常な大腸粘膜が直接がん化する場合があります。また、潰瘍性大腸炎やクローン病の既往も発症リスクが高いです。
発症しやすい生活習慣の要因として、高脂肪や低繊維の食事、アルコールの多量摂取、喫煙、運動不足などが挙げられます。
大腸がんの早期のものは無症状のことが多く、進行すると以下の症状が出現します。
- ・血便・下血
- ・排便習慣の変化(便秘・下痢)
- ・便が細くなる(狭小化)
- ・体重減少
- ・食欲低下
- ・腹痛
- ・腹部膨満感
①腹膜播種
大腸粘膜から大腸壁まで広がり、腹腔内にがん細胞が散らばる。
②リンパ節転移
大腸壁の中を流れるリンパ液に乗ってリンパ節に辿り着き、増殖する。
③血行転移
血液により他の臓器に転移する。好発部位は肝臓・肺が多く、骨や脳など全身に転移することもある。
大腸がんの進行度は病期(ステージ)で表されます。病期はがん実質の大きさではなく、大腸壁への深達度や浸潤の程度、転移の有無で決まり、以下の通りステージ0~Ⅳの5段階に分類されます。
| 0 | 大腸粘膜内に留まるもの。 |
|---|---|
| Ⅰ | 固有筋層までに留まるもの。 |
| Ⅱ | 固有筋層を超えて浸潤するもの。 |
| Ⅲ | 深さに関わらずリンパ節への転移を認めるもの。 |
| Ⅳ | 深さやリンパ節転移に関わらず、多臓器への転移を認めるもの。 |
一般的に大腸の粘膜や粘膜下層に留まるものを「早期大腸がん」、固有筋層よりも深い層に達している場合を「進行大腸がん」と呼びます。
| Tis | がんが粘膜内に留まる。 |
|---|---|
| T1 | がんが粘膜下層まで浸潤している。 |
| T2 | がんが固有筋層まで浸潤している。 |
| T3 | がんが固有筋層を超えて浸潤している。 |
| T4 | がんが漿膜表面もしくは漿膜を破って腹腔に露出している。 |