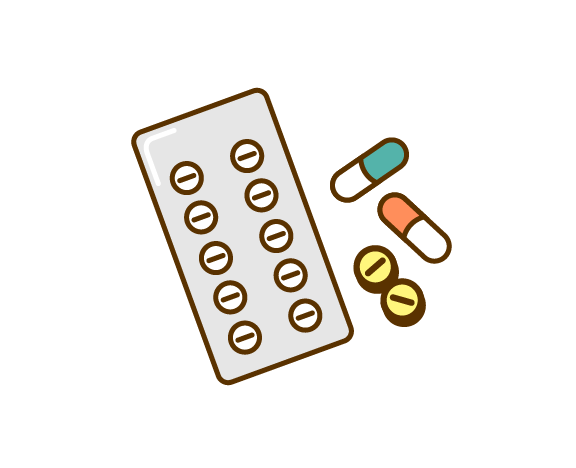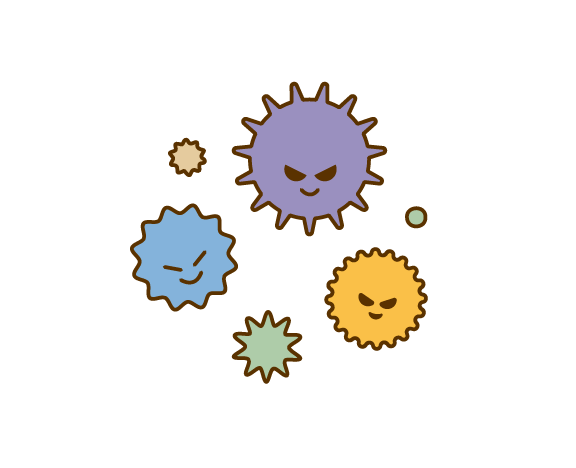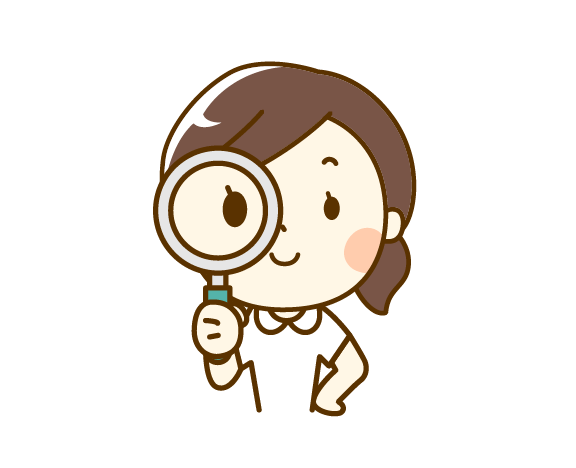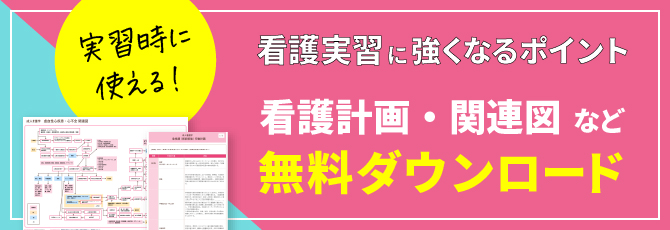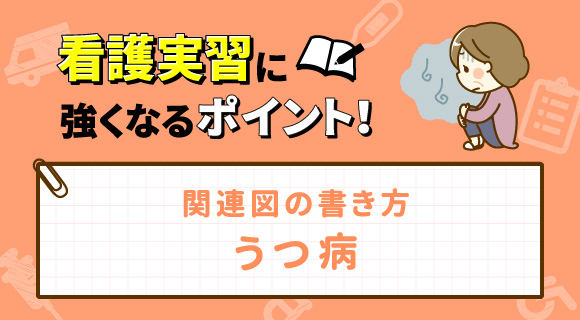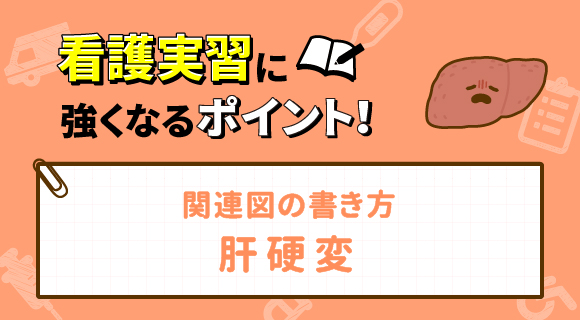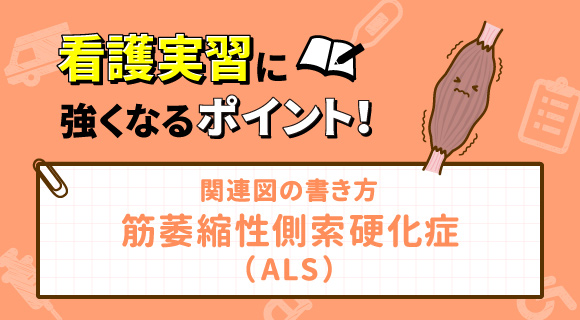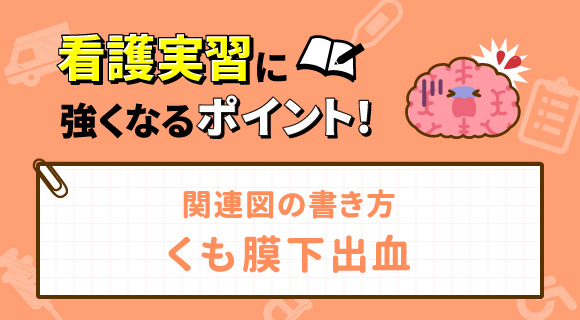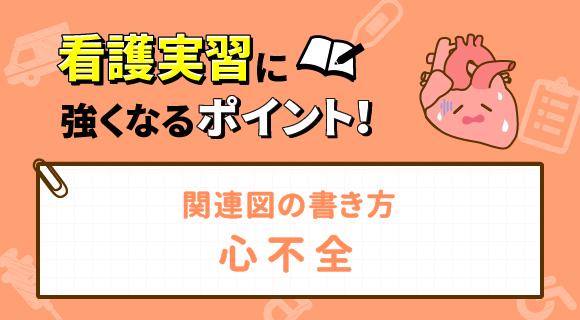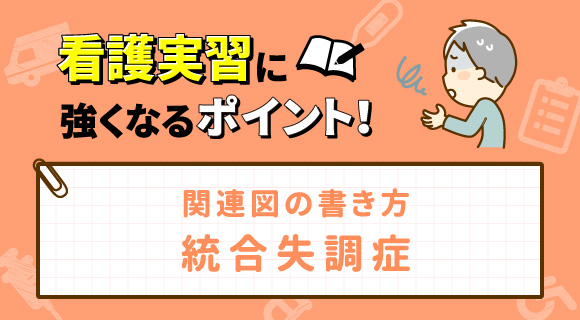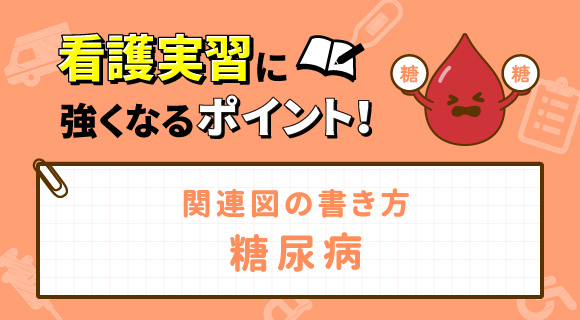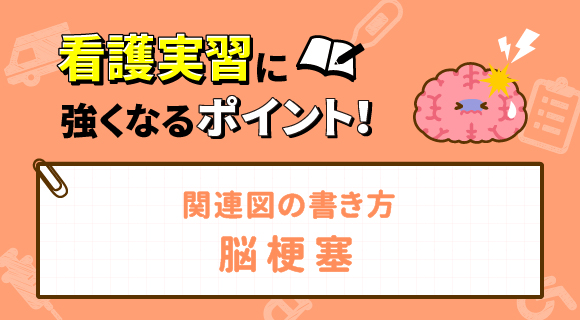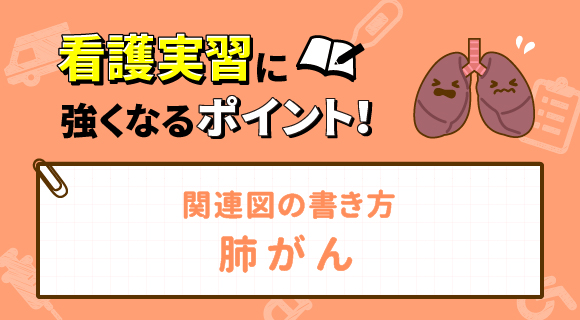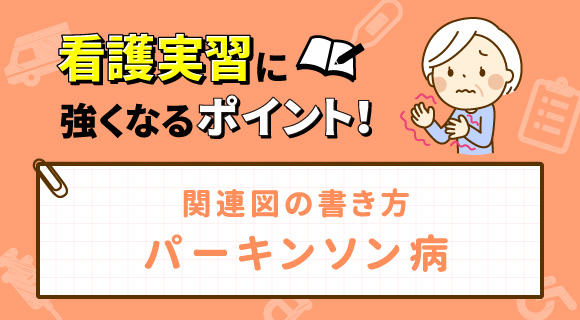大腿骨頸部骨折とは、大腿骨の頸部に起こる骨折のことです。股関節に起こる骨折のほとんどが、大腿骨頸部あるいは大腿骨転子部や転子下で発生しています。
大腿骨頸部骨折は、60歳以上から徐々に増え始め、70歳以降で急増します。閉経後の60歳以上の女性に圧倒的に多くみられ、男性では80歳以上の発症率が高くなります。
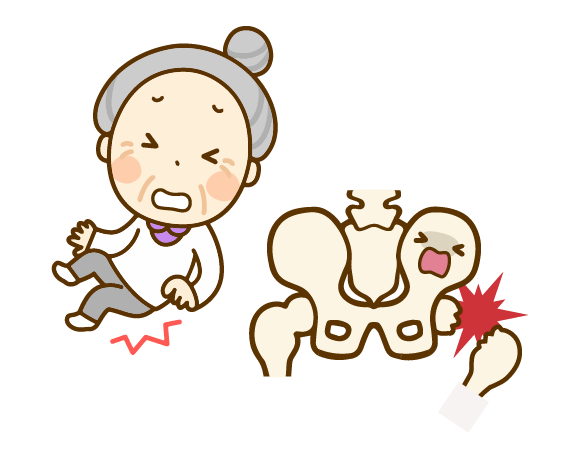
骨折の原因は転倒によるものが多く、若年者でも高所からの転落や交通外傷で起こることがあります。多くは骨粗鬆症で骨がもろくなっている高齢者にみられ、軽く尻もちをついた程度の弱い外力でも骨折を起こすことがあります。
①疼痛
骨折直後から自動運動不能になり、股関節部の疼痛を訴えます。患肢を外旋させると局所に疼痛があり、触診により大腿骨頸部前面で圧痛を認めます。
②腫脹・皮下出血
大腿骨頸部骨折の場合は、関節内骨折であるため、腫脹や皮下出血は少ない傾向にあります。転子部骨折の場合は、大転子部から臀部にかけて腫脹や皮下出血が出現しやすいです。
大腿骨頸部骨折の分類法では、Garden分類が最も多く使われています。以下の通り、stageⅠ~Ⅳの4段階に分類されます。
| Ⅰ | 不完全骨折でひびが入った状態。 |
|---|---|
| Ⅱ | 転位を伴わない完全骨折の状態。 |
| Ⅲ | 転位を伴う完全骨折の状態。 |
| Ⅳ | 高度の転位を伴う完全骨折の状態。 |