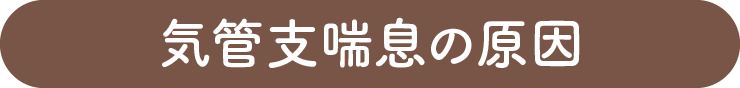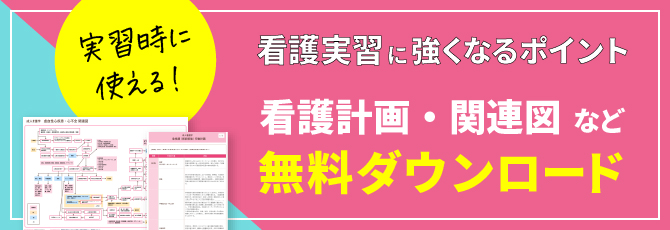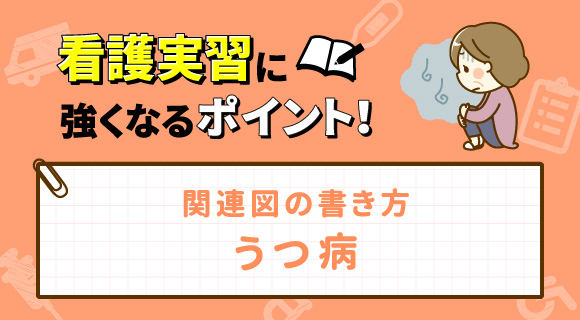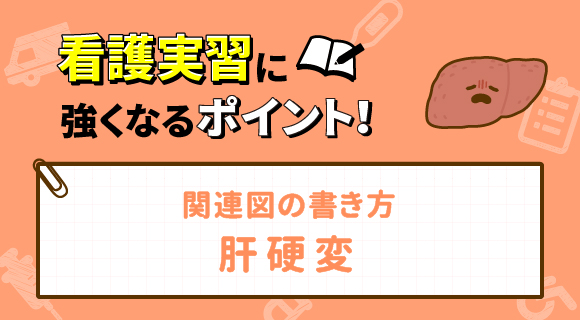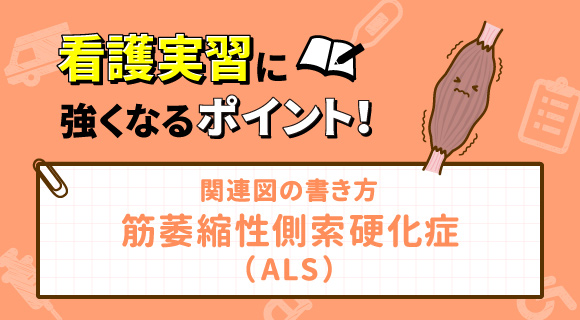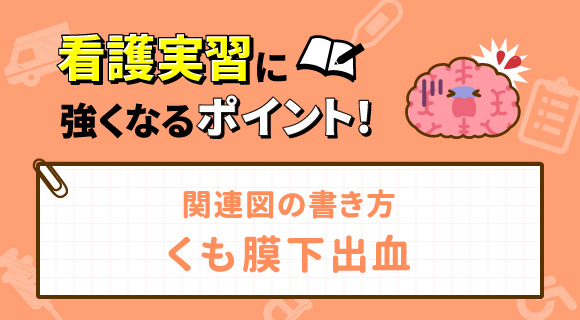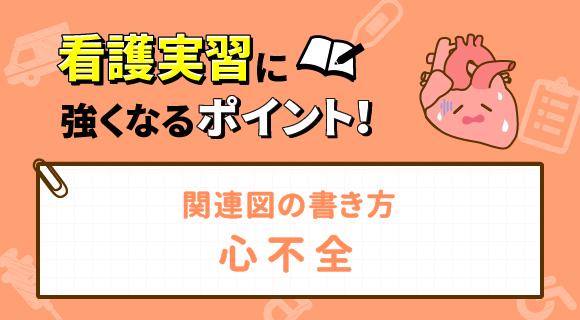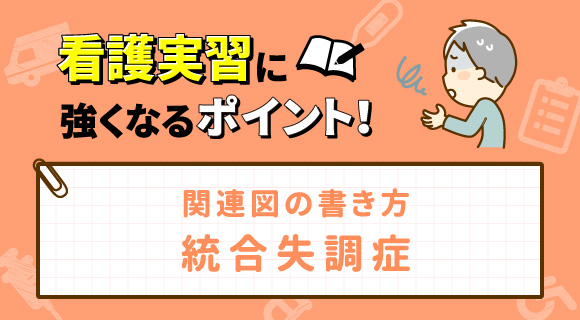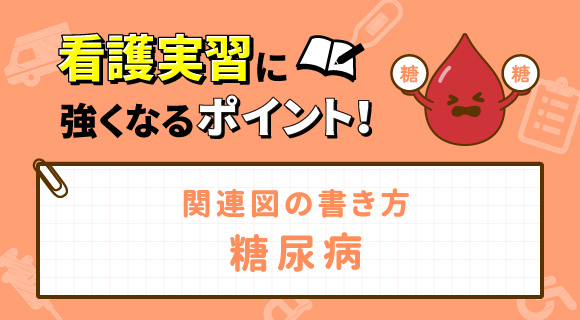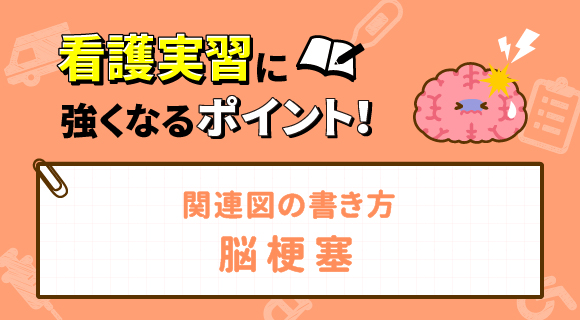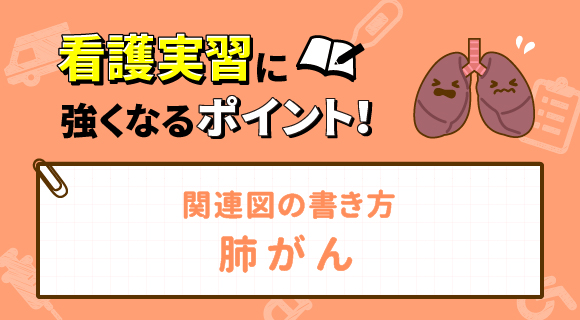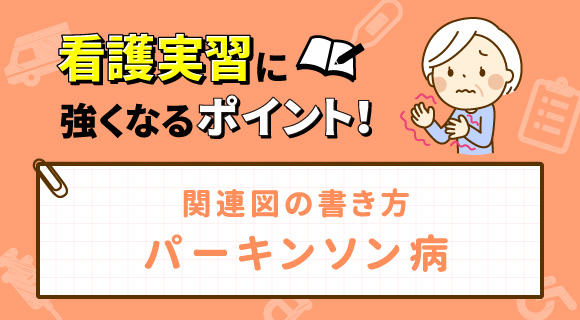気管支喘息とは、空気の通り道である気管支が慢性的に炎症を繰り返すことで狭くなり、呼吸時にヒューヒューやゼーゼーといった異常音が発生する喘鳴や、呼吸困難などの発作が生じる病気です。
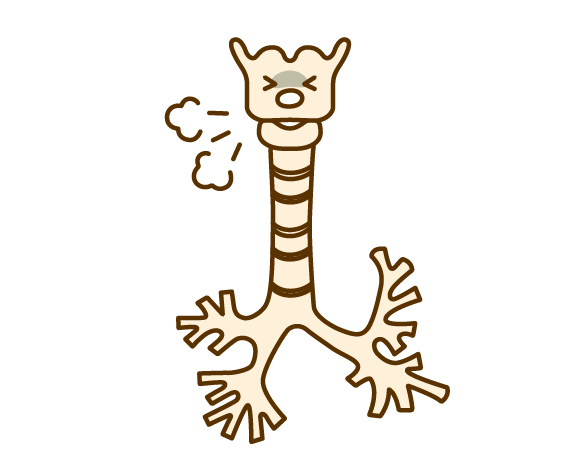
成人では40~50代での発症が多く、発病する要因は遺伝因子と環境因子が関与しています。
遺伝因子
家族に気管支喘息やアレルギー体質の人がいる場合、発病する確率が高くなります。
環境因子
アレルギーの原因物質であるアレルゲンのダニ、ほこり、花粉、カビ、ペットの毛の吸入やウイルス感染症のほか、大気汚染、喫煙、食品添加物、薬物、アルコールなども原因となることがあります。そのほかにも低気圧や刺激臭、過労やストレスなどは症状を悪化させます。
気管支喘息の治療では、気道の炎症を抑えて、発作が起きないようにコントロールすることが重要です。発作を繰り返すと気道粘膜が肥厚し、狭窄した気道が戻らなくなってしまう可能性があります。
喘息の治療薬は、発作が起きないようコントロールする長期管理薬と、発作が起きた時に緊急的に使用する発作治療薬の2つに分類されます。
長期管理薬
気道過敏性を抑え、喘息発作が生じないように気管支の状態を保つことを目的とした薬剤です。主に気道の炎症を抑える作用のあるステロイド吸入薬が使用されます。状態に応じて、抗ロイコトリエン薬やテオフィリン製剤、長時間作用型β2刺激薬などが組み合わされます。
発作治療薬
実際に喘息発作が起きた時に使用し、症状を改善させる薬です。喘息の発作が起きた場合は、即効性のある短時間作用型β2刺激薬を吸入し、狭窄した気管支を広げて症状を抑えます。強い発作が持続する場合は、テオフィリン製剤やステロイド薬の点滴、アドレナリン皮下注射なども使用されます。