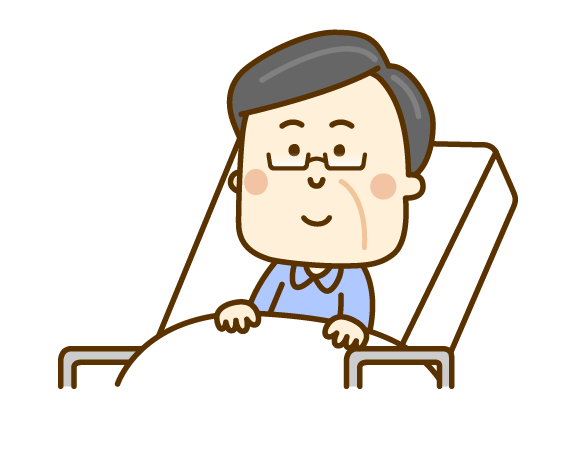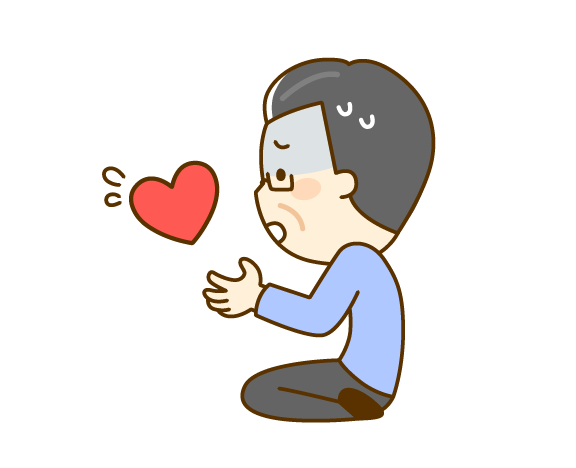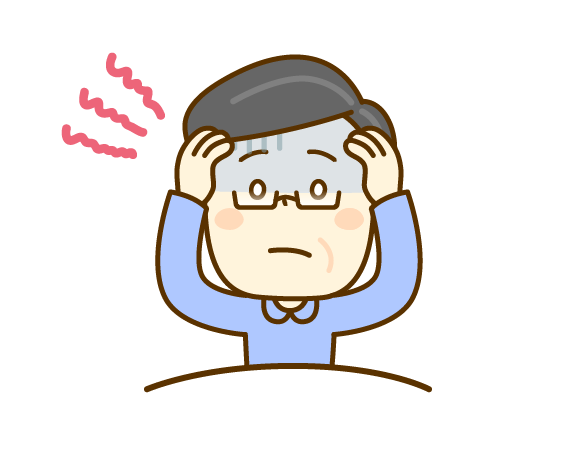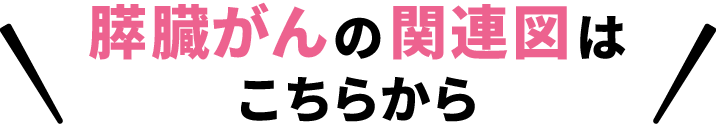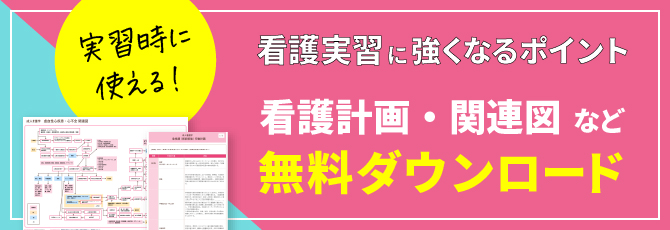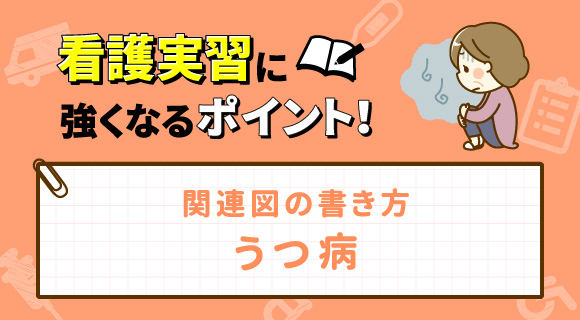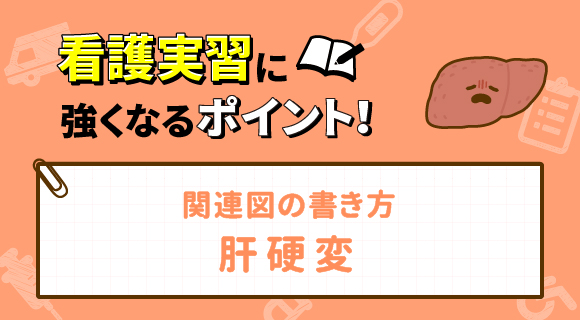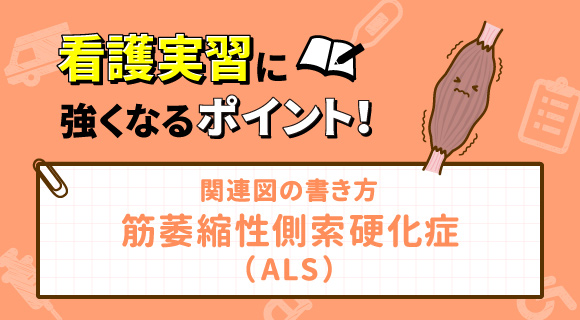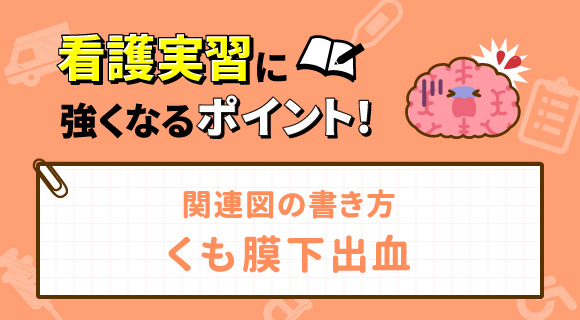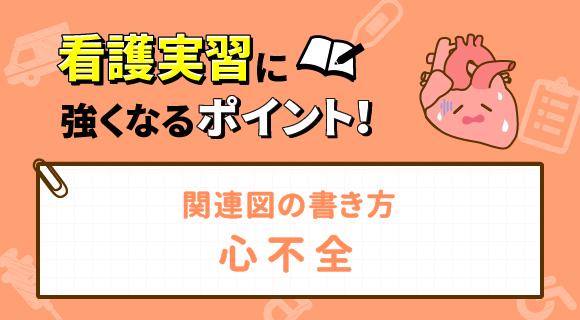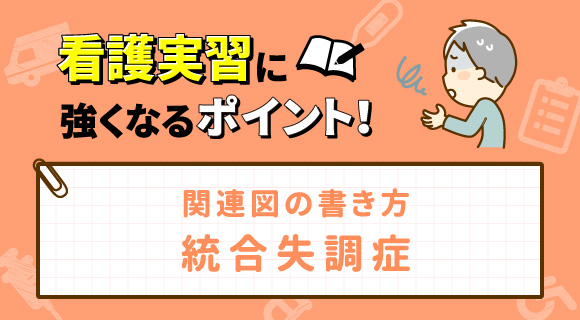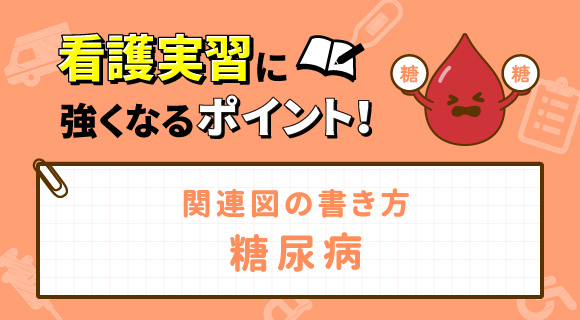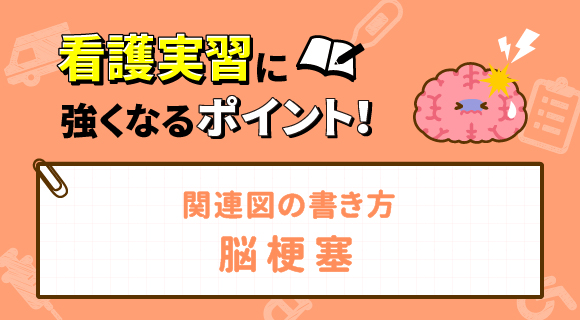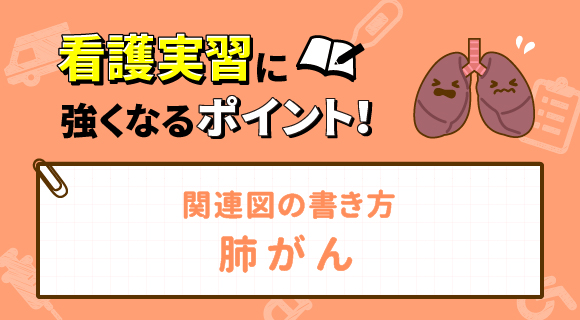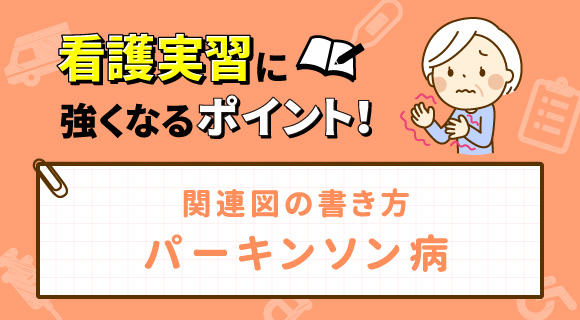膵臓がんとは膵臓に発生する悪性腫瘍のことです。通常膵臓がんとは転移・浸潤しやすい膵管がんのことを指します。膵臓の周りにあるリンパ節や肝臓に転移しやすく、腹部にがん細胞が散らばって腹膜播種がみられる場合も多いです。
膵臓は内臓の最も背中側にあるため、膵臓がんは早期発見が難しく病状が進行した状態で発見されることがほとんどです。
そのため他のがんと比べて予後が悪く、発生率が少ない割にがんによる死亡原因は国内第4位を示しています。
年齢は60歳代から高齢になるほど多くなり、性別はやや男性に多い傾向があります。
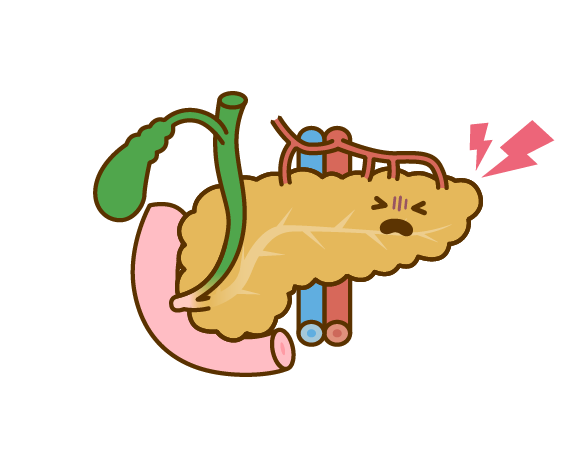
原因としては、膵臓がんの家族歴、膵臓の合併疾患(糖尿病、慢性膵炎)、嗜好品(喫煙、飲酒)などです。糖尿病は膵臓がんに罹患した人の半数以上にみられます。
主な症状は腹痛や腰背部痛、食欲不振や体重減少、黄疸などです。糖尿病を発症することや、急な悪化がきっかけで発見されることもあります。
腫瘍ができた部位によっても症状は異なります。膵頭部にできたがんは胆管が狭くなるため、黄疸が現れやすくなることが特徴です。さらにがんが進行している場合は腹水がみられることもあります。
一方、膵体部や尾部のがんは胆管に影響が及びにくいため黄疸は現れにくいです。そのため、膵頭部にできたがんよりもさらに発見が遅くなる場合があります。