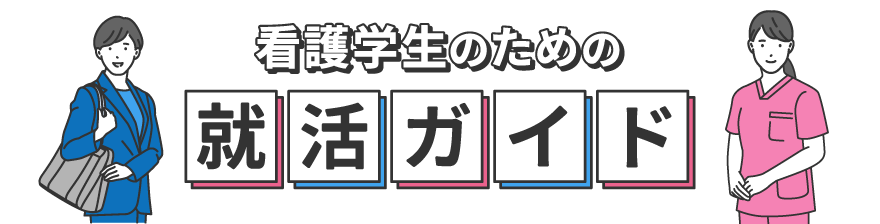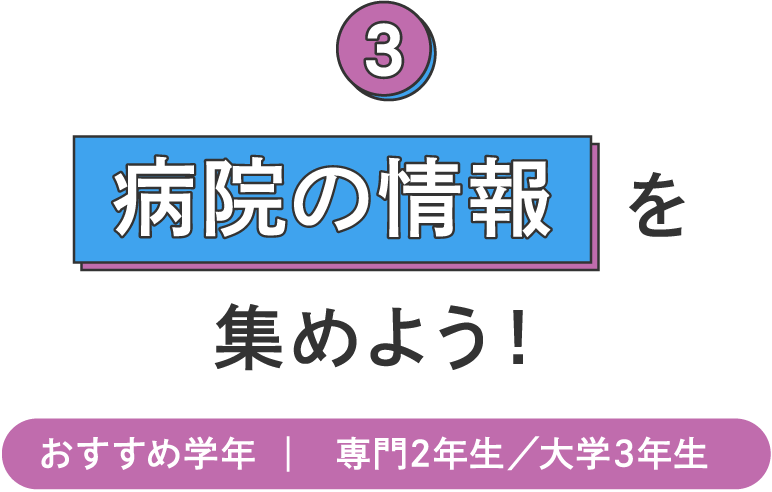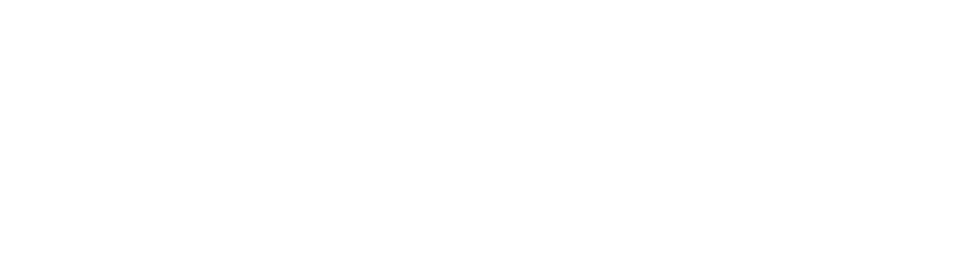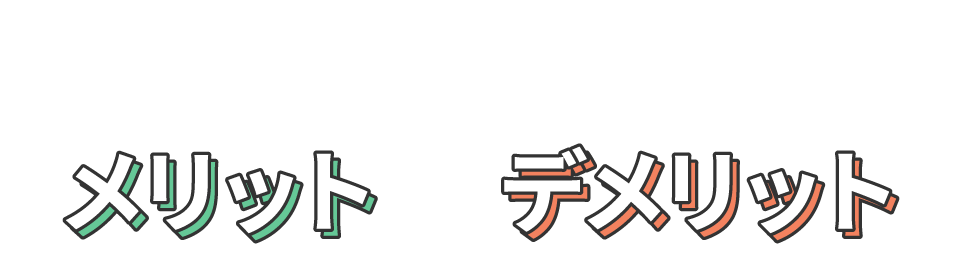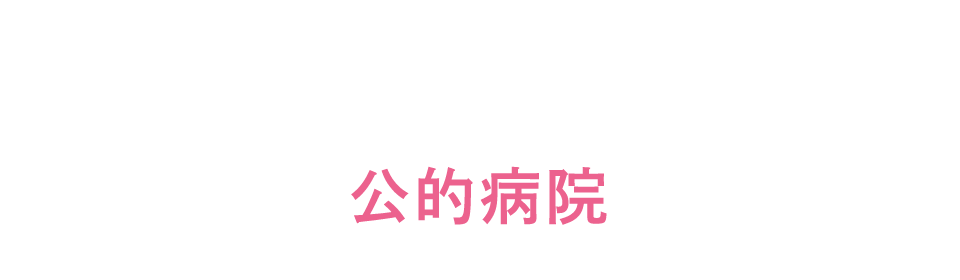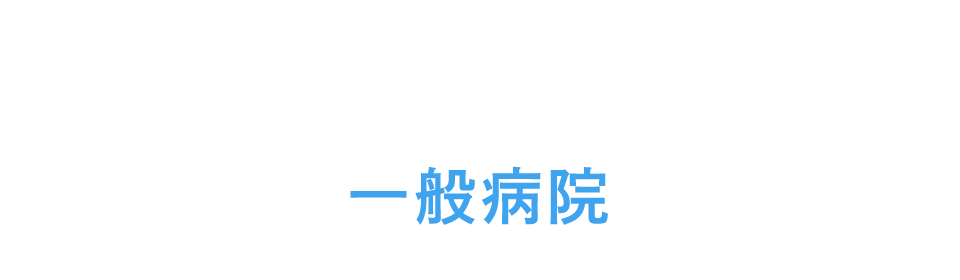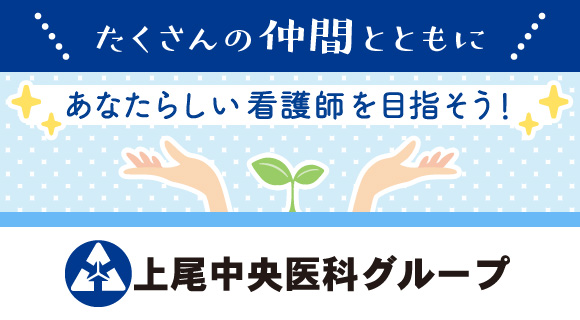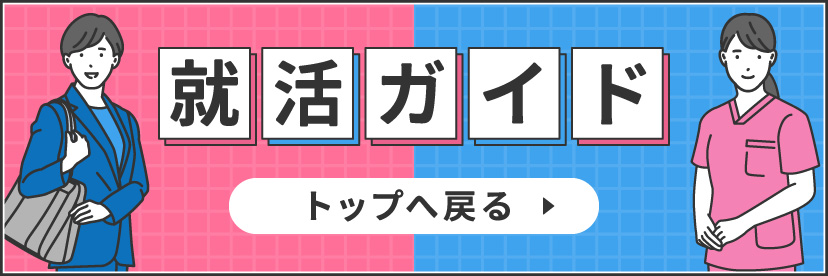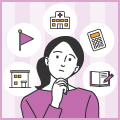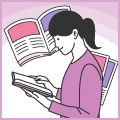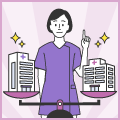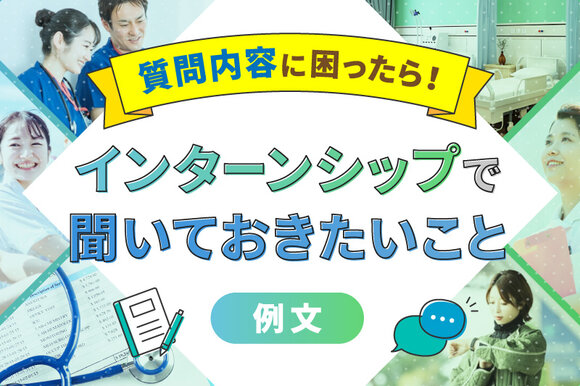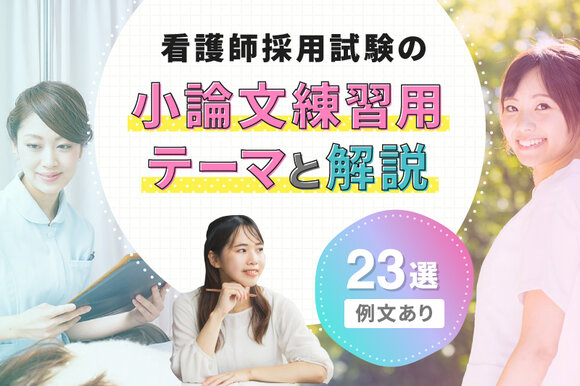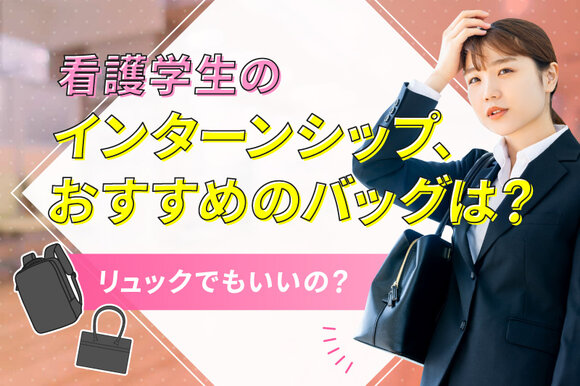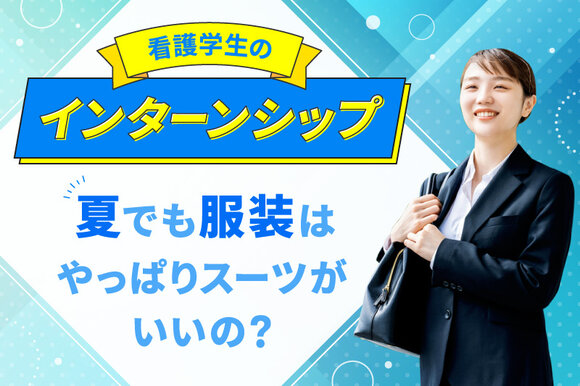グループ病院とは日本各地に病院・診療所・介護施設などを持ち、
総合的な医療サービスを展開している病院を指します。
同じグループの病院でも総合病院や、専門性に特化した病院、
地域性を考慮した病院など、病院機能により役割を分けています。
公的機関の公的病院と、民間の医療法人が運営している一般病院など、
規模はさまざまですが大きなグループでは以下の病院があります。
(2021年3月時点の病院数)
理想の看護を追求できる
全国各地にさまざまな機能の病院や施設を展開しているため、転勤や異動ができます。入職後は経験を重ねるにつれて目指したい看護が変わっていきます。より専門性の高い看護をしたい、あの地域の医療に貢献したいなど、あなたが目指す理想の看護を追求できます。結婚など、転居を伴わなくてはならないライフイベントの際にも、キャリアを継続したまま転勤することができます。
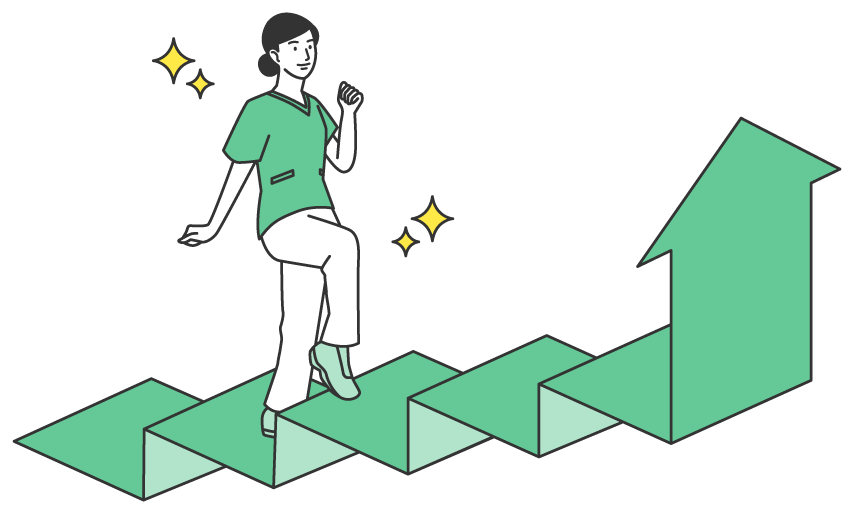
グループ共通の制度
グループ病院は病院の数が多く、職員数も多いため、共通の制度を設けています。グループ独自の教育制度などを共通化し、どの病院で働いても同じ教育や研修を受けることができます。待遇面でも給与や手当、福利厚生などの条件が共通していることが多く、地域差からくる待遇の違いはありません。

経営が安定している
グループ病院はさまざまな機能の病院や施設を持っているため、経営が安定している傾向にあります。手術・入院、その後の転院先の選定などもグループ内の病院でまかなうことができます。仮に、1つの病院の経営が悪化したとしても、他の病院が好調であればグループ全体での経営を維持することができます。

転勤・異動がある
メリットとしてもあげた内容ではありますが、大きな組織であるため、転勤・異動は想定されます。
キャリアアップや役職を目指すには、教育の一環としてほかの病院での経験を積ませることがあります。望まない異動や転勤の辞令が出る場合もありますので、病院を選ぶ段階で確認しておくとよいです。

独立行政法人 国立病院機構(NHO)
国立病院機構は、もともと国立病院や国立療養所であり職員の身分は国家公務員でしたが、2014年に厚生労働省所管の特定独立行政法人となったことで職員の身分も非公務員となりました。日本最大の規模を誇る国立病院機構は、全国で6つのグループを展開し、141病院を運営しています。がんなどの高度先駆的医療、災害医療や国際的感染症への対応など、民間では対応が困難な医療や、国をあげて取り組むべき政策医療を展開するとともに、救命救急センターなどの急性期型から、回復期、慢性期など地域のニーズに応じた医療提供を行っています。
日本赤十字社
日本赤十字社は、「苦しんでいる人を救いたい」という想いを実現するために、全国92病院の運営をはじめ、看護学校の運営、国内災害救護、災害や紛争に苦しむ人々を救うための国際活動、献血などの血液事業など、さまざまな事業を展開しています。
赤十字病院グループでは、救急医療、高度専門医療、生活習慣病の予防や介護支援、災害時における国内外への医療チーム派遣など、さまざまな活動を行っています。急性期病院、療養病院、そして地域医療支援病院など、地域の中核病院として地域に根差した医療を提供している一方で、大規模災害時などにおける救護活動に備えて、救護班や備蓄品を配備し、国内外に医師や看護師を派遣できる体制を整えています。
独立行政法人 労働者健康安全機構 労災病院グループ(JOHAS)
厚生労働省所管の法人である労災病院グループは、全国に32病院あります。各労災病院では、地域の中核病院として全ての働く人の職業生活を医療面から支えるために、労働者の健康をサポートしています。具体的には、予防から治療、リハビリ、職場復帰に至る一貫した専門的な医療提供や、職場における健康確保のための活動支援になります。看護師をはじめとした全スタッフは、最新で高度な医療を提供するとともに、患者さま中心の温もりのある「患者サービス」の提供に努めています。
社会福祉法人恩賜財団 済生会
済生会は、生活困窮者を救済するために明治天皇によって設立されました。日本最大の社会福祉法人として、40都道府県で医療・保健・福祉活動を展開しています。経済的に困っている人の医療費を無料にしたり、減額したりする「無料定額診療事業」を積極的に行っているのが大きな特徴のグループ病院です。災害時には救命救急から慢性期だけではなく、生活再建に向けた支援活動を展開しています。医療・保健・福祉を総合して提供できる団体として、すべての資源(施設・設備・人)を動員してシームレスなサービスを提供しています。
独立行政法人 地域医療機能推進機構(JCHO ジェイコー)
JCHO(ジェイコー)グループは、全国57病院と介護施設、訪問看護ステーションなどを有する厚生労働省所管の組織です。救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療の5事業、その他、地域医療の抱えている課題やニーズを受け止め、必要とする医療および介護を提供しています。とくに地域包括ケアの推進、全国ネットを活かしたへき地への医師派遣や災害医療の支援に力をいれており、「地域医療の要」としての役割を担っています。
公益社団法人 地域医療振興協会(JADECOM)
地域医療振興協会は、地域医療を支援することで地域の振興を図ることを目的に設立されました。「いついかなる時でも医療を受けられる安心を、すべての地域の方にお届けしたい」という信念のもと、山間や離島といった「へき地」など地域医療の確保が厳しい自治体から委託を受けて、病院、診療所などの運営を行っています。へき地への医師派遣・代診医派遣や地域医療を担う総合医の育成、看護専門学校での看護師育成など教育面でも力を入れています。
国家公務員共済組合連合会(KKRグループ)
KKRグループは、国家公務員が加入する共済組合の連合組織で、病院運営のほか、年金管理や運営事務を行っています。
全国にある33病院は、組合員とその家族への医療サービスの提供を目的に設立され、同時に一般にも公開されています。
地域医療や国への政策医療への貢献、DMATの活動など、職員一人ひとりが専門性を高め、患者さまへ質の高い医療を提供できるように努めています。
徳洲会グループ
全国65ヶ所ある徳洲会グループは、「いつでも、どこでも、誰でもが最善の医療を受けられる社会」を目指して、年中無休24時間オープンで救命救急医療に取り組み、予防医療・慢性医療・先進医療に至るまで、地域住民の要望に応える医療を提供しています。離島・へき地医療に力を入れており、離島への診療所開設や医師の応援を行っています。介護・福祉に対する取り組みや、国際医療貢献、災害医療活動(TMAT)も盛んに行っています。
全日本民医連(民医連)
民医連は、戦後、医療に恵まれない労働者や農民、低所得者の医療要求に応えるため、地域住民と医療従事者が協力して、全国に作られた民主的な医療機関です。設立以来、地域住民の身近な医療機関として活動しています。医療制度を改善する運動もすすめ、差額ベッド料はいただいていません。現在、全日本民医連に加盟する医療機関をはじめとした事業所は、全国47都道府県にあり、医療・介護・福祉分野の活動を活発に行っています。
中央医科グループとは、首都圏を中心に93病院の経営を行う、IMS(イムス)グループ、戸田中央メディカルケアグループ(TMG)、上尾中央医科グループ(AMG)の3グループを指します。
IMS(イムス)グループ
IMSグループは、東日本を中心に140施設(うち、病院は36病院)の運営を通し、一貫した医療・介護を提供している総合医療・福祉グループです。予防医学から救命救急・治療・リハビリテーション・介護・在宅支援までの一貫した総合医療の提供と、地域に根差した地域住民の皆さまのための地域医療の提供を心掛けています。
戸田中央メディカルケアグループ(TMG)
戸田中央メディカルケアグループは、首都圏に29病院と6つの老人保健施設のほか、特別養護老人ホーム、クリニック、健診センター、訪問看護ステーションなど、合計120ヶ所の関連事業所を展開する医療グループです。超高齢社会を迎えるにあたり、病院機能の分化、在宅医療の推進、多職種協同チームにて、患者さまに最適な医療提供を行っています。
上尾中央医科グループ(AMG)
上尾中央医科グループは、首都圏を中心とした1都6県に28の病院と21の介護老人施設などを運営しています。高度急性期~地域包括ケアまで、質の高いトータルケアを地域の皆さまへ提供しています。患者さまはもちろん、ご家族の皆さまや地域の皆さまとのコミュニケーションを大切に、職員からも「愛し愛される病院・施設」であることを目指しています。