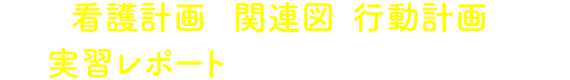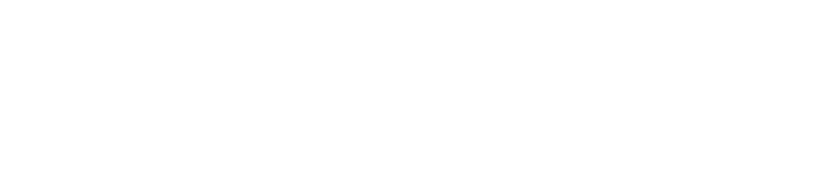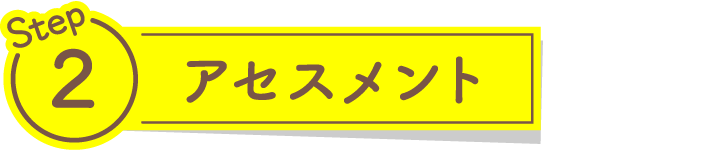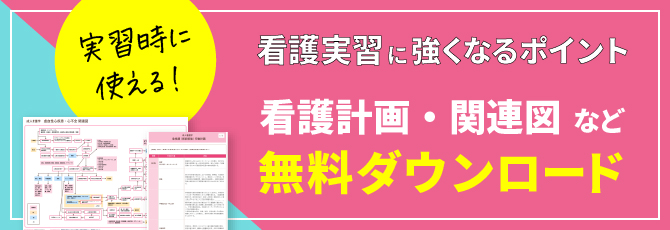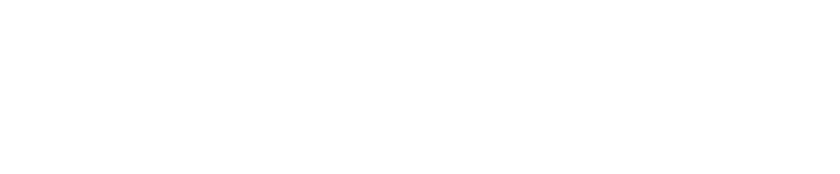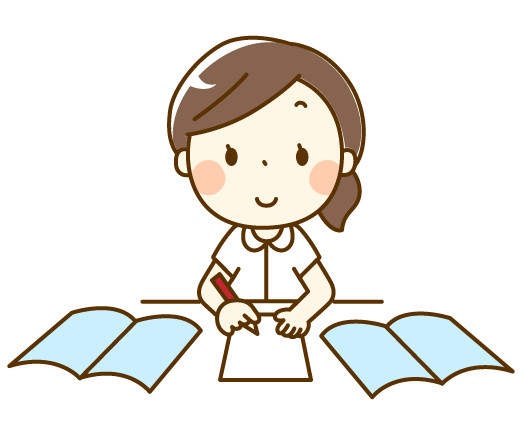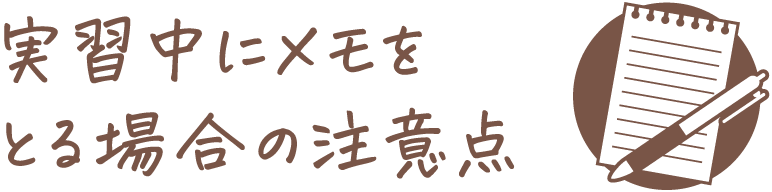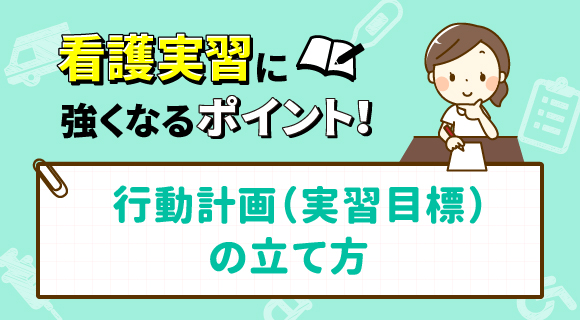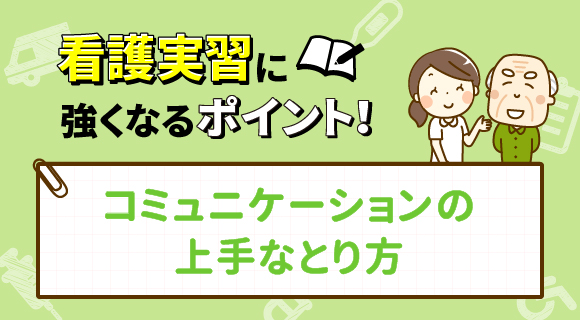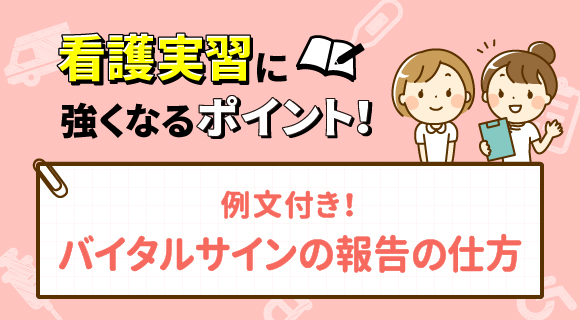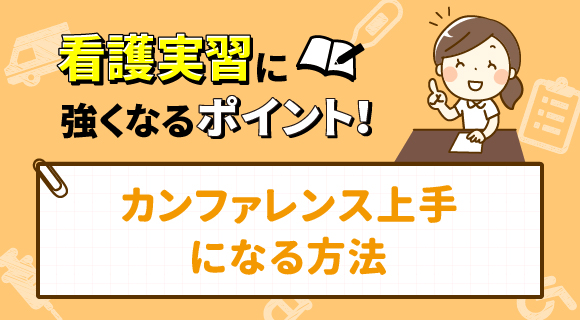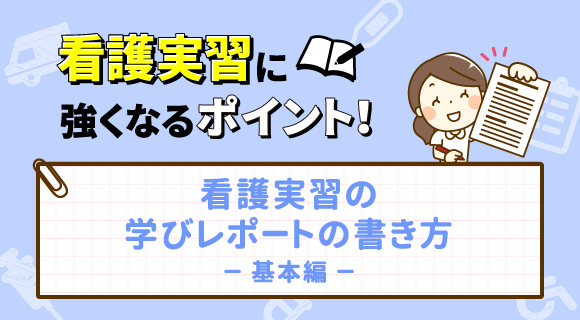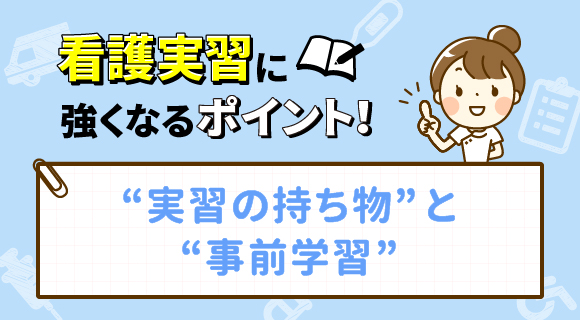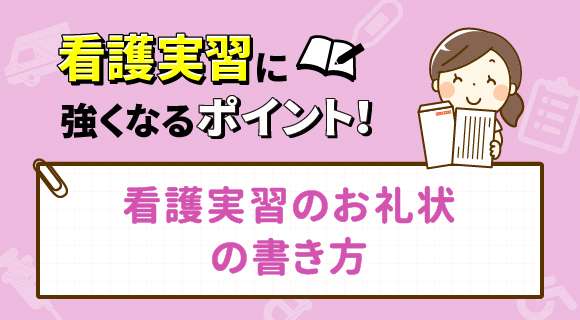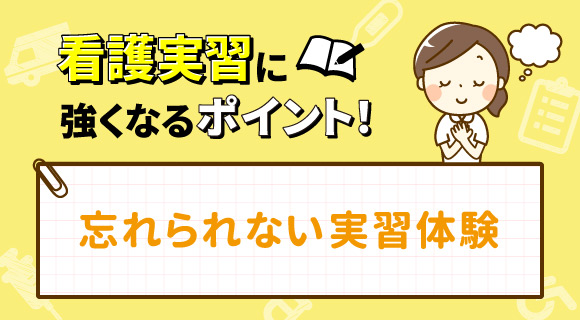実習で好成績をとるためには、実習記録を充実させることが最も大切です。
ただ情報をたくさん書けば良いという事ではなく、患者さまの病態を正しく理解し「個別性」=「具体性」を上手に盛り込むことが必要です。
以下①~④までのステップを意識して取り組むと、だれでも好成績をとれる実習記録が書けますので、ぜひ参考にしてみてください。
- 患者さまの基本情報はカルテから収集する(現病歴、既往歴、入院までの経過も忘れずに確認)
- カルテから収集できなかった情報は、リストアップして患者さまに聞く
- 患者さまの表情や様子、ベッドサイドからも情報収集する

やみくもに患者さまと話しているだけでは、時間がもったいないだけ!
集めた情報は後から関連図に反映するので、意識しながら収集しましょう。
集めた情報は後から関連図に反映するので、意識しながら収集しましょう。
- S情報(患者さまの発言や言葉のみ)とO情報(診察や検査から得られた事実)を正しく理解し、簡潔に記述する
- さまざまな文献を使用して根拠を調べる(雑誌や書籍を参考にしてみるのもOK)
- アセスメントの際、情報が不足していたら翌日情報収集する
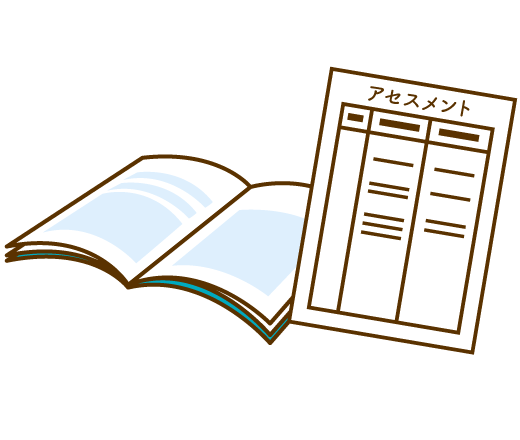
アセスメントが感想文にならないように注意しましょう!
集めた情報から"患者さまは、現在の状態から今後どうなっていくのか?"という予測や、リスクに対する自分の考えをしっかり記述することが大切です。
集めた情報から"患者さまは、現在の状態から今後どうなっていくのか?"という予測や、リスクに対する自分の考えをしっかり記述することが大切です。
- すべて自分で書こうとせず、参考書などを活用する。先生にアドバイスをもらうのもgood!
- 見やすくするために、色分けしたり、付箋を用いて修正を効率的に行う
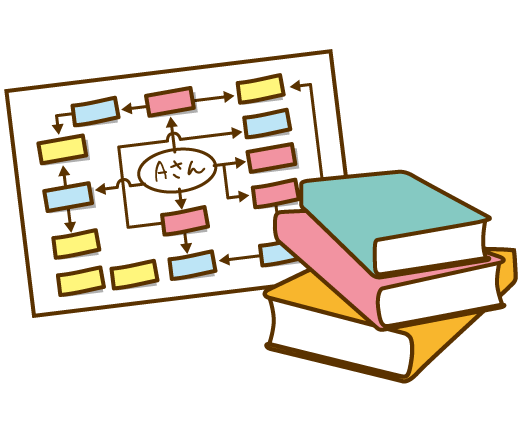
個別性を持たせるためには、入院による変化、生活習慣、家族背景、治療について、患者さま自身について記入すると、その患者さま特有の問題が見えてきます。
- 看護目標・看護計画は、自分以外の人が見ても理解できるかを意識する。回数・数値など入れて具体的に記述する
- 看護計画は、疾患だけを観るのではなく、患者さまが暮らしてきた環境、気にしていること、家族・介護者の様子など、患者さま自身に注目することで個別性が見えるようになる
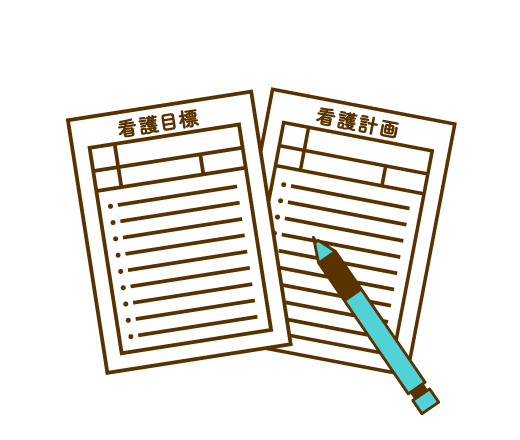
参考書の内容をそのまま使用してしまうと、患者さまの「個別性」=「具体性」が見えてきません。
関連図を利用し、主疾患と副疾患に共通する症状や徴候を探してみると、すぐに個別性は見つかります。患者さまの他の疾患と絡めてアレンジすると、より「個別性」が見えてきます。
関連図を利用し、主疾患と副疾患に共通する症状や徴候を探してみると、すぐに個別性は見つかります。患者さまの他の疾患と絡めてアレンジすると、より「個別性」が見えてきます。